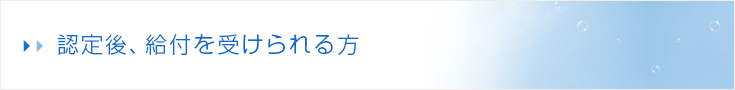
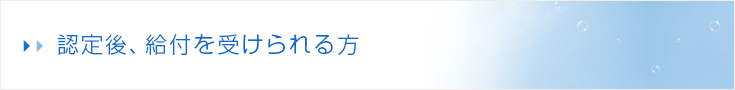
各種請求の手続き
「認定を受けた方が亡くなられた場合」または「認定申請を行い、認定前に亡くなられその後、認定を受けることができた者としての決定を受けた場合」、認定を受けた方の葬祭を行う方は「葬祭料」を機構に請求することができます。ご遺族の方は、次の給付を機構に請求することができます。
1) 未支給の医療費等
- ア 療養を開始した日※から亡くなられた日までの医療費及び療養手当で、まだ支給されていなかったもの
- イ ※「療養を開始した日」とは、認定を受けた疾病について初めて保険医療機関等において診療、薬剤の支給等健康保険法等の適用となる医療を受けた日をいいます。ただし、認定申請のあった日の3年より前に受けた医療については、救済給付の対象とはなりません。
2)救済給付調整金
医療費及び療養手当並びに未支給の医療費等の額の合計額が280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たない場合、その差額分
なお、第三者による交通事故など、認定を受けた疾病に起因しない場合は、「葬祭料」及び「救済給付調整金」は支給されません。
これらの救済給付を請求するには、死亡届及び石綿健康被害医療手帳返還届を提出する必要があります。届出についての詳細は、こちらを参照してください。
葬祭料の請求
1)葬祭料とは
認定を受けた方または「認定の申請中に死亡した方で認定を受けることができる方であったとの決定を受けた方」(以下、「被認定者」という。)が認定を受けた疾病に起因して死亡した場合に、葬祭を行う方の請求に基づき支給されます。
2)葬祭料の請求
葬祭料を請求しようとする方は「葬祭料請求書」(手続様式第15号)(PDF、180KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。
に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。
3) 必要な添付書類
| 項目 | 添付書類 |
|---|---|
| 葬祭料請求書 (手続様式第15号) (PDF、180KB) (WORD、33KB) 手続様式第15号記載例(PDF、627KB) |
|
※1葬祭料を請求される方が、1.の添付書類を救済給付調整金または未支給の医療費等他の請求書に添付されているときはこれらの書類の添付は省略できます。その旨を葬祭料請求書の余白にご記入ください。
※2領収書や死体埋火葬許可書に請求者のお名前があることが必要です。
※3領収書の原本については審査後に返却いたします。
※4死体埋火葬許可書の施主欄に請求者のお名前があることが必要です。
この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。
4)葬祭料の支給
機構は「葬祭料請求書」について内容を審査し、給付決定額(定額)を請求者指定の口座に振り込みます。
5)請求できる期間
葬祭料を機構に対し請求できる期間は、被認定者が認定を受けた疾病に起因して死亡した日の翌日から2年以内です。
6)請求から支給までの流れ
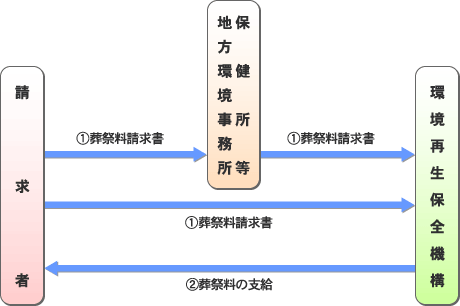
7)不服申立て
支給にかかる処分に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求することができます。
8)「葬祭料請求書」記載例
葬祭料請求書(手続様式第15号)記載例(PDF、627KB)![]()
未支給の医療費等の請求
1)未支給の医療費等とは
未支給の医療費等とは、被認定者が死亡した場合において、その死亡した被認定者にお支払いすべき医療費・療養手当(以下「医療費等」という。)でまだその方に支給していなかった医療費のことをいいます。この医療費の支払いについては、ご遺族の方が機構に対して請求できるものです。
お支払いをする医療費は、被認定者が療養を開始した日以降にかかった医療費の自己負担分で未払いのものです。また、療養手当は、被認定者が死亡した月の分まで支給されます。なお、認定申請の日の3年以前の医療費等は支払われません。
2)未支給の医療費等の請求
未支給の医療費等を請求しようとするご遺族の方は、「未支給の医療費等の請求書」(手続様式第14号)に必要事項を記入し、必要な添付資料を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。被認定者が死亡する前に医療費の支給を請求していなかった場合、未支給の医療費等を請求しようとするご遺族の方は、被認定者が自己負担した医療費を請求する場合と同様に、「医療費請求書」(手続様式第10号)に「高額療養費の支給額を独立行政法人環境再生保全機構が確認することに関する同意書」および医療機関に記載してもらった「受診等証明書」(手続様式第11号)を添えて提出していただきます。請求にあたってはこちらを参照ください。
書類は正確に記入してください。また、必要な添付書類に不備がないようご留意ください。
3)請求ができる遺族の方
死亡した被認定者の配偶者・子・父母・孫・祖父母又は兄弟姉妹であって、死亡した被認定者の死亡当時、生計を同じくしていた方が請求を行うことができます。(配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含みます。)
なお、生計を同じくしていた方の証明については、こちらをご参照ください。
4)請求の順位
請求の順位は下図の順序によります。先順位者が生存し、かつ生計を同じくしていた場合、後順位の方は請求できません。
なお、同順位者が2人以上の場合、同順位者の1人がした請求をもって全員が請求したこととなり、その請求者1人に対して行った支給は、全員に対して支給したこととなります。二重請求や分割支給はできません。
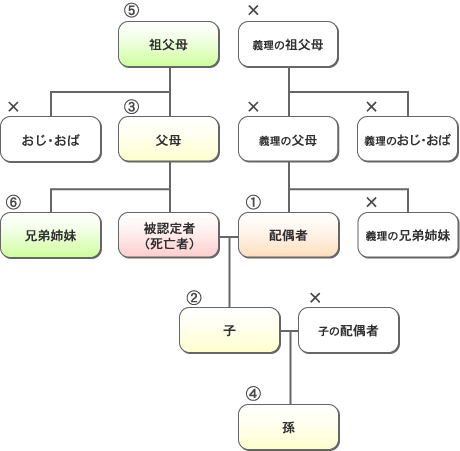
1~6の番号が請求順位です。
×のついている方は、請求権がありません。
5)未支給の医療費等の決定及び支給
機構は、「未支給の医療費等の請求書」について内容を確認し、給付の可否を決定し、請求したご遺族の方に書面で通知します。支給決定された方については、給付決定額を請求者指定の口座に振り込みます。
6)請求から支給までの流れ
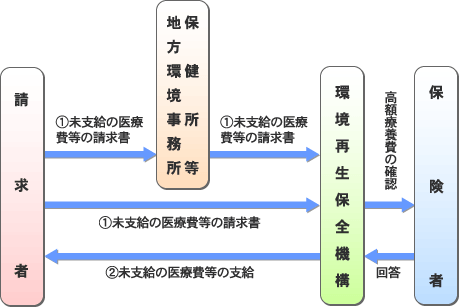
7)不服申立て
支給にかかる処分に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求することができます。
8)提出いただく書類:請求者と死亡した被認定者との関係についての書類
請求にあたっては、下記「添付書類」欄を参考にして、必要な書類を添えて提出してください。
| 項目 | 添付書類 |
|---|---|
| 未支給の医療費等の請求 (手続様式第14号) (PDF、192KB) (WORD、40KB) 手続様式第14号記載例(PDF、660KB) |
|
※1 未支給の医療費等を請求される方が、(1)の添付書類を葬祭料等他の請求書に添付されているときは省略できます。その旨を未支給の医療費等の請求書の余白にご記入ください。
※2 戸籍の謄本又は抄本で、請求者が請求権最優先順位者であるかどうかを確認します。配偶者の場合は婚姻関係を、請求順位が子以下の方の場合は、請求順位が上位である配偶者等の不在(死亡や離縁等)も確認しますので、そのことがわかる戸籍証明書をご提出ください。(請求できる順位は、こちらを参照)
※3 戸籍の謄本、抄本、住民票及び戸籍の附票は、役所から交付されたものをご提出ください。
※4 死亡した被認定者が医療費請求をしていなかった場合に、未支給の医療費等の請求者に提出していただくこととなります。
この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。
9)生計同一関係の証明書として考えられるもの(例)
| 配偶者 | 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 | |||
| 法律婚 | 事実婚 | |||
| 死亡した被認定者と死亡の当時同居していた場合 | 現在も死亡者と同一戸籍 | 死亡者の住民票除票と請求者の住民票、消除者(死亡者)を含む世帯全員の住民票、戸籍の附票。 これらを入手できない場合は、確定申告の控え(収受印のあるもの)、保険証の写しなど |
- | 死亡者の住民票除票と請求者の住民票、消除者(死亡者)を含む世帯全員の住民票、戸籍の附票。 これらを入手できない場合は、確定申告の控え(収受印のあるもの)、源泉徴収票(証明印のあるもの)、保険証の写しなど |
| 現在は死亡者と同一戸籍ではない | 死亡者の住民票除票と請求者の住民票、消除者(死亡者)を含む世帯全員の住民票、戸籍の附票。 これらを入手できない場合は、確定申告の控え(収受印のあるもの)、源泉徴収票(証明印のあるもの)、保険証の写しなど |
|||
| 死亡した被認定者の死亡の当時同居していなかった場合 | 確定申告の控え(収受印のあるもの)、源泉徴収票(証明印のあるもの)、保険証の写しなど | |||
※どれか1つの書類では、生計同一関係を証明できない場合、複数の書類を組み合わせる等してご提出していただくことがあります。戸籍の附票および住民票については、それに属する全員が消除された場合、市区町村における保存期間は、除籍・除票となってから5年間です。(住民基本台帳法施行令第34条第1項)戸籍の附票や住民票は、役所から交付されたものをご提出ください。(コピーは無効)
10)提出いただく資料
認定申請後に亡くなられ、死後認定された方、療養を開始した日※から亡くなられた日までに負担された保険医療費の自己負担分(注1)で死亡前に機構に請求していなかったものがある場合、未支給の医療費を請求できるご遺族が
「受診等証明書(手続様式第11号)(PDF、248KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() 記載例(病院用)(PDF、963KB)
記載例(病院用)(PDF、963KB)![]() 記載例(薬局用)(PDF、967KB)
記載例(薬局用)(PDF、967KB)![]() 」を病院・薬局等に記入していただき、
」を病院・薬局等に記入していただき、
「医療費請求書(手続様式第10号)(PDF、201KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() 記載例 (PDF、168KB)
記載例 (PDF、168KB)![]() 」とあわせて機構に提出してください。
」とあわせて機構に提出してください。
同時に「高額療養費の確認同意書(PDF、98KB)![]() (WORD、39KB)
(WORD、39KB)![]() 記載例 (PDF、952KB)
記載例 (PDF、952KB)![]() 」もご提出ください。
」もご提出ください。
(注1 健康保険法等で給付される額を除いた額、健康保険法でいうところの一部負担金、標準負担額)
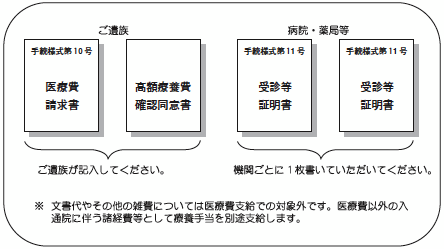
<注意事項>
- 請求できる期間は、療養を開始した日※から死亡日までの保険医療費の自己負担分となります。
- 認定疾病以外の医療、保険外の医療、民間療法は対象となりません。
- 差額ベッド代、文書代、自費検査料など保険給付対象外の費用も対象となりません。
※「療養を開始した日」とは
認定疾病について、初めて保険医療機関等において診察、薬剤の支給等健康保険法第63条第1項等に規定されている療養の給付(医療)を受けた日をいいます。認定を受けた方について療養を開始した日は、基本的には提出いただく医師の診断書に記載された当該医療機関における療養開始日となりますが、複数の医療機関にかかっている場合などには、医療費の償還払い請求の際に提出していただく「受診等証明書」及び「医療費請求書」に記載される療養開始日をもとに決定されます。
〈参考〉健康保険法
(療養の給付)
第63条 被認定者の疾病又は負傷に関しては、次にあげる療養の給付を行う。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
11)「未支給の医療費等の請求書」(手続様式第14号)
未支給の医療費等の請求書(手続様式第14号)記載例(PDF、660KB)![]()
救済給付調整金の請求
1)救済給付調整金とは
被認定者が、認定を受けた疾病に起因して死亡した場合で、被認定者に対して既に支給された医療費※療養手当及び未支給の医療費等の額の合計額が、280万円(特別遺族弔慰金の額)に満たない場合、その差額を被認定者のご遺族に支給する給付です。
なお、第三者による交通事故など、認定疾病に起因しない死亡の場合には、救済給付調整金は支給されません。
※医療費には、被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示することにより、医療機関から受けた療養について機構が医療機関に対して直接支払った額(現物給付額)を含みます。
2)救済給付調整金の請求
救済給付調整金を請求しようとするご遺族は、「救済給付調整金請求書」(手続様式第17号)(PDF、189KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() 記載例 (PDF、543KB)
記載例 (PDF、543KB)![]() に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。
に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えて機構へ提出してください。地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。
書類は正確に記入してください。また、必要な添付書類に不備がないようご留意ください。
3)救済給付調整金を請求できるご遺族の方
死亡した被認定者の配偶者・子・父母・孫・祖父母又は兄弟姉妹であって、被認定者の死亡当時、生計を同じくしていた方が請求を行うことができます。(配偶者には事実上婚姻関係と同様に事情のあった人を含みます。)
なお、生計を同じくしていた方の証明については、こちらをご参照ください。
4)請求の順位
請求の順位は下図の順序によります。また、先順位者が生存し、かつ生計を同じくしていた場合、後順位の方は請求できません。
なお、同順位者が2人以上の場合、同順位者の1人がした請求をもって全員が請求したこととなり、その請求者1人に対して行った支給は、全員に対して支給したこととなります。二重請求や分割支給はできません。
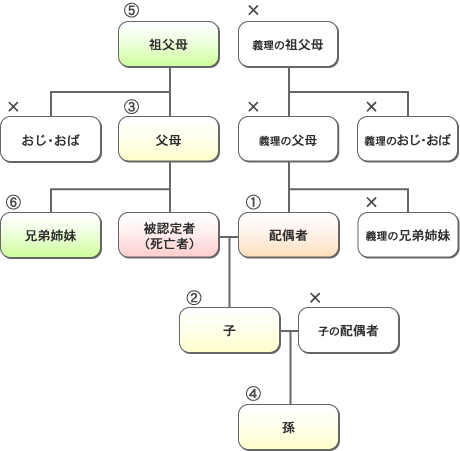
1~6の番号が請求順位です。
×のついている方は、請求権がありません。
5)請求に必要な書類
請求にあたっては、下記「添付書類」欄を参考にして、必要な書類を添えて提出してください。
| 項目 | 添付書類 |
|---|---|
| 救済給付調整金請求書 (手続様式第17号) (PDF、189KB) (WORD、33KB) 手続様式第17号記載例 (PDF、543 KB) |
|
※1 救済給付調整金を請求される方が、(1)の添付書類を葬祭料等他の請求書に添付されているときは省略できます。その旨を救済給付調整金請求書の余白にご記入ください。
※2 戸籍の謄本又は抄本で、請求者が請求権最優先順位者であるかどうかを確認します。配偶者の場合は婚姻関係を、請求順位が子以下の方の場合は、請求順位が上位である 配偶者等の不在(死亡や離縁等)も確認しますので、そのことがわかる戸籍証明書を ご提出ください。(請求できる順位は、こちらを参照)
※3 戸籍の謄本、抄本、住民票及び戸籍の附票は、役所から交付されたものをご提出ください。
※この他、必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。
6)救済給付調整金の決定及び支給
機構は、提出された「救済給付調整金請求書」(手続様式第17号)(PDF、189KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() 記載例 (PDF、543KB)
記載例 (PDF、543KB)![]() 及びその添付資料について、既に支給した医療費、療養手当の額等を確認、給付の可否を決定し、請求したご遺族に書面で通知します。支給決定された方については、給付決定額を請求者指定の口座に振り込みます。(なお、機構が医療機関に支払う医療費の額の確定は、医療を受けた月から2ヶ月後になりますので、救済給付調整金の審査はそれ以降になります。)
及びその添付資料について、既に支給した医療費、療養手当の額等を確認、給付の可否を決定し、請求したご遺族に書面で通知します。支給決定された方については、給付決定額を請求者指定の口座に振り込みます。(なお、機構が医療機関に支払う医療費の額の確定は、医療を受けた月から2ヶ月後になりますので、救済給付調整金の審査はそれ以降になります。)
7)請求できる期間
救済給付調整金を機構に対し請求できる期間は、被認定者が認定疾病に起因して死亡した日の翌日から2年以内です。
8)請求から支給までの流れ
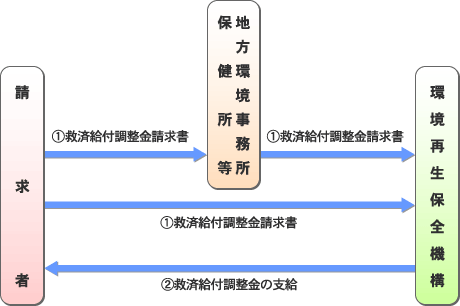
9)不服申立て
支給にかかる処分に不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求することができます。
未支給の医療費等及び救済給付調整金の支給例
1)認定後に亡くなられた方のご遺族の場合
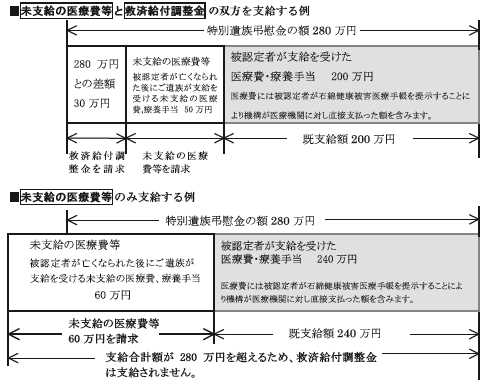
2)認定申請中に亡くなられ認定を受けることができる者であると決定されたご遺族の場合
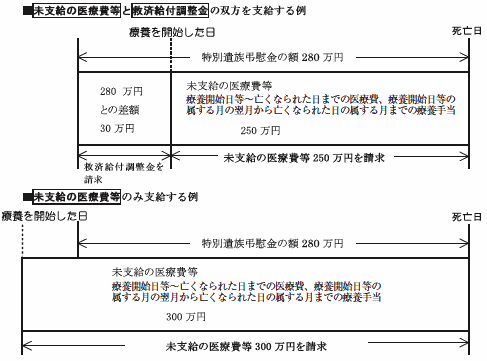






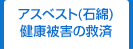

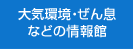




 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード
