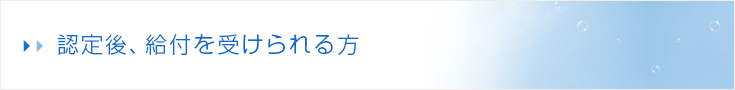
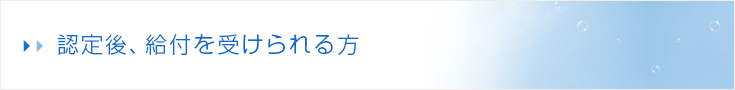
医療費の請求
医療費とは
機構により、指定疾病(中皮腫、肺がん)にかかった旨の認定を受けた方(被認定者)に対し、機構は医療費を支給します。支払われる医療費は、保険医療機関等※において受けた次に掲げる医療についてのものです。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
※「保険医療機関等」とは、健康保険法に規定する保険医療機関、保険薬局、介護老人保健施設、介護医療院などをいいます。
医療費は次のどちらかで支給されます。
- 現物支給
- 認定疾病(これに付随する疾病を含みます。)に係る医療を受ける時は、認定時に交付された石綿健康被害医療手帳(以下「医療手帳」といいます。)を保険医療機関等の窓口に提示することにより、窓口で自己負担分を支払わずに忘れずに認定疾病(これに付随する疾病を含みます。)に係る医療についての医療を受けることができます。被認定者の自己負担分の医療費は機構から保険医療機関等に支払われます。
- 償還払い
- 医療手帳が提示できない以下のア及びイのケースについては、いったん医療費をご自身で支払っていただき、後日機構に対して自己負担分をご請求いただいて支給することになります。
- ア 被認定者が、緊急その他やむを得ない理由により保険医療機関等以外の医療機関等で医療を受けた場合。
- イ 医療手帳の交付を受ける前に認定疾病についての医療を受けた場合など、被認定者が医療手帳を保険医療機関等に提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認められる場合。
療養開始日、基準日
「療養を開始した日」とは認定疾病について健康保険法第63条第1項等の療養を開始した日を言い、初めて保険医療機関等において健康保険法適用となる医療を受けた日です。ただし、その日が認定の申請のあった日の3年より前の日であった場合は、認定の申請のあった3年前の日(以下、「基準日」といいます。)とします。基準日以降の医療費について機構がお支払します。
以下、ケースに分けて説明します。
<参考>健康保険法
(療養の給付)
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
ア.療養開始日が基準日となるケース(認定の申請のあった日から3年以内の例)
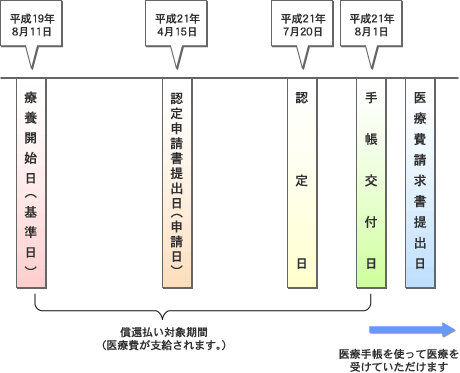
療養開始日(平成19年8月11日)から手帳交付日の前日(平成21年7月31日)までが医療費の支給される償還払いの対象期間です。手帳交付日(平成21年8月1日)以降は保険証と一緒に医療手帳を医療機関の窓口に提示することによって、医療機関の窓口で自己負担分を支払わずに認定疾病に係る保険医療を受けることができます。
イ.療養開始日が認定の申請のあった日から3年前の日よりも前の例
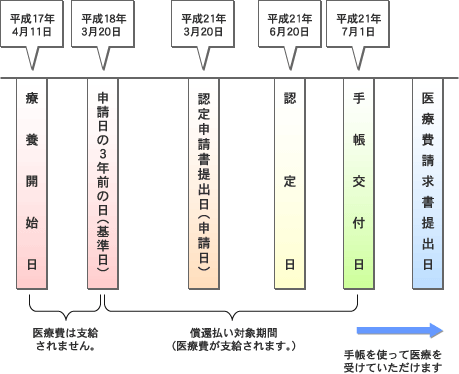
療養開始日が認定の申請日の3年前の日よりも前の場合は、基準日(平成18年3月20日)から手帳交付日の前日(平成21年6月30日)までが、医療費の支給される償還払いの対象期間になります。基準日以前の医療費は支払われません。手帳交付日(平成21年7月1日)以降は保険証と一緒に医療手帳を医療機関の窓口に提示することによって、医療機関の窓口で自己負担分を支払わずに認定疾病に係る医療を受けることができます。
医療費の請求
被認定者は償還払いの医療費について、機構に請求することができます。医療費を請求しようとする方は、医療費請求書(PDF、201KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() (手続様式第10号)に必要事項を記入し、受診等証明書(PDF、208KB)
(手続様式第10号)に必要事項を記入し、受診等証明書(PDF、208KB)![]() (WORD、33KB)
(WORD、33KB)![]() (手続様式第11号)などの必要な添付書類を添えて機構又は地方環境事務所、保健所等に提出してください(郵送可)。記載方法はこちらを参照してください。
(手続様式第11号)などの必要な添付書類を添えて機構又は地方環境事務所、保健所等に提出してください(郵送可)。記載方法はこちらを参照してください。
書類は正確に記載し、添付書類の漏れがないようにお願いします。特に、「4(○に4)認定疾病に係る療養を開始した日」欄には、受診等証明書(手続様式第11号)が複数枚ある場合はその最も古い療養開始日をご記入ください。
療養開始日は受診等証明書(手続様式第11号)及び認定申請の際に提出された判定様式第1号・第2号により機構で確認します。
注意
請求できる医療費は、保険診療分の医療費で保険医療機関等に支払った自己負担分に限られます。自己負担したものであっても室料差額(差額ベッド代)、診断書料、自費検査料、通院時タクシー代等の保険給付対象外の費用は請求することができません。
遺伝性疾病、歯科診療、正常分娩に係る産科診療、第三者行為による障害等の、認定疾病以外の医療にかかった費用は支給の対象にはなりません。
同一月内の同一医療機関ごとの自己負担分(医科入院・外来別に計算し、さらに診療科ごとに計算した自己負担分)が自己負担限度額(一般の場合は月額:80,100 円+(医療費総額-267,000 円)×1%)を超えているときは、この自己負担限度額を超えている部分については、加入している健康保険から高額療養費として支給されます。機構からの給付は自己負担限度額までになりますのでご注意下さい。(高額療養費の支給については、保険者(健康保険組合等)への手続きが必要になります。各保険者にお問い合わせ下さい。)。
医療費の給付対象となる金額 =自己が支払った金額-健康保険等対象外の費用-高額療養費として支給される金額
請求書及び請求にあたって必要な書類
医療費の請求に必要な書類は以下の通りです。
| 項目 | 様式 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 医療費請求書 (PDF、201KB) (WORD、33KB) |
手続様式 第10号 |
|
※1 受診等証明書は機構の指定様式です(手続様式第11 号)。こちらは医療機関に記入していただいてください。なお、複数の医療機関で認定の疾病に係る療養をされたり、複数の薬局で薬剤を購入された場合は、その機関ごとの受診等証明書の提出が必要となります。(医療機関により文書作成料がかかる場合がありますが、この費用は医療費請求の対象外です。)
この他に必要に応じて書類の追加提出をお願いする場合があります。
※2 移送費とは、患者を診察した医師がその医療上転院、転地が必要であると認めた場合において、入院、転院、転地療養をするための移送について、普通の交通手段では不可能であり、客観的に見てその妥当性が認められる場合に寝台自動車等を用いたときに要した費用のことです。タクシー代等は含まれません。
※3 高額療養費の有無及び支給額を機構から保険者に照会させていただいたうえで給付額を決定します。高額療養費の有無にかかわらずご記入・ご提出ください。
医療費の決定及び支給
提出された「医療費請求書」及び「受診等証明書」の内容を審査したうえで給付決定額を請求者の指定した預貯金口座に振り込みます(事前に支給決定通知書を機構からお送りします。)。 なお、医療費の額は、高額療養費の有無及び支給額を確認した後に決定されます。
請求できる期間
医療費を機構に対して請求できる期間は、対象となる医療費の支払いを行った日の翌日から2年以内です。ただし、基準日から申請日の前日までの間の医療費については、申請日から2年以内です。
請求から支給までの流れ
(現物給付)
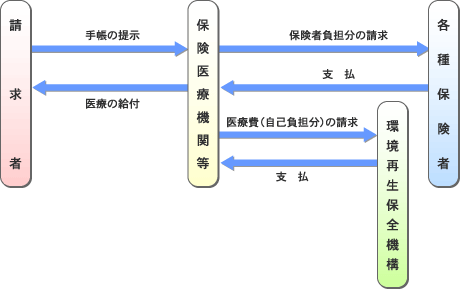
(償還払い)
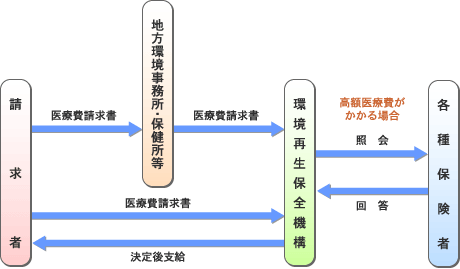






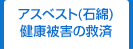

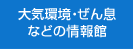




 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード
