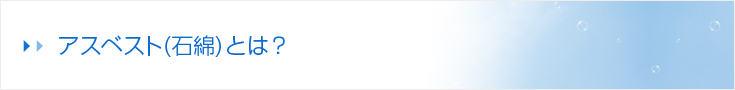
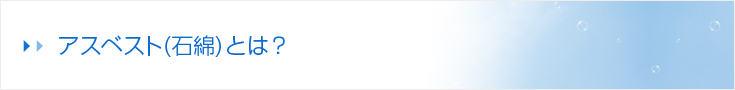
石綿(アスベスト)ばく露の医学的所見
石綿関連疾患の診断で重要な点は、石綿ばく露歴を確認することです。そのため、病気の既往歴や喫煙歴のほかに、学生時代のアルバイトも含めて従事した職業・職種を具体的に年代順に聴き取ること、幼少・子供時代の居住地などの生活環境も聴き取ることが重要です。また、父母や配偶者の石綿ばく露作業歴を聴き取ることも大切です。
しかしながら、石綿関連疾患は発症までの潜伏期間が長いことから、石綿ばく露歴が明らかでない場合もでてきます。そのため、胸膜プラークと石綿小体(アスベスト小体)が、医学的に客観的な石綿ばく露の所見として非常に重要です。
1. 胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)
石綿を吸入することによって壁側胸膜に生じた限局的な線維性の肥厚を、石綿健康被害救済制度及び労災保険制度では「胸膜プラーク」と呼んでいます。通常は、びまん性胸膜肥厚と異なり、臓側胸膜との癒着はありません。
- 石綿ばく露との関連
- 通常、ばく露開始から概ね15~ 30年以上を経て、画像上認められるようになります。職業性ばく露だけでなく、家庭内ばく露や石綿鉱山、工場の近隣ばく露のような低濃度ばく露でも認められます。胸膜プラークは過去に石綿のばく露があったことを示す重要な医学的所見です。最近の研究から、胸部正面エックス線画像により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの、または胸部CT 画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一側の胸部CT 画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上のものについては、肺がん発症の危険が2倍以上となる累積石綿ばく露量があったと推定される結果が得られています。
- 診断
- 胸膜プラークの診断には、胸部CT画像が有用です。胸膜プラークは、概ね両側の壁側胸膜や横隔胸膜に非対称性にみられます。傍脊椎領域に見られる脂肪や肋間静脈による肥厚像は胸膜プラークと似た像を呈するので、注意が必要です。胸腔鏡検査時に肉眼で光沢を帯びた白色の肥厚斑として観察することもできます。胸膜プラークは石綿肺とは異なります。
- 経過
- 時間の経過とともに徐々に厚くなり石灰化しますが、胸膜プラークだけでは治療を要するほどの著しい呼吸機能障害は起こりません。
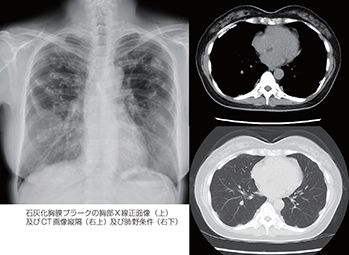

2. 石綿小体(アスベスト小体)
石綿小体とは、肺内に長期間滞留した石綿繊維の一部がフェリチンなどの鉄たんぱく質で覆われたものをいい、過去の石綿ばく露を推定する重要な指標となるものです。通常直径は2~ 5μmで鉄アレイ様など特徴的な形をしています。大量の石綿繊維を吸入した場合には、繊維の種類に関わりなく石綿小体が肺内に大量に見つかります。
ヒトの生体試料を用いた石綿ばく露量の評価には、手術や剖検時に得られた肺組織について、位相差光学顕微鏡を用いて石綿小体を計数する方法(労災病院のアスベスト疾患ブロックセンター(参照)で実施可能です)があり、乾燥肺重量1g当たりの本数で表します。職業性石綿ばく露の場合、2種類以上の石綿のばく露を受けていることが多いと言われています。比較的大量の短いクリソタイル(白石綿)だけのばく露を受けていると考えられるものの、石綿小体が一定量認められない場合には、石綿繊維そのものを電子顕微鏡で調べる専門的な分析が必要になる場合があります。また肺組織を得ることができない場合には、気管支肺胞洗浄液(BALF)中の石綿小体を検出する方法もあります。※1
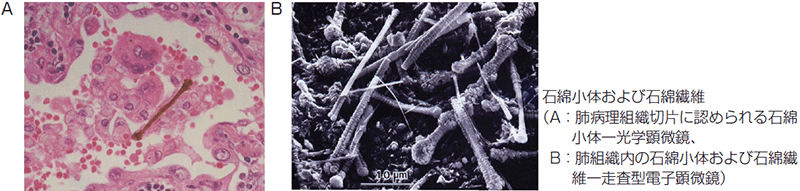
肺がんの発症のリスクが2倍以上になる累積石綿ばく露量に相当する石綿小体等の医学的指標は以下の通りです。
累積石綿ばく露量の25繊維/ml×年に相当する医学的指標
- ① 乾燥肺重量1g 当たりの石綿小体5,000 本以上
- ② 乾燥肺重量1g 当たりの石綿繊維200 万本以上(繊維長が5 μm超)
- ③ 乾燥肺重量1g 当たりの石綿繊維500 万本以上(繊維長が1 μm超)
- ④ 気管支肺胞洗浄液(BALF)1ml当たりの石綿小体が5 本以上
- ⑤ 複数の肺組織切片中の石綿小体※2
※1 気管支肺胞洗浄:気管支鏡を気管支に挿入して生理食塩水を注入し、回収した洗浄液の細胞成分や液性成分を分析し呼吸器疾患を診断する方法。
※2「肺組織切片中の石綿小体」の所見とは、肺組織の薄切り試料の中に石綿小体が光学顕微鏡で確認された場合をいい、複数の肺組織薄切標本において1標本当たり概ね1本以上の石綿小体が認められる必要があります。






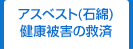

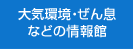




 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード
