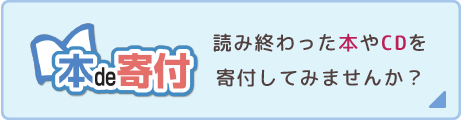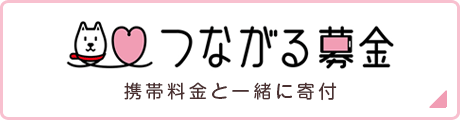協力・協働による地域づくり研修

研修概要
社会や地域の抱える課題が多様化・複雑化する中で、NPO・NGO、地域住民、企業および行政など、ステークホルダー間の協力が課題の解決には不可欠であり、個々の組織マネジメントと合わせ、地域マネジメントが必要となっています。
本研修では、環境保全活動に係る地域づくりと地域課題解決のステークホルダー(地球環境基金の助成先団体を含むNPO・NGOのほか、地域住民、行政担当者、企業担当者など)を広く対象とし、参加者が協働を生み出す方法に理解を深め、協力・協働を進めていくために必要となる視点を獲得できるよう、ステークホルダー間の協力関係を広げるヒント・きっかけの提供を目的とした全2回の「協力・協働による地域づくり研修」を実施します。
研修日程
| 日程・開催方法 | 研修テーマ | 講師 | 定員 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 |
日時: 2023年3月10日(金) 14:00~16:00 開催方法:オンライン(WebEx) |
多様なステークホルダーと協働していく方法 | 松原 明氏 池本 桂子氏 |
先着 50名 |
| 第2回 |
日時: 2023年3月17日(金) 14:00~16:00 開催方法:オンライン(WebEx) |
これからの地域づくりや地域課題の解決を担うNGO/NPOのあり方(目指すべき姿) | 久保 尭之氏 | 先着 50名 |
講師紹介
〈第1回〉
松原 明 氏
「協力世界」代表
1994年NPO法立法を推進するシーズ・市民活動を支える制度をつくる会を創設。事務局長、代表理事を務める。NPO法、認定NPO法人制度、NPO法人会計基準、NPO法改正などNPO支援制度の創設を推進し、NPO支援財団研究会、NPO法人会計基準協議会、日本ファンドレイジング協会、東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN)などの創設も推進。
現在、「協力世界」を主宰し、NPOや地域づくり等で人々が協力を築くための技術を、誰でも学べるように「協力のテクノロジー」として体系化を進めている。著書に『NPO法人ハンドブック』1998年、共著に『協力のテクノロジー』2022年、『NPO法コンメンタール』1998年、『NPOはやわかりQ&A』など

池本 桂子 氏
新卒で公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会に入職。会員対応やイベント運営を3年間経験後フリーランスに。
複数の環境NPOで、会計・総務・会員寄付者対応・人事・労務などバックオフィス業務に従事した。並行して、認定NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会の会員としても活動。2010年にフルタイム職員となり、NPO法やその税制など、各種の政策提言活動に従事。2019年に代表理事を務めて2020年に退職。現在は再びNPO支援のフリーランスに。市民活動の力の源「参加と協力」の普及・推進に努めている。

〈第2回〉
久保 尭之 氏
一般社団法人みなみあそ観光局(地域DMO)/戦略統括マネジャー
1991年鹿児島県生まれ。東京大学工学部卒。大手重工メーカーのエンジニアや一般社団法人東の食の会での2011年東日本大震災後の東北一次産業の復興支援を経て、2016年熊本地震を機に阿蘇へ。南阿蘇エリアの観光地域づくりを担う一般社団法人みなみあそ観光局にて現職。その他、専門学校イデアITカレッジ阿蘇のディレクター/講師や阿蘇のローカルビジネス(空き家の不動産、アクテビティ、飲食など)の立ち上げなどを通して、ビジネス/マーケティングの力を生かした持続可能な地域づくりに多角的に取り組む。

申し込み先
独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部
kikin_kensyu★erca.go.jp(★を@に変換してください)
まで下記の内容を記載の上お申し込みをお願いいたします。
〈申し込み記載内容〉
①氏名
②所属
③年代(例:30代)
④参加を希望する回(全2回ですが、どちらか1回だけの参加も可能です。)
※件名を「地域づくり研修申込_氏名」としてください
※郵送でのお申し込みはできません
※複数人での参加希望の場合もお一人ずつお申し込みをお願いいたします。
申し込み締切
第1回:2023年3月 3日(金)16時(厳守)
第2回:2023年3月 10日(金)16時(厳守)
お問い合わせ
独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金部
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー8階
電話:044-520-9505
メール:kikin_kensyu★erca.go.jp (★を@に変換してください)
 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロードPDF形式のファイルはadobe readerが必要です。