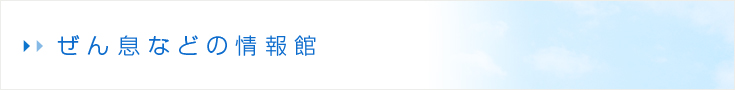
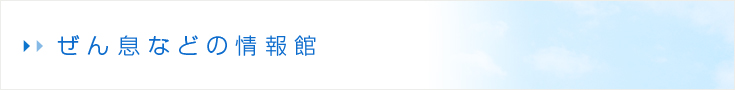
2-3 慢性気管支炎、気管支ぜん息等の発症・増悪因子の検索に関する研究
代表者:秋山 一男(国立相模原病院部長)
研究の目的
成人慢性閉塞性肺疾患は社会的に重要な地位を占める中高年世代に罹患患者数が多い疾患である。
気管支喘息有病率は我が国成人人口の約3%を占め、現在約300万人の患者数が推定される。
また慢性気管支炎、肺気腫とも社会の高齢化とともに増加傾向が明らかであり、慢性呼吸不全により在宅酸素療法を必要とする患者の中では最も頻度の高い基礎疾患である。
これら成人慢性閉塞性肺疾患罹患患者のQOLの障害、低下による社会・経済的損失は莫大なものがある。
成人気管支喘息ではその60-80%を成人発症喘息が占めることが明らかになっているが、その発症機序に関しては、未だ不明の点が多い。
気管支喘息の発症要因の一つと考えられる気道過敏性については、小児発症喘息において重要と考えられる先天的気道過敏性に対して、成人発症喘息においては、後天的気道過敏性の関与が大きいと考えられる。
そこで研究内容1においては、成人発症喘息における気道過敏性の獲得機序の解明を共通の目的として掲げ、各班員施設が、臨床的、基礎的視点からの研究を多角的に実施し、班員相互の情報交換、討論を繰り返すことにより各々の個別研究を有機的に統合することで、最終目的である“気道過敏性”の獲得機序の解明を試みた
後天性気道過敏性獲得機序が明らかになれば、喘息の発症予防へとつながり成人喘息患者の減少が期待される。また大気汚染や喫煙が重大な外因として知られている慢性気管支炎、肺気腫であるが、肺癌発症の危険因子としての役割を含め、この両者を鑑別して病因、病態を解明することはこれら疾患の予防対策を考える上で極めて重要である。
このような視点から、研究内容2においては、共同研究として疾患の病型構成の過去10年間の変遷と最近の実態を明らかにすることを目的と掲げ、また個別研究では、慢性閉塞性肺疾患、特に早期肺気腫患者の発症機序を明らかにすること、慢性閉塞性肺疾患の気道炎症の特徴とそのマーカーの意義を明らかにすること、慢性閉塞性肺疾患と肺癌の合併に関して、閉塞性障害が喫煙とは独立した肺癌の危険因子となり得るか否かを検討し、さらに肺癌の早期発見のために車載型HRCTによる検診の有用性を検討した。
これら成人慢性閉塞性肺疾患の発症・増悪予防へとつながる発症、増悪因子の検索は高齢社会を迎えた我が国において重要な研究課題である。
3年間の研究成果
本研究班では成人慢性閉塞性肺疾患の発症、増悪に関わる因子を研究内容1では気管支喘息を対象疾患として、研究内容2では慢性気管支炎、肺気腫を対象疾患として研究を進めた。
研究内容1
気管支喘息の発症に関わる最も重要な因子としての”気道過敏性”の獲得機序の解明を共通の研究目標に掲げて3年間の研究を実施した。
結果として、疫学調査、臨床試験、ヒト検体を用いたin vitro実験、動物モデルを用いたin vivoあるいはin vitro実験等、臨床的研究から基礎的研究にわたる多角的な研究を続けてきた。
気道過敏性の獲得機序について3年間での本研究で明らかになった点としては、
- a. 気道上皮が大気汚染物質やウィルス感染による刺激により積極的に炎症性サイトカインを産生分泌して気道炎症に能動的に関わり、気道過敏性亢進をきたす
- b. 脂質メディエーター合成酵素遺伝子多型が気管支喘息発症に関わる喘息遺伝子としての役割を有する可能性がある
- c. 無症候性気道過敏性亢進の背景因子としては、アトピー素因が関連している可能性がある
- d. 喘息の必要条件である気道過敏性は各収縮物質に特異的な過敏性が存在し、患者毎のheterogeneityが大きい
- e. 内因型喘息の病態に常在微生物に対する免疫学的機序が関与している可能性がある
等の新しい知見が得られた。
研究内容2
慢性気管支炎、肺気腫の発症、増悪因子の検索に関する研究においては、共同研究においては、慢性閉塞性肺疾患患者の過去10年間の変遷と最近の患者内訳・治療薬の特徴を、アンケート調査により診断名と病像の両面から明らかにした。その結果、肺気腫型が圧倒的に多いことが確かめられた。
個別研究においては 、
- a. 早期肺気腫の病変形成における発症機序の一端を明らかにした慢性閉塞性肺疾患の気道炎症に関してその特徴とマーカーについて新知見を得た
- b. 慢性閉塞性肺疾患に合併する肺癌が、単なる合併ではなく、慢性気道閉塞を起こす因子と共通する因子を背景に合併している可能性を指摘した
- c. 背景基礎疾患がある患者に合併する肺癌の早期診断に車載型肺CT検診が有用であることを示し、その改良を行った
これまでの研究により、慢性気管支炎、気管支喘息等の成人慢性閉塞性肺疾患の発症・増悪予防へとつながる発症、増悪因子の一部が解明されたと思われるが、今後さらに新しい知見を蓄積することにより、日常臨床に還元し得る成果を期待したい。

















