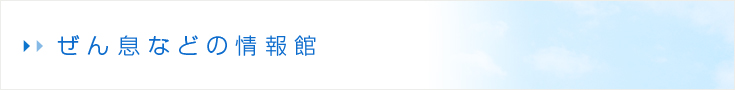
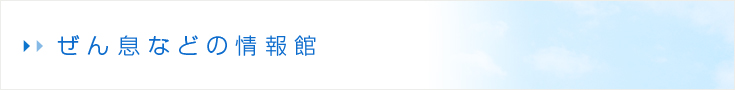
2-1 同一地域、同一手法による小児気管支ぜん息等の動向把握と比較検討に関する研究
代表者:西間 三馨
研究の目的
気管支喘息の経年的疫学調査においては、同一地域で、かつ、確立された調査手法で行われることが理想的である。 我々は1982年に西日本11県の小学児童5万5千人を対象にATS-DLD日本版・改訂版による疫学調査を行い、次の結果を得た(アレルギー、32:1063,1983)。
- 喘息罹患率は男:3.83%、女:2.49%、全体:3.17%で学年が上がるにつれ減少し、小学6年生は1年生の3/4であった。
- 都市部が非都市部に比して1.5倍多かった。
- 喫煙、暖房との関係は認められなかった。
- 二親等内にmajor allergyの家族歴のある群の喘息罹患率は、ない群に比して2.4倍、気管支喘息の家族歴のある群のそれは3.8倍であった。
その後1992年にも同様の調査を行い、1.4倍の増加を認めた(アレルギー42:192,1993.日小ア誌、7:59,1993)。
今回20年後における同一地域、同一手法によって変動の実態とその要因を喘息以外のアレルギー疾患も含めて調査検討することは、この頻度の極めて高い疾患群を診断治療し、対策を行う上で重要である。また、国際的比較をするために全世界と同時期に同一手法で行うISAAC(International Study of Asthma and Allergies in Childhood)第3相調査への1995年に引き続く参画、ならびにATS-DLD方式とISAAC方式の比較検討は極めて重要である。
13年度研究の対象及び方法
小課題1
1982年、1992年と同一の小学校80校を対象とし、ATS-DLD日本版・改訂版を使用し、同一項目で比較検討する。
- 各対象校ごとに調査用紙、説明書等の修正をし、調査手法を確定する。
- 2学期~3学期にかけて調査用紙の配布、及び回収を行う。検査予定地域は対象者のアンケート結果に基づき選定し、血液検査、肺機能検査を実施する。
- 2001年2月までに有症率を中心としたデータ解析をし、各調査校へ結果報告する。
小課題2
問診票の比較検討方法にはいくつかあるが、ほぼ同一と考えられる集団での異なる時期での比較、同じ手段での同一時期での比較、同一対象での経年的比較、2つの問診票の別々の比較、同時の比較などである。 一昨年度はATS-DLD版、昨年度はISAAC版で行ってきた調査対象と同一の対象に対して、今年度はISAACの問診票の診断のための問診項目を従来のATS-DLDの問診票の診断の個所に入れ替えた問診票を作成し、同一の季節に実施した。 この方法で得られた結果を過去2年間の結果と比較した。
13年度研究成果
西日本11県での疫学調査結果(粗集計)
- 回収状況:配布数37,779、回収数36,228、回収率95.89%であった。
- 有症率:有症率は気管支喘息(BA):6.14%、喘息寛解(RBA):2.81%、喘鳴(W):5.30%、持続性咳嗽(PC):0.59%、持続性痰(PS):0.33%、アトピー性皮膚炎(AD):13.81%、同寛解(RAD):13.19%、アレルギー性鼻炎(AR):20.45%、同寛解(RAR):4.85%、アレルギー性結膜炎(AC):9.77%、同寛解(RAC):6.05%、スギ花粉症(P):5.73%、同疑(PP):6.61%であった。
- BA の学年別の疾患の有症率をみると減少傾向は全くなかった。性別では、男:7.59%、女:4.66%であった。アレルギーの家族歴と既往歴、気道感染の既往歴の有無で大きな差があり、地域差は減少していた。全体、小学校1年生、小学校6年生の喘息初発年齢をみると、近年の低年齢発症化を支持するデータであった。
福岡市での検討
小学校1年生についての有症率の比較:1999年度、2000年度、2001年度のATS-DLD、ISAAC、ATS-DLD版を用いて実施した結果は、喘息の有症率の比率は8.28%:17.8%:7.02%であり、喘鳴の有症率の比率は6.9%:13.6%:6.8%であり、いずれも約1:2:1であった。
また、同一患児の診断名がATS-DLDとISAACの2つの問診票でどのように変わるかをみるためにこの2年間での診断名の変化をみたが、自然の軽快傾向も存在するためか、両問診票の比較を行うのは同一症例で年度を越えた比較検討をしても難しいと考えられた。

















