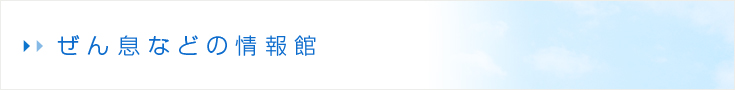
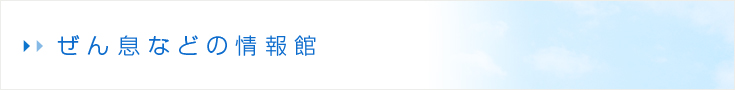
3-3 高齢者の気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫の保健指導等に関する研究
代表者:木田 厚瑞
研究の目的
気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫は高齢者に多い疾患である。罹患することにより気管支ぜん息では頻発する発作があり、慢性気管支炎、肺気腫では慢性の呼吸不全により、患者の日常生活は大幅に制限されることになる。また、急性の発作や病態の増悪により生命の危険にさらされることも稀ではなく、これらはいずれも高齢化とともに高い死亡率を示している。さらに高齢者では肺がんを含め、全身的な合併症あるいは睡眠呼吸障害など問題点は多岐にわたっている。こうした問題を解決し患者の健康回復を図るためには、患者を取りまく環境も含めた総合的な検討を実施することが必要である。
本研究では、高齢者の気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫の適切な管理方法のあり方とその環境づくりについて検討し、健康回復及び日常生活の向上に資することを目的とした。
13年度研究の対象及び方法
中課題の下に計8項目の小課題研究を推進した。
- 高齢者剖検例における肺気腫の重症度と呼吸器症状の関連性に関する研究
- 高齢者COPDにおけるQOL評価の方法に関する研究
- 気管支拡張症を伴う肺気腫症例に関する研究
- COPDにおけるGOLDの重症度分類に関する研究
- GOLDガイドラインにより管理されたCOPD患者のoutcomeに関する研究
- COPDにおける気道閉塞可逆性試験の意義に関する研究
- COPDにおける労作時呼吸困難、下肢の疲労に関する研究
- 高齢者の慢性呼吸器疾患に対するTelehealthの応用:実態調査と問題点について
13年度研究成果
1.高齢者の剖検肺からみた肺気腫について
中等度以上の肺気腫において、はじめて労作時呼吸困難、咳、痰などの呼吸器症状が著明となることが判明した。男性では肺気腫の重症化とともに、やせが著明となるが、女性では必ずしも一致しない。喫煙歴のある男性における体重減少は肺気腫の存在を強く示唆することが判明した。
2.COPDにおける気管支拡張病変の合併について
HRCTによる検討ではCOPDの約30%に気管支拡張病変の合併を認め、さらに、肺気腫の程度が強い群に気管支拡張変化が強い傾向にあった。
3.肺気腫の診断について
GOLD(2001)では、もはや肺気腫、慢性気管支炎という分類をしておらず、従来の分類との間に齟齬を生ずる結果となった。慢性気管支炎と肺気腫のpathogenesisが同じであるかどうかについては議論が多いが、病変の主座が肺胞壁を中心とするか、末梢気道を中心とするかについての明らかな差は認められる。肺気腫という診断名は今後、不要としたほうがいいのかどうかについても検討を進める必要がある。
4.COPDのoutcomeについて
肺機能のほか、6分間歩行テスト、QOL評価、外来受診回数、入院回数と期間がoutcomeを評価するパラメータとして適切であることが判明した。またQOL評価では筆者らが開発したVAS-8 QOL Scaleが従来のスタンダードとされているSGRQとの相関性が高いことを明らかにした。QOLは下肢の疲労感とも関連する。
5.気道閉塞の可逆性について
FEV1.0とFVCの各々の改善率をみることが、病態を簡便に判定する意味で適切であることを明らかにした。
6.在宅呼吸ケアにおけるITの利用
使いやすい機器の開発、それらを使うための教育、指導にそれぞれ問題があることを明らかにした。いずれも限界性はあるが、将来の新しい方向として今後の研究が必要である。

















