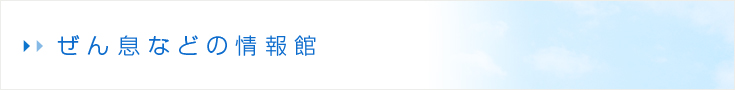
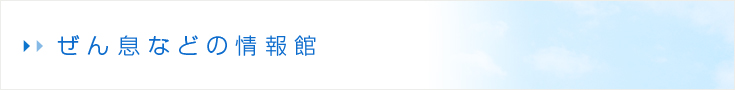
1-1 気管支ぜん息の発症リスク低減に関わる因子の検索と管理・指導への応用に関する調査研究
代表者:滝澤 始
研究の概要・目的
私たちは、実際の大気環境中でありうる低い濃度で、かつ長期間継続的にデイーゼル排気(Diesel Exhaust, DE)に曝露するマウスの系を確立し、ぜん息モデル動物における急性期の増悪影響、慢性期での気道リモデリングへの影響、さらに発症への影響について報告してきた。異なる2つのマウス系の短期暴露の比較検討から、その感受性要因として、 抗オキシダント酵素、特にheme oxidase (HO)-1とその発現調節因子Nrf-2 を見出した。
本調査研究では、以上の研究成果をふまえ、
- 実験モデルにおけるぜん息発症・増悪にかかわる感受性遺伝子を同定
- これらを危険因子 としてスクリーニングするために適切なバイオマーカーの開発
- 感受性マウスに抗オキシダント物質を予防的に投与することにより、DEによる被害リスクが低減できるか否かを検証する。
年度ごとの研究目標(計画)
平成18年度
感受性の異なる2系統マウスで、低濃度かつ長期間継続的にディーゼル排気粒子(Diesel Exhaust Particles, DEP)の曝露によるマウス気道炎症反応の系統差(DEP単独の作用):前年度までの成果を踏まえ、幼弱マウスに6ヶ月間の長期暴露を行い、その影響を詳細に検討し、喘息様病態への影響を確立する。前年度より詳細にサイトカイン、抗酸化酵素群の検討を行い、感受性の差に関連する遺伝子群を絞り込む。
平成19年度
- 感受性の異なる2系統マウスで、低濃度かつ長期間継続的にデイーゼル排気粒子(Diesel Exhaust Particles, DEP)の曝露によるマウス喘息モデルでの気道炎症反応の系統差を、幼弱マウスに6ヶ月間の長期暴露を行い詳細に検討する。
- 抗酸化酵素の重要な転写因子であるNrf2ノックアウトマウスにおける低濃度DEP曝露の気道炎症反応への影響について検討する。
平成20年度
DE暴露によって引き起こされる気道炎症病態における酸化ストレスの役割を一層明らかにするために、以下の検討を行う。
- 抗酸化酵素の重要な転写因子であるNrf2ノックアウトマウスにアレルギー性喘息モデルを作成し、低濃度DEP曝露の気道炎症反応への影響について検討する。
- さらに、昨年度の研究でヒトにおいて、安全かついくつかのバイオマーカーの測定が可能であった、呼気濃縮液採取と測定の基礎的検討を、健常者とともに気管支喘息患者においても行う。
3年間の研究成果
平成18年度
低濃度・長期(6ヶ月)DEP単独曝露により、 BALB/cマウスでは、マクロファージの遊走因子であるMCP-1が有意に上昇するとともに、DEPを貪食した肺胞マクロファージが認められたが炎症病巣は見られなかった。抗酸化ストレス酵素のGST-M1の発現が増強しており、DEPの酸化ストレスに対する抗酸化防御反応が有効に作用している可能性が示唆された。一方、C57BL/6マウスでは、2ヶ月をピークとする一過性の気道過敏性亢進があり、リンパ球の浸潤を伴う明らかな気道周囲の炎症病巣が見られた。抗酸化酵素の発現増強が見られない中で、BALF中IL-12の産生が有意に上昇しており、リンパ球を動員した炎症反応により局所の防御を行っていると推定された。さらに19年度予定のアレルゲン誘発喘息モデルでのDEP影響、およびC57BL/6マウスでの化学予防についても検討しえた。
平成19年度
低濃度・長期(6ヶ月)DEP単独曝露により、肺局所のGST-M1タンパクの発現をウェスタンブロット法で定量し、そのBALB/cマウスでの増加、C57BL/6マウスでの抑制を確認した。酸化ストレスの指標とされる8-OHdGの増加がBALB/cではDE暴露によっても認められないこと、C57BL/6マウスでの増加が確認された。BALB/cマウスでの明らかなアレルギー性気道炎症病態の増悪が認められたが、これはDEPのアジュバントとしての作用ではなく、DEPによる酸化ストレスがOVAによるアレルギー性気道炎症病態をさらに増悪させたと考えられた。Nrf2-/-マウスでは Nrf2+/+マウスと比較し、気道過敏性の明らかな増強と肺組織像でのPAS陽性粘液細胞の増生が見られ、Nrf2が重要な役割を演じていることが明らかにされた。
平成20年度
今年度の調査研究では、以下の3点が明らかとなった。
- DE(DEP)への感受性は宿主によって異なり均一ではない。即ち健康影響の感受性遺伝子が存在する。
- DE(DEP)暴露影響は参加ストレスに依存し、それはNrf2遺伝子に関連する。
- DE(DEP)感受性宿主のスクリーニングのための適切なバイオマーカーの開発は効率的かつ適切な健康被害予防に重要であることが明らかとなった。
評価結果
平成18年度
2種のマウスを用いた実験であり、DEPがヒトへどのような影響があるのか、個人差はどうなのかを明らかにし、DEP暴露によるマクロファージ数の変化を人間にも応用できることを証明するなど、臨床にも応用できるための研究を期待する意見があった。
平成19年度
酸化ストレスと抗酸化防禦のメカニズムがかなり明確になったことは大きな成果である。今後、酸化ストレスが喘息発症にどの程度、直接的関与をもつのかを明らかにすること、呼気濃縮液中の酸化ストレスマーカーの探求などを期待すると共に、将来は人への臨床応用へと発展することを望む意見があった。
平成20年度
動物実験での成果をもとにヒトに於いてもDEによる喘息への影響が酸化ストレスによって引き起こされることを明らかにし、呼気濃縮液を用いて実証した成果は大きく評価できる。今後は、EBCの検討をもう少し症例を増やして、実際に使用できる段階まで進展させることが望まれるとの意見があった。
1-1 気管支ぜん息の発症リスク低減に関わる因子の検索と管理・指導への応用に関する調査研究

















