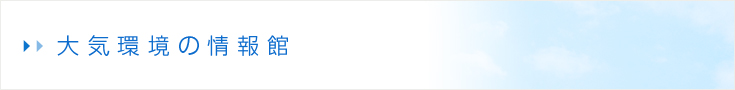
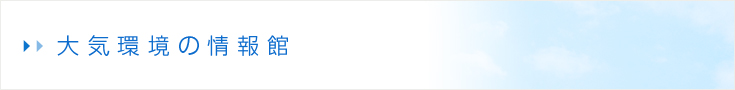
環境問題の歴史
| 西暦(和暦) | 環境関連の出来事 | その他の出来事 | 時代概要 |
|---|---|---|---|
| 1891(明治24年) | 足尾銅山鉱毒問題の国会提起 | 明治時代~1964年 近代化と共に始まった大気汚染" 明治時代の近代化政策とともに始まった大気汚染の歴史。第二次世界大戦後の工業復興でも大気汚染問題が引き起こされ、各地で公害防止条例が制定されていきます。さらに1955年からの好景気下では、工業都市の住民に深刻な健康被害が起こり、大気汚染は大きな社会問題へ発展します。 |
|
| 1903(明治36年) | 浅野セメント粉じん被害(東京・深川) | ||
| 1911(明治44年) | 日立鉱山亜硫酸ガス被害 | ||
| 1914(大正3年) | 日立鉱山で156m(当時世界一)の煙突が建設され煙害が減少 | ||
| 1916(大正5年) | 大鉱業家(三井、三菱、住友、古川など)の出資により金属鉱業研究所を設立 | ||
| 1932(昭和7年) | 大阪で煤煙防止規則が制定(日本初の発令) | ||
| 1945(昭和20年) | 第二次世界大戦終戦 経済的豊かさを優先 する戦後に、公害問題が 深刻化 |
||
| 1949(昭和24年) | 東京都が工場公害防止条例を制定 | ||
| 1955(昭和30年) | イタイイタイ病(富山県)が社会問題化 東京都にばい煙防止条約が制定(戦後初) |
||
| 1956(昭和31年) | 水俣病の発生を公式に発表 | ||
| 1961(昭和36年) | 四日市市にぜんそく患者が多発 | ||
| 1962(昭和37年) | ばい煙規正法が制定(日本で最初の大気汚染対策の法律) | ||
| 1964(昭和39年) | 新潟県阿賀野川流域に水銀中毒患者を発見 厚生省に公害課が設立 |
東京オリンピック | |
| 1967(昭和42年) | 公害対策基本法が制定 | 1965年~1971年 公害問題が国会を揺るがす 高度経済成長によってさらなる工業化や都市化が進み、大気汚染だけでなく水質汚濁や自然破壊なども深刻化しました。これらの問題に対応するため公害対策基本法などの環境法が整備され、1970(昭和45)年には国会で公害関連14法案が可決。1971(昭和46)年には環境庁(現・環境省)が発足します。 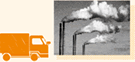 |
|
| 1968(昭和43年) | 大気汚染防止法、騒音規制法を制定 | ||
| 1969(昭和44年) | 政府が初の『公害白書』を発表 救済法が制定(日本で最初の公害被害を救済する法律) |
||
| 1970(昭和45年) | 通称”公害国会”開催 東京で初の光化学スモッグ警報発令 |
大阪万国博覧会 | |
| 1971(昭和46年) | 環境庁が設立 各省庁の公害行政を一本化する環境庁が発足し、自然・環境保全を全面的に扱う機関へ |
||
| 1972(昭和47年) | 環境庁が初の『環境白書』を発行 自然環境保全法が公布 国連人間環境会議が開催(ストックホルム) 国連環境計画(UNEP)が設立 |
1972年~1985年 産業公害型から、都市・生活型の大気汚染へ 環境庁の発足を契機に公害対策の必要性が民間企業にも広がりました。石油ショックによって省資源・省エネルギーへの取り組みが進み、産業公害型の大気汚染が減少する一方で、都市・生活型の大気汚染が増加。自動車の排出ガス規制も本格化します。  |
|
| 1973(昭和48年) | 公害健康被害補償法が制定 第1回環境週間が始まる(6月5日~11日) ワシントン条約が採択 (絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的とした条約) |
石油ショック | |
| 1976(昭和51年) | 「緑の国勢調査」(自然環境保全基礎調査)を開始 | ||
| 1977(昭和52年) | 国連砂漠化防止会議が開催 | ||
| 1979(昭和54年) | 第1回世界気候会議(ジュネーブ)で世界気候計画が採択 | ||
| 1980(昭和55年) | ラムサール条約(水鳥の生息地である湿地に関する条約)とワシントン条約に日本が加盟 | ||
| 1984(昭和59年) | 第1回世界湖沼環境会議が開催(滋賀県) | ||
| 1985(昭和60年) | ウィーン条約(オゾン層保護)が採択 | ||
| 1987(昭和62年) | 国連の環境と開発に関する世界委員会が「持続可能な開発」の考え方を提唱 モントリオール議定書(オゾン層破壊物質削減)が採択 | 1986年~現在 地球温暖化や生物多様性の減少などを受け、環境問題は世界共通の課題に 公害問題や環境問題は1970年代から世界的に表面化し、環境に関する国際的な議論が活発になります。国際社会において「持続可能な開発」という考え方への共通認識が生まれ、今、先進国と開発途上国が協力して地球規模の環境問題へ取り組むことが求められています。 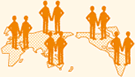 |
|
| 1988(昭和63年) | 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が設置 | ||
| 1989(平成元年) | アルシュ・サミット(初の環境サミット)が開催 | ||
| 1990(平成2年) | 国立公害研究所を国立環境研究所に改組 地球温暖化防止行動計画が決定 |
||
| 1991(平成3年) | 再生資源利用促進法が公布 | ||
| 1992(平成4年) | 環境と開発に関する国連会議(地球サミット)が開催(リオデジャネイロ) 国連人間環境会議から20年を経て、持続可能な開発に向けた地球規模の取り組みを構想 |
||
| 1994(平成6年) | 気候変動枠組条約が発効 | ||
| 1995(平成7年) | 阪神・淡路大震災 | ||
| 1997(平成9年) | 地球温暖化防止京都会議(COP3)にて京都議定書が採択 | ||
| 1998(平成10年) | 家電リサイクル法が公布 | ||
| 1999(平成11年) | 温暖化対策推進法が施行 | ||
| 2000(平成12年) | 循環型社会形成推進基本法が公布 グリーン購入法が公布 食品リサイクル法が公布 |
||
| 2001(平成13年) | 環境庁から環境省へ再編 | ||
| 2002(平成14年) | 自動車リサイクル法が公布 持続可能な開発に関する世界首脳会議が開催(ヨハネスブルク) |
||
| 2005(平成17年) | 京都議定書が発効 | 愛知万国博覧会 | |
| 2006(平成18年) | 石綿による健康被害の救済に関する法律が制定 | ||
| 2008(平成20年) | 会場設備を含め環境配慮が主要テーマの一つとなった主要国首脳会議(洞爺湖サミット)が開催 | ||
| 2010(平成22年) | 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)にて名古屋議定書が採択 | ||
| 2011(平成23年) | 東京電力福島第一原子力発電所事故 | 東日本大震災 | |
| 2012(平成24年) | 福島環境再生事務所を開設 原子力規制委員会が環境省の外局として発足 |
||
| 2013(平成25年) | 政府間交渉委員会第5回会合(INC5)にて水銀に関する水俣条約が採択 | ||
| 2014(平成26年) | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社が発足 | ||
| 2015(平成27年) | 国連サミットにて持続可能な開発目標SDGsが採択 気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)にてパリ協定が採択 |
||
| 2016(平成28年) | パリ協定が発効 | ||
| 2017(平成29年) | 水銀に関する水俣条約が発効 | ||
| 2018(平成30年) | 気候変動適応法が公布 | ||
| 2020(令和2年) | 2050年までに脱炭素社会(カーボンニュートラル)を目指すことを宣言 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | |
| 2021(令和3年) | 熱中症警戒アラートの全国運用開始 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が公布 |
東京オリンピック |

















