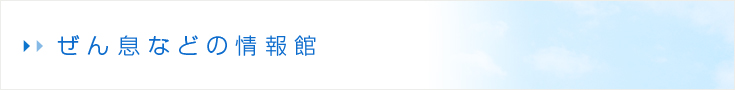
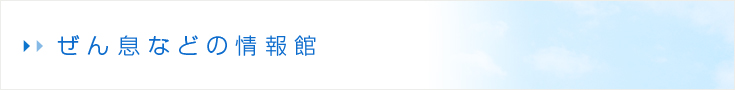
COPDの用語集
あ行
横隔膜
腹腔と胸腔の間にある、筋肉性の膜。呼吸機能に対し、重要な役割を担っている。COPDが悪くなり肺が膨らみすぎになると、横隔膜が平らになってうまく息を吸うことができない。効率のよい呼吸のために普段から横隔膜を鍛えることが大切。
横隔膜呼吸
横隔膜の上下による深い呼吸。腹式呼吸ともいう。おなかを膨らませて息を吸い込むときには横隔膜は下がり、おなかを引っ込めて息をはき出すとき横隔膜は上がる。この呼吸法をマスターすると、息切れを和らげることができる。
か行
カニューラ
在宅酸素療法において、酸素を吸入するために常に装着する鼻チューブのこと。
間質性肺炎
肺胞壁(間質)に炎症が起きる病気。肺が線維化して固く縮み、ついには呼吸ができなくなって、死に至ることもある。せきと息切れが主な症状。塵肺、過敏性肺臓炎、放射性肺炎、感染症などが原因として挙げられるが、その正確な原因は不明であることが多い。
気管支拡張症
気管支が拡張して、気管支の浄化作用が低下し、タンがたまって細菌などが繁殖しやすくなった状態。気管支炎や肺炎を起こしやすくなる。慢性のせきとタンが主な症状で、ときに血タンや喀血が見られる。症状により手術か薬物療法を選択。
胸膜
肺の表面と胸壁の内面とを覆う膜。部位によって横隔胸膜、肋骨胸膜、縦隔胸膜、胸膜頂の4つに分かれる。
胸膜腔
肺と胸腔のすき間。中には少量の液体が入っており、呼吸運動時の摩擦を少なくする役目を果たしている。
口すぼめ呼吸
口笛を吹くようにして息をはく呼吸のこと。ゆっくりと息をはき切ることにより、自然に新鮮な空気を吸い込むことができるため、息切れを和らげるのに有効。腹式呼吸と組み合わせることで、より深く効率的な呼吸ができるようになる。
呼気
呼吸によって肺から排出される気体。
呼吸法
息切れを楽にするには、正しい呼吸法を身につけることが大切。口すぼめ呼吸と腹式呼吸(横隔膜呼吸)が無意識にできるようにするのが理想。
さ行
在宅酸素療法
Home Oxygen Therapy,略してHOT(ホット)。慢性呼吸不全患者に対して行われる家庭酸素療法。睡眠時を含む24時間酸素を吸入することにより、心臓を始めとする臓器のはたらきを正常化し、発作の回数を減らすことができる。酸素の吸入時間が長ければ長いほど生存率は高まる。
酸素濃縮器
在宅酸素療法に用いる酸素供給装置。外出の際には携帯用の酸素ボンベを持ち運ぶ必要がある。
酸素ボンベ
酸素供給装置のひとつ。携帯型の登場により、慢性呼吸不全患者の外出が可能になった。
スパイロメーター
肺に出入りする息の量を測定する器械。COPDの診断に用いる。
せき
肺や気管支にたまっているタンなどの不要物を外に出すための自然な身体の反射運動。
た行
体位排痰法
タンがたまっているところが上になるような姿勢をとり、タンを出やすくする方法。タンは寝ている間にたまりやすいので、起床して1時間以内と、就寝1時間前に行うとよい。
タン
気道から出る分泌液に細菌やホコリ、粘膜細胞などが混じったもの。呼吸器系の感染症などが疑われる。血が混じったり、緑色や褐色をしていたらすぐに医師の診察を受けること。
は行
排痰法
たまったタンを出やすくする方法。体位排痰法や胸に振動を与える方法、器具を使用する方法などがある。
肺動脈
心臓の右心室から流れてくる血液を肺のすみずみに送る血管。血液は右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房→左心室→大動脈と循環している。
肺静脈
肺から心臓の左心房へ血液を受け入れる血管。
肺線維症
肺胞が線維化して硬くなり、伸縮が困難になる病気。間質性肺炎が進行した状態。
肺血栓・塞栓症
静脈系にできた血の塊が血流によって運ばれ、肺動脈に詰まり閉塞する疾患。エコノミークラス症候群として有名になった。診断と治療が遅れると死に至ることもある。
肺気腫
広い範囲にわたって肺胞が壊れ、肺の中に多くの穴が開いてガス交換できなくなる病気。喫煙、大気汚染、粉塵などが原因とされる。
肺がん
現在、日本におけるがんの死因のトップ。50歳以上に多く、男女比は3対1。喫煙が大きな要因として考えられる。
ま行
慢性気管支炎
気管支に慢性の炎症が起こったために、持続性または反復性のタンを伴うせきが2年連続、毎年3か月以上続く疾患。
慢性閉塞性肺疾患
Chronic Obstructive Pulmonary Disease,略してCOPDともいう。気管支の炎症や肺の弾性の低下により気道閉塞を起こし、呼吸困難に至る病気の総称。慢性気管支炎、肺気腫が代表的。せき、タン、息切れが主な症状で、最も大きな原因はたばこ煙とされる。WHOの統計によれば、世界の死亡原因の第4位にランクされ、日本でも年々患者数が増えている。
むくみ
肺が原因で心臓に負担がかかると、足首やすねにむくみが出る。利尿薬で過剰な水分を外に排出するが、急なむくみと息切れがあるときは、心不全が疑われるので、病院で診察を受けたほうがよい。

















