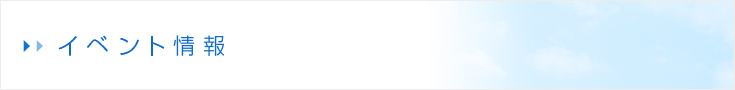
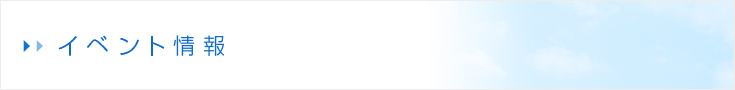
令和7年度呼吸ケア・リハビリテーション指導者養成研修
概要
ぜん息及び慢性閉塞性肺疾患(COPD)の主な症状は咳、痰と呼吸困難であり、薬物療法は症状改善に有用でありますが、呼吸困難やそれに伴う日常生活動作の低下に対して呼吸リハビリテーションを併せて行うことで更なる症状の改善を期待することができ、「COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン」においても、その有用性について言及されているところです。
独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)では、公害健康被害予防事業対象地域において呼吸リハビリテーションを専門とする理学療法士等の能力を向上させ、呼吸リハビリテーションの普及を図ることを目的として、「令和7年度呼吸ケア・リハビリテーションスタッフ養成研修」をオンライン形式で実施しております。(研修の詳細はこちらをご確認ください。)
また、地方公共団体が実施する各種事業においては、呼吸リハビリテーションを指導する医療従事者(理学療法士、看護師等)の確保が難しく、地方公共団体や地域の患者ニーズと医療従事者のマッチングが困難であることから、呼吸リハビリテーションの知見を備え、公害健康被害予防事業対象地域の地方公共団体及び患者等のニーズを把握し、各地域で活躍できる医療従事者の育成がより一層求められています。
このことを踏まえ、予防事業研修の内容の理解をより深めるために水島地域において「呼吸ケア・リハビリテーション指導者養成研修」を実施いたします。
実施日時
令和7年11月6日(木)~11月7日(金)
- 研修実施会場
-
11月6日(木)水島愛あいサロン(岡山県倉敷市)
〒712-8057
岡山県倉敷市水島東千鳥町1-50
アクセス: https://mizushima-ii.com/access-2/ (外部サイトへリンクします。)
(外部サイトへリンクします。)
11月7日(金)倉敷市民会館
〒710-0054
岡山県倉敷市本町17-1
アクセス: https://arsk.jp/shimin/access/ (外部サイトへリンクします。)
(外部サイトへリンクします。)
対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する者とします。
- (1)公害健康被害予防事業に従事する理学療法士、看護師、保健師等(予定の者を含む。)
- (2)地方公共団体の保健事業に関わる医療・保健指導従事者で、地方公共団体の責任において特に参加させることが必要と認められる者
- (3)一般社団法人日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医又は呼吸器指導医の下で、COPD患者への呼吸リハビリテーションに取り組んでいる者(予定の者を含む。)
※定員を上回る申込があった場合は、勤務先の地方公共団体又は医療機関等(訪問看護ステーション、介護施設を含む。)の所在地が公害健康被害予防事業対象地域*の地方公共団体又はその都府県にある者を優先します。
研修の概要
研修の目的を踏まえ、研修内容は、呼吸リハビリテーションの指導に要する医学的スキルに加え、地方公共団体が行う各種事業の企画・立案、集団指導における講師及び保健所等に勤務するスタッフへの指導等に必要な知識を習得するために、オンラインプログラム及び実地プログラム(実習、フィールドワーク等)により構成し、下表のとおりとします。
【オンラインプログラム】
| 日付 | 時間 | 演題 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 事前オンライン学習 | |||
| 本事業の目的について | 環境再生保全機構 | ||
| ぜん息・COPD患者に対する呼吸ケア・リハビリテーションの有用性について | 兵庫医科大学 副学長・教授 一般社団法人日本呼吸理学療法学会理事長 玉木 彰 先生 |
||
| COPDの病態について | 公益財団法人結核予防会複十字病院 病理診断部 部長 岡 輝明 先生 |
||
| COPD患者におけるセルフマネジメント支援の基礎と実際(在宅酸素療法) | 順天堂大学大学院 医療看護学研究科 教授 若林 律子 先生 |
||
| 呼吸リハビリテーションコンディショニング/運動療法/ADL トレーニング | びわこリハビリテーション専門職大学 リハビリテーション学部 学部長・教授 千住 秀明 先生 |
||
| 身体所見の取り方と呼吸リハビリテーション基本手技【実技】 | びわこリハビリテーション専門職大学 リハビリテーション学部 学部長・教授 千住 秀明 先生 |
||
| 呼吸リハビリテーション/栄養指導 | 関東学院大学 栄養学部 管理栄養学科 学部長・教授 田中 弥生 先生 |
||
| 事例紹介 | 日本赤十字社 前橋赤十字病院 呼吸器内科 部長 堀江 健夫 先生 |
||
【実地プログラム】
| 日付 | 時間 | 演題 | 講師 |
|---|---|---|---|
| 1日目 11月6日(木) |
9:50 | 倉敷駅前 集合(バス移動) | ー |
| 10:00~10:15 | 【講義】研修について(バス車内) | 環境再生保全機構 | |
| 10:15~10:30 | 【講義】フィールドワークについて | ||
| 10:30~10:40 | フィールドワーク① みずしま資料交流館 (あさがおギャラリー)見学 |
水島地域環境再生財団 副理事長 福田憲一氏 |
|
| 10:40~11:00 | 【講義】医療者がとりくむ『環境』」の課題~過去・現在・未来~」 | ||
| 11:00~11:15 | 【講義】 研修の開催にあたって 公害健康被害補償・予防事業について |
環境再生保全機構 | |
| 11:15~11:45 | バス移動 【講義】水島地域について(1) |
水島地域環境再生財団 理事 塩飽敏史氏 |
|
| 11:45~11:55 | フィールドワーク② 鷲羽山スカイライン水島展望台視察 |
||
| 11:55~12:30 | バス移動 【講義】水島地域について(2) |
||
| 12:30~13:30 | 昼休憩 | ー | |
| 13:30~14:00 | 【視察・講義】倉敷市の大気監視の仕組み、環境学習 (倉敷市環境学習センター環境学習教室・監視センター) |
未定 | |
| 14:00~14:30 | 【講義】倉敷市保健行政の課題、行政ニーズについて (倉敷市環境学習センター環境学習教室) |
岡山県倉敷市役所 健康づくり課課長 |
|
| 14:30~14:45 | 休憩・徒歩移動 | ー | |
| 14:45~15:15 | フィールドワーク③ 【見学】 呼吸リハビリ講座 肺年齢測定 (水島愛あいサロンコミュニティフロア) |
ー | |
| 15:15~15:45 | 【講義】呼吸リハビリテーションの地域連携、ぜん息・COPD患者のニーズについて | 水島地域環境再生財団 事務局長 藤原園子氏 |
|
| 15:45~17:00 | 実習】呼吸リハビリテーション指導 実習1(水島愛あいサロン 会議室) |
千住秀明先生 水島地域の患者(希望者) |
|
| 17:00~18:00 | 【ふりかえり】参加者意見交換会 | 水島地域環境再生財団 理事 塩飽敏史氏 |
|
| 18:00 | 解散 | ー | |
| 2日目 11月7日(金) |
10:00~12:00 | 呼吸リハビリテーション指導 実習2 | 千住秀明先生(教授) 補助講師(人材バンク) (人数については未定) |
| 12:00~13:00 | 昼休憩 | ||
| 13:00~15:00 | 呼吸リハビリテーション指導 実習3 | ||
| 15:00~15:15 | 休憩 | ||
| 15:15~16:15 | 呼吸リハビリテーション指導 実践1 | ||
| 16:15~16:30 | 閉会にあたって | 環境再生保全機構 |
定員
20名程度
研修参加費用
研修への参加費は無料とします。また、研修生には、独立行政法人環境再生保全機構旅費規程に準じ、研修生の勤務先最寄り駅から研修開催地までの旅費を支給いたします。
ただし、研修生の所属する職場、機関等より本研修の参加に際し、旅費が支給される場合には支給しません。
研修受講条件
- (1)原則として、全カリキュラムに出席できること。
- (2)研修修了者は、機構が別途設置する「ERCA予防事業人材バンク」に登録し、地方公共団体が行う予防事業及び機構が実施するパッケージ支援事業等における講師、補助スタッフとして、積極的に協力すること。
- (3)研修終了後に機構が別途提示する研修受講報告書(アンケート)を提出すること。
申込方法及び決定等
研修対象者の要件を満たしている者で本研修への参加を希望する者は、以下の機構ホームページ上の申込フォームにアクセスし、【2025年10月17日(金)まで】に必要事項を入力して申し込むこと。
その他注意事項等について
- (1)申込多数の場合は、機構にて参加可否を決定するため、申込後の機構からの通知をもって参加確定とさせていただきます。
- (2)研修当日は、動きやすい服装でご参加ください。また、持ち物として、聴診器、バスタオル(枕として代用を予定)を持参してください。
聴診器を用意できない場合には、申込時にあらかじめ機構に申し出てください。 - (3)実習については、男女別にいくつかのグループに分かれ、実習を行うため、ペアとなった参加者及び講師が身体に触れる場合があります。
- (4)意欲をもって講義にご参加ください。また、必要に応じて事前に案内のあった課題について予習して臨んでください。
- (5)本研修を受講することにより、参加者自身のスキル向上だけではなく、地域や医療機関での呼吸リハビリテーションの普及、公害健康被害予防事業の効果的、効率的な推進等に努めてください。
- (6)疾病等により、研修の受講継続が不可能と認められる場合や研修生の資質が研修運営に支障があると認められる場合には、研修生を帰任させることがあります。
- (7)本研修の全カリキュラムを受講した者に対して、研修修了証を発行します。
【問い合わせ先・受講申込先】
独立行政法人環境再生保全機構 予防事業部事業課 実習会担当:佐々木、佐藤
〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー 8階
TEL:044-520-9570 E-mail:hoken@erca.go.jp

















