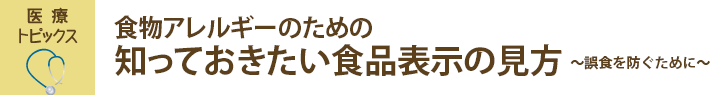![]() すこやかライフNo.42 2013年9月発行
すこやかライフNo.42 2013年9月発行
医療トピックス
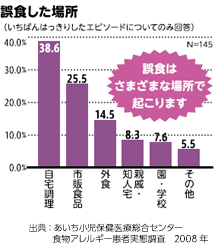
2012年末に東京都調布市の小学校で起こった食物アレルギーによる死亡事故をきっかけに、食物アレルギー児の誤食を防ぐための対応について、注目が集まっています。
しかし、右のグラフを見てもわかるとおり、園や学校だけでなく自宅や外出先など、誤食はいつでも、どこでも起こる可能性があります。誤食を防ぐために、まずは食物アレルギーを引き起こす食品について、正しい知識を身につけておく必要があります。
そこで今回は、誤食を防ぐために大切な「食品表示の見方」について、あいち小児保健医療総合センター内科部長 伊藤浩明先生のお話をもとに詳しく紹介していきます。
より詳しくは、次のメニューからご覧ください
- アレルギー表示対象品目とは
- 最近の食物アレルギーの傾向
- 加工食品における食品表示の主なチェックポイント
- 食品表示 知っておきたい読み方テクニック
- 食品表示にまつわる「ひやりはっと事例」から学ぶ誤食を防ぐ食品表示の活用法
- 食べられる範囲を広げ「楽しい」食生活を送ることを目標に
お話をうかがった先生
あいち小児保健医療総合センター 内科部長 伊藤 浩明先生

プロフィール
1986年名古屋大学医学部卒業。同大学院内科系小児科学、米国テキサス大学留学、国立名古屋病院などを経て、2001年よりあいち小児保健医療総合センターアレルギー科医長。2010年より現職。日本アレルギー学会指導医、日本小児科学会専門医。
メッセージ
食物アレルギーで原因食品を完全に除去している方は、買い物の時には必ずアレルギー表示をチェックすることが必要です。この制度のおかげで、アレルギーのお子さまを持つ方も普通のスーパーで買い物することができ、給食や外食などでも安全な食事を責任持って提供することが可能となりました。もし、原因物質が表示されていない食品でも明らかに強いアレルギー症状が出現した場合には、その食品を保存した上で、主治医と同時に保健所の食品衛生担当者に相談してください。アレルギー物質混入の可能性について、製造販売業者に確認し、混入の有無をチェックしてくれることもあります。
示制度は、国の法律で厳密に運営されているために信頼できる反面、制度上の込み入ったルールや、言葉の上でどうしても誤解しやすい点があります。この制度を良く理解して、有効に活用しましょう。