

すこやかライフNo.48 2016年9月発行
![]() 医療トピックス:在宅酸素療法のスムーズな導入・継続のために
医療トピックス:在宅酸素療法のスムーズな導入・継続のために
困ったときに役立つ社会的なサポートを活用しましょう
在宅酸素療法を進めるにあたっては、医療費や機器の維持費などの経済的な負担が発生します。また、家族のサポートや介助者が必要になる場面も多々あります。とくに高齢者世帯やひとり暮らしの場合は、困ったことが起こったときに相談できる場所や人を見つけておく必要があります。現在、在宅酸素療法の患者さんたちを支援する社会的なサポートとしては、おもに「介護保険制度」と「身体障害者手帳」があります。
1. 在宅で療養する不安を解消する「介護保険制度」
介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支えあう制度です。40歳以上の人が保険料を納め、介護が必要となったときに費用の一部を負担するだけでさまざまなサービスを利用することができます。
介護保険の申請をすると、調査が行われ、要介護度(介護を必要とする度合い:要支援1・2、要介護1~5)が判定されます。この判定に応じて、受けられるサービスが決定します。
在宅酸素療法の導入にともない、介護や支援が必要だと感じたら、まずは住んでいる地域の「地域包括支援センター(下記参照)」に相談しましょう。
おもな介護保険のサービス
- 訪問介護
- ホームヘルパーが自宅を訪問し、家事や入浴など、生活のお手伝いをしてくれます。
- 訪問看護
- 看護師が自宅を訪問し、酸素供給装置のチェックや体調・薬の管理などをしてくれます。
- 福祉用具のレンタルや購入の補助、住宅改修費の補助
- 電動ベッドや車いすなどのレンタルや、住宅の改修費などを支給してもらえます。
*ただし、いずれも要介護度に応じて利用できる場合と利用できない場合があり、自己負担する費用も異なります。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんが住みなれた町で安心して暮らしていけるように、介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から高齢者とそのご家族を支える機関です。市区町村が運営し、地域ごとに必ず設置されていて、誰でも利用することができます。
- 介護保険を利用してみたいけれど、どうすればいいの?
- 買い物のときに手伝いがほしい。
- 具合が悪くなったときに相談できる場所がほしい。
など、困ったことは気軽に相談してみましょう。
地域包括支援センターへ行けない場合、電話で連絡すれば、センターの職員が自宅を訪問してくれます。
今は必要ないという方も、まずはお住まいの地域の「地域包括支援センター」がどこにあるのか、把握しておきましょう。
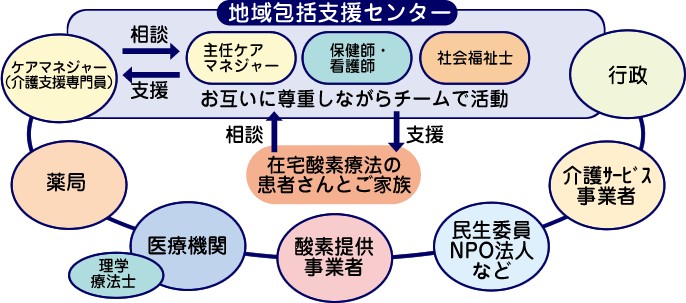
2. 医療費助成などがある「身体障害者手帳」
在宅酸素療法が必要となった場合、状態に応じて「身体障害者手帳」の交付を受けることができます。
呼吸機能障害は、1級、3級、4級の3段階に区分されており、各自治体によって異なりますが、おもに医療費の助成や年金・手当の給付、税金・交通費・公共料金の減免、生活支援などが受けられます。
身体障害者手帳を交付してもらうためには、申請が必要です。まずは主治医に相談し「意見書」を作成してもらい、市町村の福祉事務所(もしくは障害福祉担当課)に相談してみましょう。
1日1回外に出て季節を感じてみましょう
 在宅酸素療法は、外出時に酸素ボンベを携帯しなければならないなど、負担になることが多いかもしれません。しかし、今回ご紹介したように機器は進歩し、介護保険制度などの社会的なサポートも充実してきました。
在宅酸素療法は、外出時に酸素ボンベを携帯しなければならないなど、負担になることが多いかもしれません。しかし、今回ご紹介したように機器は進歩し、介護保険制度などの社会的なサポートも充実してきました。
酸素を吸っているから活動を制限するのではなく、酸素を吸うことで楽に動けるようになり、苦しかったときよりも活動範囲を広げることができるのが、在宅酸素療法のメリットです。家の中にこもりきりでは気分も沈んでしまいます。まず1日1回は外に出て、季節を感じてみましょう。少し動けるようになると、次は散歩してみよう、買い物に出かけてみようという意欲につながるはずです。自分らしく生活するための「在宅酸素療法」を目指しましょう。
- 前のページへ(酸素を吸いながら生活しやすい環境をつくる)
- 困ったときに役立つ社会的なサポートを活用しましょう
- 医療トピックスコーナートップに戻る

















