

![]() すこやかライフNo.51 2018年3月発行
すこやかライフNo.51 2018年3月発行
現場レポート
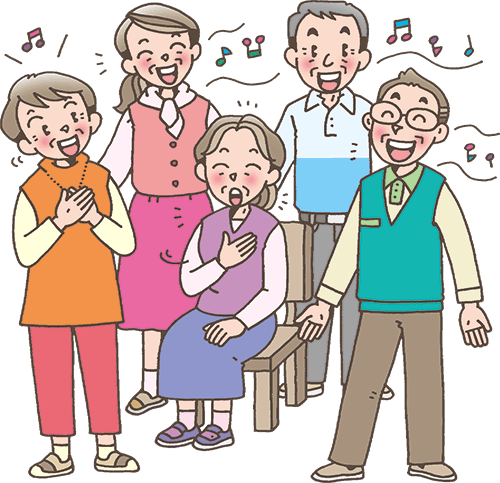
歌を歌う、楽器を演奏する、音楽を聴くことによって、心身の健康の回復・向上を図る音楽療法。認知症の改善、脳血管障害後遺症のリハビリテーションなどを中心に幅広く実践されています。
では、ぜん息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)をはじめとする呼吸器疾患には、どのような効果があり、実際にどのような形で行われているのでしょうか。今回は、成人、高齢者を対象とした取り組みについて、自治体と呼吸器専門病院の例をご紹介します。
ぜん息発作やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)になると息を吐き切れなくなり、呼吸がうまくできなくなります。このとき、横隔膜(胸とお腹の間の筋肉)を使った腹式呼吸を行うと、肺が押し上げられ空気が吐き出されて、呼吸が楽になります。この腹式呼吸を自然な形で習得できるのが、音楽療法です((山﨑先生に聞く)なぜ、腹式呼吸を覚えるのに音楽療法がいいの?参照)。
音楽療法はまた、病気自体や治療、リハビリテーションに伴うストレスの緩和、そして身体活動性やQOL(生活の質)向上にも効果があるといわれています。
こうした観点から、東京都荒川区、および霧ヶ丘つだ病院(福岡県北九州市)の取り組みを見ていきます。
より詳しくは、次のメニューからご覧ください
お話をうかがった先生
声楽家・作曲家 清泉女学院短期大学 教授 山﨑浩(やまざき・ひろし)先生

プロフィール
国立音楽大学声楽科卒業。声楽家・作曲家として舞台活動をする傍ら、「音楽とこころの健康」をテーマとした講演活動多数。また東京都内で、病院の精神科デイケア講師、特別区8区の呼吸器音楽療法講座講師も務める。
読者へのメッセージ
音楽は年齢を問わず私たちに必要なものであり、心を豊かにしてくれるものです。音楽を嫌いな人はいません。誰でもが持っている「自分の心を動かす音楽」を味わうことで、私たちはリラックスすることができます。心身がリラックスした状態で「歌う」ことは、理想的な深い呼吸活動をもたらします。まず音楽を心から楽しみ、リラックスした状態で積極的に「歌う」ことを通して腹式呼吸の「呼気」、そして「吸気」を体感してみてください。
霧ヶ丘つだ病院 理事長・院長 久留米大学医学部 臨床教授 津田徹(つだ・とおる)先生

プロフィール
1982年、久留米大学医学部卒。産業医科大学、カリフォルニア大学サンフランシスコ校を経て産業医科大学産業生態科学研究所作業病態学講師、呼吸病態生理学助教授。医学博士。現在、霧ヶ丘つだ病院理事長兼院長。日本呼吸器学会指導医、日本睡眠学会認定医、日本内科学会認定医、日本呼吸ケア・リハビリテーション学会理事など。
読者へのメッセージ
COPDの患者さんのほとんどは、長年、たばこを吸ってきて「たばこに縛られた人生」を送られてきたと思います。COPDと診断された以上(されなくても)、まず禁煙をし、たばこに替わる新たな楽しみを見つけましょう。もちろん音楽ではなく、他のものでも構いません。
楽しいこと、毎日の生活の張りとなるものが一つでもあれば、心身ともに活性化され、必ずCOPDの治療にも良い影響を及ぼします。
霧ヶ丘つだ病院 医療相談室長 末松利加(すえまつ・りか)先生

プロフィール
産業医科大学呼吸器科教授秘書・研究補助員を経て、1999年に津田内科病院(現:霧ヶ丘つだ病院)に入職。現在、医療ソーシャルワーカー(医療相談室長)と医療連携室を兼ねる。福岡県下の医療ソーシャルワーカー(経験3年未満)の基礎講座の講師なども務める。日本禁煙学会認定専門指導者、日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー/インストラクター。
読者へのメッセージ
COPD 患者さんは息切れがつらくて動きが制限されるなど、病気になっただけでストレスになります。在宅酸素療法でカニュラを付けたりしていたら、なおさらでしょう。
しかしそのストレスは、好きなことがあれば、相当軽減することができます。笑顔で大きな声で歌っている患者さんたちから、そのことを教わりました。こころと体は密接につながっています。何か好きなことを見つけて、心身ともに生き生きと毎日を送ってください。


















