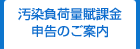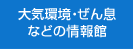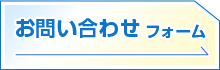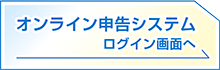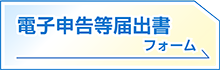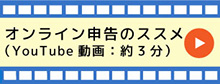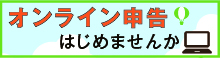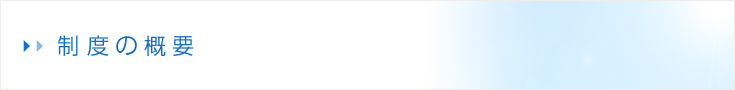
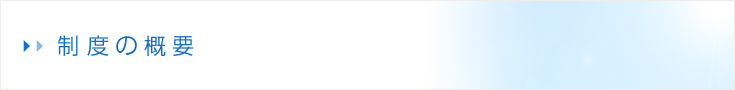
納付義務者について(詳細な解説)
納付義務者の要件
(1)1987年(昭和62年)4月1日にばい煙発生施設等を設置していたこと。
解説
法律では、第五十二条第一項第二号において「その解除があつた日(以下「基準日」という。)の前日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において」と定めています。
1988(昭和63)年3月1日に第一種地域の指定がすべて解除されましたので、法律に基づくと「基準年度」は1987(昭和62)年度であり、「属する年度の初日」とは1987(昭和62)年4月1日となります。
(2)その施設が硫黄酸化物を排出し得るものであったこと。
解説
法律では、第五十二条第一項第二号において「前号の政令で定められていた物質(以下「対象物質」という。)を排出するばい煙発生施設が設置され」と定めています。
これは、昭和六十二年政令第三百六十八号による改正前の政令第二十八条において「硫黄酸化物」と定められていましたが、1988(昭和63)年3月1日の第一種地域の指定解除に伴う制度改正により、政令第二十八条は削除されました。
(3)その施設が設置されていた工場・事業場における最大排出ガス量の合計が指定地域解除前の地域区分に応じて定められていた次の量以上であったこと。
旧指定地域 5,000m3N/h
その他地域 10,000m3N/h
解説
法律では、第五十二条第一項第二号において「最大排出ガス量が基準年度の初日において同号の政令で定められていた地域の区分に応じて同号の政令で定められていた量以上であつた工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者」と定めています。
これは、昭和六十二年政令第三百六十八号による改正前の政令第二十九条において別表第三により地域の区分に応じて最大排出ガス量が定められていましたが、1988(昭和63)年3月1日の第一種地域の指定解除に伴う制度改正により、政令第二十九条及び別表第三は削除されました。
公害健康被害の補償等に関する法律(抜粋)
地域及び疾病の指定
第二条 この法律において「第一種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴つて相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病(次項に規定する疾病を除く。)が多発している地域として政令で定める地域をいう。
汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務
第五十二条 機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第一項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第十三条第二項の規定による支払に要する費用並びに機構が行う事務の処理に要する費用(以下「補償給付支給費用等」という。)の一部に充てるため、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設が設置される工場又は事業場を設置し、又は設置していた事業者で、次に掲げるもの(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から、毎年度、汚染負荷量賦課金を徴収する。
一 第一種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である政令で定める物質を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が政令で定める地域の区分に応じて政令で定める量以上である工場又は事業場を、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日において設置している事業者
二 第一種地域の指定がすべて解除された場合にあつては、その解除があつた日(以下「基準日」という。)の前日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において前号の政令で定められていた物質(以下「対象物質」という。)を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が基準年度の初日において同号の政令で定められていた地域の区分に応じて同号の政令で定められていた量以上であつた工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者。ただし、基準日以後も基準日前にされた第四条第一項の認定に係る被認定者及び認定死亡者(以下「既被認定者」という。)に関する補償給付支給費用等が生ずる場合に限る。
2 第一種地域の指定がすべて解除された場合において、基準日がその属する年度の初日の翌日以後の日であるときは、前項第二号に掲げるばい煙発生施設等設置者に対する同項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「基準日の属する年度の翌年度から毎年度」とする。
3 ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。
改正前の施行令(解説)
施行令では、第一条で指定地域について、第二十八条で対象物質について、第二十九条で最大排出ガス量について、それぞれ定めています。
【改正前】公害健康被害補償法施行令(抜粋)
第一種地域及び第二種地域並びにこれらの地域に係る疾病の指定
第一条 公害健康被害補償法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第一のとおりとする。
二 法第二条第二項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。
汚染負荷量賦課金の賦課対象物質
第二十八条 法第五十二条第一項の政令で定める物質は、硫黄酸化物とする。
最大排出ガス量
第二十九条 法第五十二条第一項の最大排出ガス量(同項に規定するばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。)につき政令で定める量は、別表第三の第二欄に上げる地域の区分に応ずる同表第三欄に揚げる量とする。
単位排出量当たりの賦課金額
第三十条 法第五十四条の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した硫黄酸化物一立方メートルにつき、別表第三の第二欄に揚げる地域の区分に応ずる同表の第四欄に揚げる金額とする。
別表第三(第二十九条、第三十条関係)
| 一 | 別表第一の二十八の項から三十一の項まで及び三十二項の項に揚げる地域 | 五、○○○立法メートル | 省略 |
|---|---|---|---|
| 二 | 別表第一の二の項から二十二の項までに揚げる地域 | 五、○○○立法メートル | 省略 |
| 三 | 別表第一の一の項、二十四の項、二十五の項及び三十一の二の項に揚げる地域 | 五、○○○立法メートル | 省略 |
| 四 | 別表第一の二十三の項、二十六の項、二十七の項及び三十三の項から三十七の項に揚げる地域 | 五、○○○立法メートル | 省略 |
| 五 | 別表第一に揚げる地域以外の地域 | 一○、○○○立法メートル | 省略 |
指定地域解除 1988(昭和63)年3月1日

改正後の施行令(解説)
1988(昭和63)年3月1日の第一種地域の指定解除に伴う制度改正により、指定地域、対象物質、最大排出ガス量の条文は削除されました。
改正後は、第三十四条第一号で過去分賦課料率を第二号で現在分賦課料率を、毎年度、政令で定めています。
【改正後】公害健康被害の補償等に関する法律施行令(抜粋)
第二種地域及び疾病の指定
第一条 公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める地域及び同項に規定する疾病は、別表第二のとおりとする。
第二十八条から第三十条まで 削除
単位排出量当たりの賦課金額
第三十四条 法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
一 法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第五十三条第一項第二号イに規定する累積量一立方メートルにつき、-省略-
二 法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額
【参考】●昭和六十二年政令第三百六十八号(抜粋)
公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令
公害健康被害補償法施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
第一条の見出しを「(第二種地域及び疾病の指定)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「法」を「公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)」に改め、同項を同条とする。
第二十八条から第三十条までを次のように改める。
第二十八条から第三十条まで 削除
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
別表第三を次のように改める。
別表第三 削除
別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第三十二条関係)
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
昭和六十三年政令第七十八号(抜粋)
公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令
第三十八条を第三十九とし、第三十四条から第三十七条までを一条ずつ繰り下げ、第三十三条の次に次の一条を加える。
(単位排出量当たりの賦課金)
第三十四条 法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
一 法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額 温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第五十三条第一項第二号イに規定する累積量一立方メートルにつき、四十五円七十六銭
二 法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額 標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の第二欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の第三欄に掲げる金額
別表第四の次に次の一表を加える。
別表第五(第三十四条関係)
附 則
1 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
情報コーナー
 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロードPDF形式のファイルはadobe readerが必要です。