

すこやかライフNo.45 2015年3月発行
![]() 特集:アレルギー児の安心・安全な学校生活のために 入学・進学のときに知っておきたいこと
特集:アレルギー児の安心・安全な学校生活のために 入学・進学のときに知っておきたいこと
「学校生活管理指導表」の提出が基本
学校でのアレルギー疾患対策の基本となるのが、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(以下「学校ガイドライン」)であり、主治医、保護者、学校の情報共有の手段として使用されるのが「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」です。
とくに食物アレルギー児への対応については、2012年12月に起こった調布市での事故を受け、文部科学省が14年3月に各都道府県などに向け、学校における食物アレルギー対応において「学校ガイドライン」および「学校生活管理指導表」の活用を徹底するよう通知を行っています。今後は、学校においてアレルギー児に対する配慮が必要な場合、学校生活管理指導表の活用が一層重要になっていくと考えられます。
学校生活管理指導表を書いてもらうときが治療を見直すチャンス
アレルギー疾患は成長とともに症状が変化しやすい疾患であるため、学校生活管理指導表は毎年更新し提出します。
1年に一度、学校生活管理指導表を書いてもらうためにアレルギーに精通した専門医を受診することで、ぜん息のコントロール状態がもっと良くなるかもしれません。食物アレルギーは、成長とともにそれまで食べられなかったものが食べられるようになる「耐性獲得(アウトグロー)」しやすい疾患なので、食物経口負荷試験(すこやかライフ45号 医療トピックス 3 食物経口負荷試験)を受けることで、食べられる食物が増えていることを確認できることもあるでしょう。
このように、学校生活管理指導表を書いてもらうときが、アレルギー疾患に対する治療を見直すチャンスととらえ、専門医を受診して治療の見直しをしてもらいましょう。
- (注)保育所向けには、厚生労働省より「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」が発行されています。詳しくは、すこやかライフ40 号「現場レポート」をご覧ください。
学校生活管理指導表の活用のしかた
では、学校生活管理指導表を使ってどのように学校と情報を共有すればよいのでしょうか。活用のしかたと学校との面談時に伝えたいポイントをご紹介します。
活用のしかたのポイント
 管理指導表は基本的に、入学前の就学時健診の際にアレルギーがあることを伝え、学校から受け取ります。
管理指導表は基本的に、入学前の就学時健診の際にアレルギーがあることを伝え、学校から受け取ります。 提出が必要なのは、学校生活において学校側の配慮が必要と保護者が考えるアレルギー児のみです。
提出が必要なのは、学校生活において学校側の配慮が必要と保護者が考えるアレルギー児のみです。
たとえば「ぜん息がある」という場合でも、症状がコントロールされており、とくに学校での特別な配慮が必要でない児童・生徒は提出する必要はありません。
ただし、なかにはアレルギーがあるとわかった場合、必ず提出を求める学校もあるため、学校側に確認しておきましょう。 自己判断で書くのではなく、医師が正しい診断のもとに記入します。
自己判断で書くのではなく、医師が正しい診断のもとに記入します。
学校生活管理指導表は医師の診断書代わりです。医師の正しい診断、客観的な評価が根拠となってはじめて、保護者の思い込みではなく学校での対応が必要であることを、学校側に伝えることができます。- (注)文書料が発生することがあります。あらかじめ病院に確認しましょう。
 教職員全員で情報共有してもらうことに同意しましょう。
教職員全員で情報共有してもらうことに同意しましょう。
学校において子どもが重篤な症状に陥ってしまった場合、どの学校職員にも一刻も早く気づいて対応してもらうためには、職員全員で情報共有してもらうことが重要です。情報共有欄に必ず署名して提出しましょう。
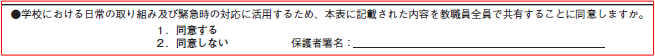
 緊急時の「連絡医療機関」を事前に確認しましょう。
緊急時の「連絡医療機関」を事前に確認しましょう。
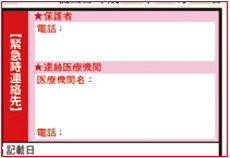 緊急時の連絡先が必要だと考えられる児童、生徒(たとえば、アナフィラキシーショックやぜん息の大発作で、緊急搬送が必要になるおそれのある児童、生徒)の場合に医師が記載する欄です。
緊急時の連絡先が必要だと考えられる児童、生徒(たとえば、アナフィラキシーショックやぜん息の大発作で、緊急搬送が必要になるおそれのある児童、生徒)の場合に医師が記載する欄です。
緊急時の搬送先などについては、主治医に相談しましょう。
面談時、とくに学校に伝えておきたいポイント
学校生活管理指導表の提出後、面談の場が設けられます。学校生活管理指導表をもとに、「何かあったら」というような抽象的な表現ではなく、「どんな症状のときにどうするのか」など具体的なルール作りをすることが大切です。ただし、学校の体制などにより、すべての要望が受け入れられるわけではないことを理解しておきましょう。
 何のアレルギーがあって重症度がどのくらいなのか
何のアレルギーがあって重症度がどのくらいなのか
〈たとえば〉
「うちの子は牛乳の食物アレルギーで「アナフィラキシー」を起こしたことがあります。医師には重い食物アレルギーだと診断されていますので、配慮をお願いします。」
このような場合、学校側も「アナフィラキシー」とは何なのか、正しい認識を持っていないと、事故につながるおそれが高まります。学校、保護者それぞれがアレルギー疾患に対する正しい知識を持ち、病気の重症度について共通認識を持つことが、対応の基本といえるでしょう。 いつ、どんな症状が出るのか、どんな対応が必要なのか
いつ、どんな症状が出るのか、どんな対応が必要なのか
〈たとえば〉
「運動をするとぜん息の発作が出ることがあります。その場合は、腹式呼吸をさせ少し休ませて様子をみてください。発作がおさまれば、運動を再開できます。」 レポート用紙1枚程度にまとめて提出を
レポート用紙1枚程度にまとめて提出を
学校生活管理指導表だけでは伝えきれないことを書面にまとめ、提出するとよいでしょう。
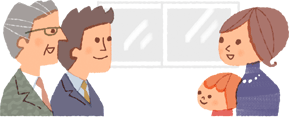 学校生活には、学校側も気づかないアレルギー児にとってのリスクが潜んでいるおそれがあります。次ページ(ぜん息児の場合) から紹介する、「アレルギー児が症状を起こしてしまうおそれのある状況」をもとに、面談時にあらかじめ学校に伝えておきたい事項をチェックしてみましょう。
学校生活には、学校側も気づかないアレルギー児にとってのリスクが潜んでいるおそれがあります。次ページ(ぜん息児の場合) から紹介する、「アレルギー児が症状を起こしてしまうおそれのある状況」をもとに、面談時にあらかじめ学校に伝えておきたい事項をチェックしてみましょう。
- (注)基礎知識習得のために、環境再生保全機構のパンフレットをご活用ください。
- 特集コーナートップに戻る
- 「学校生活管理指導表」の提出が基本
- 次のページへ(ぜん息児の場合)

















