

すこやかライフNo.46 2015年9月発行
![]() 現場レポート:食物アレルギーのある子どもたちの修学旅行時の食事対応について
現場レポート:食物アレルギーのある子どもたちの修学旅行時の食事対応について
特定原材料7品目は「責任をもって除去」
手順書は、食物アレルギーのある子どもについて、事前にどんな情報をどのように入手するかも、整理・統一しました。
手順書に記載された事前調査票(図1)では、保護者に対しまず、「現在、医師に食物アレルギーと診断され通院しているかどうか」を尋ねます。この質問は、「本当に食物アレルギー対応が必要な児童・生徒」だけを選び出し、現場の煩雑さを少しでも減らすためのものです。現時点での診断・通院の有無を聞くことで、本当は食べられるのに単なる好き嫌いで除去を求めたり、耐性を獲得し食べられる可能性があるのに、乳幼児の時の診断を根拠に保護者が「食べられない」と、思い込んだりしている場合が除外されます。
除去する食品は、加工食品の表示義務のある特定原材料7品目注1に限定しました。これは、コスト的な制約がある修学旅行の食事では加工食品を使う割合が高いこと、特定原材料には症例が多く症状も重いアレルゲンが指定されていることを踏まえ、「最低限、特定原材料をチェックすれば、誤食のリスクを大幅に減らすことができる」という考え方に基づいています。
また、表示義務がある特定原材料は、受け入れ施設側にとって「責任をもって除去します」と明言できる材料です。一方、それ以外のアレルゲンは、表示義務がない(=表示されていない可能性がある)ことから、調査票では「確認できないことがあります」とはっきり書き、個別に相談に応じることとしています。
アレルゲンではなくメニューの一覧を保護者に示し、除去してほしいものに印を付けさせる方法もよく使われていますが、保護者が食材を正確に確認できず、アレルゲンを見落とすおそれがあります。アレルゲンそのものを指定する手順書の方法ならば、このような見落としも避けられます。
伊藤先生は、「施設側ができること、しなければならないことのベースラインを定めたのが手順書です。その先は各施設の体制に応じて、独自のマニュアルをつくるなどの対応をしてもらうこととしました」と語ります。
手順書では、情報(事前調査票)の流れも明確化しました(図2)。京都府健康福祉部理事の中本晴夫さんによれば、「保護者、学校、旅行会社、受け入れ施設が情報共有し、また、それぞれの役割も明らかにすることで、誤食防止や緊急時の対応を間違いないものにすることを目指しました」といいます。
- 注1
- 加工食品のアレルギー表示については、トピックス(アレルギー表示の対象は27品目)をご覧ください。
図1 事前調査票
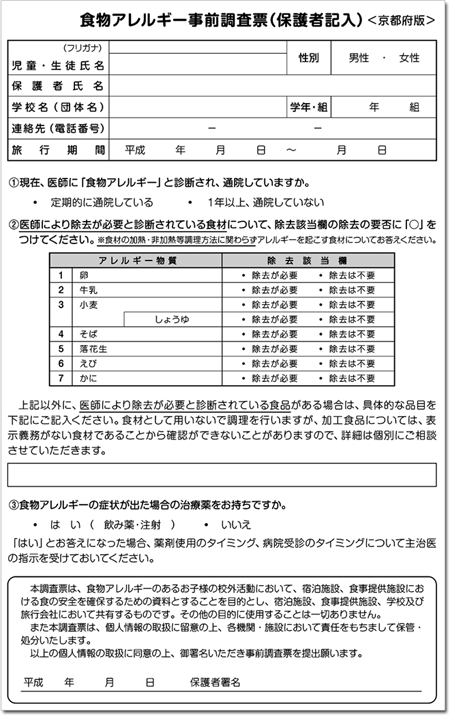
図2 「食物アレルギー事前調査票」の情報の流れ
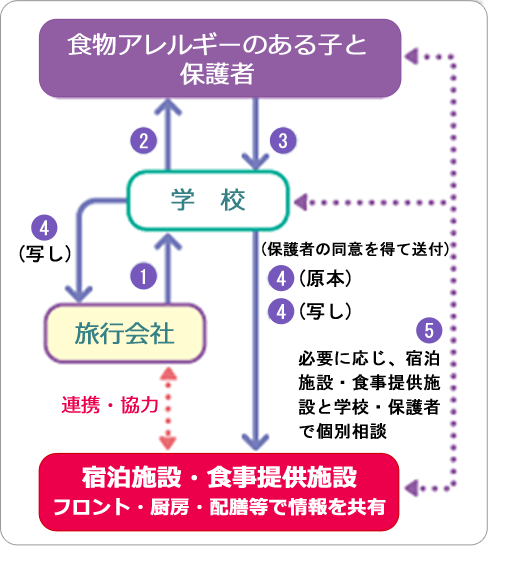
 旅行会社から、京都府に修学旅行等にくる学校へ、事前調査票を提供・依頼
旅行会社から、京都府に修学旅行等にくる学校へ、事前調査票を提供・依頼 学校から、食物アレルギーのある子どもの保護者に事前調査票を配付
学校から、食物アレルギーのある子どもの保護者に事前調査票を配付
(基本的には、学校における健康調査で食物アレルギーのある子どもを対象に事前調査票を配付しますが、入学直後等により把握ができていない場合など学校の状況に応じて全員配布の対応も可) 保護者は、主治医と相談の上で事前調査票を記載し、学校へ提出
保護者は、主治医と相談の上で事前調査票を記載し、学校へ提出 学校は、事前調査票を回収し、修学旅行等の出発が1か月前までに原本を施設に、写しを食事提供施設、旅行会社に送付
学校は、事前調査票を回収し、修学旅行等の出発が1か月前までに原本を施設に、写しを食事提供施設、旅行会社に送付 必要に応じ、宿泊施設・食事提供施設と学校・保護者が具体的な調理内容について相談
必要に応じ、宿泊施設・食事提供施設と学校・保護者が具体的な調理内容について相談
宿泊施設・食事提供施設のフロント、厨房、配膳の担当者で情報共有し、事故防止のために確認に使用
- 前のページへ(安全第一を考え完全除去が対応の基本)
- 特定原材料7品目は「責任をもって除去」
- 次のページへ(どこへでも安心して旅行できる「夢」実現のために)

















