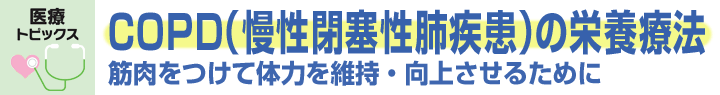![]() すこやかライフNo.49 2017年3月発行
すこやかライフNo.49 2017年3月発行
医療トピックス
COPDは、喫煙などによって肺に炎症が起こり呼吸が苦しくなる病気で、日本ではやせ型の人が多いのが特徴です。やせていることはCOPDに悪影響を及ぼすため、治療では薬物療法に加え、体格や体力を維持するための栄養療法が重要とされています。2016年の診療報酬改定で、やせた人への栄養食事指導に保険点数が付くようになり、病院などで栄養食事指導を受けやすい環境が整ってきました。
そこで今回は、COPDの栄養療法について、秋田大学 大学院 医学系研究科 保健学専攻理学療法学講座 教授 塩谷隆信先生と、駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 教授田中弥生先生にお話をうかがいました。
より詳しくは、次のメニューからご覧ください
- 多くのエネルギーが必要なのに、さまざまな理由で十分な栄養が摂れない
- やせるだけでなく筋肉量が減ることも問題
- 急激な体重の減少はありませんか?
- エネルギー量を増やすポイントは脂質の摂取
- 筋肉量を増やすために必要な栄養素「分岐鎖アミノ酸(BCAA)」
- 栄養療法だけでなく運動も併用して行うことが理想的
お話をうかがった先生
秋田大学 大学院 医学系研究科 保健学専攻 理学療法学講座 教授 塩谷隆信(しおや・たかのぶ)先生

プロフィール
1984年秋田大学大学院医学研究科修了後、同大学医学部附属病院助手。同年7月よりシカゴ大学医学部呼吸器リサーチフェロー、86年秋田大学医学部助手、95年同第二内科講師、97年秋田大学医療技術短期大学教授、99年シカゴ大学医学部文部省在外研究員、2002年秋田大学医学部保健学科理学療法学専攻教授を経て09年から現職。
メッセージ
COPDは、たばこを長期に吸った人によく起こる病気です。COPDでは栄養障害のために全身の筋肉量が減少し生活に支障をきたします。せき、たん、息切れなどで心あたりがある人は、医療機関で呼吸機能検査を受けてみてください。近年、COPDは予防と治療が可能になってきました。新しい吸入薬の治療で症状は軽くなります。さらに、栄養と運動療法による呼吸リハビリテーションを行うことで驚くほど元気になれます。
駒沢女子大学 人間健康学部 健康栄養学科 教授・管理栄養士 田中弥生(たなか・やよい)先生
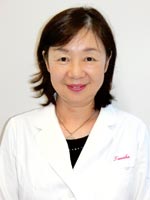
プロフィール
1981年特定医療法人新都市医療研究会君津会南大和病院栄養科入職。91年同栄養科科長、同会南大和老人保健施設栄養科長兼務。2000年同会大和病院グループ栄養科長。04年関東学院大学人間環境学部健康栄養学科非常勤講師、08年駒沢女子短期大学食物栄養科准教授、医療法人新都市医療研究会君津会南大和病院栄養科顧問。09年駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科准教授、10年慶應義塾大学看護学部非常勤講師兼任を経て14年4月から現職。博士(スポーツ医学)。
メッセージ
COPD患者さんは、呼吸苦や膨満感による食欲低下だけでなく、エネルギー代謝亢進による体重減少が起こり低栄養状態に陥りやすくなります。体重が減少すると脂肪だけが減少するのではなく、水分や筋肉もエネルギーとして使われてしまいます。これらを防ぐためには、少量でもエネルギーが高くタンパク質の多い食品を選び、おいしくて食べやすい状態にすることにより体重の維持・増加ができます。
ご協力いただいた先生方
- 市立秋田総合病院リハビリテーション科 技師長 理学療法士 高橋仁美先生
- 市立秋田総合病院中央診療部栄養室 主査 管理栄養士 山田公子先生
- 駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科 助手 管理栄養士 中澤優先生