

すこやかライフNo.49 2017年3月発行
![]() 医療トピックス:COPD(慢性閉塞性肺疾患)の栄養療法
医療トピックス:COPD(慢性閉塞性肺疾患)の栄養療法
栄養療法だけでなく運動も併用して行うことが理想的
COPDの症状を改善し、急激な悪化(増悪)を防ぐためには、食事で体に必要な栄養素を摂るだけでなく、それを筋肉に変えるための運動もあわせて行う必要があります。
栄養食事指導に加え、運動などをトータルに指導してくれるのが「呼吸リハビリテーション」です。COPDの人は、体を動かすと息切れが出るため、動くことを避けてしまいがちですが、呼吸リハビリテーションで行われる運動療法は、今残っている肺の機能を十分に発揮させ、体を動かすことで呼吸を楽にして、筋力の衰えを防ぐという重要な役割を持っています。
呼吸リハビリテーションでは、栄養食事指導・運動療法のほかにもたんの出し方や呼吸の仕方など、病状を安定させ、呼吸を楽にする方法も指導しています。
呼吸リハビリテーションを行っている施設は、下記呼吸リハビリテーション施設の検索のサイトで検索することができます。まだ栄養食事指導や運動療法を受けたことがない、呼吸リハビリテーションを受けてみたいという人は、主治医と相談してみましょう。


市立秋田総合病院での
栄養食事指導、呼吸リハビリテーションの様子
呼吸リハビリテーション施設の検索
一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
http://www.jsrcr.jp/modules/shisetsu/一般社団法人日本呼吸ケア・リハビリテーション学会のホームページ
(外部サイトへ移動します)
家庭でできるCOPD体操
市立秋田総合病院で行われている運動の一部をご紹介します。無理のない範囲で、自宅で取り組んでみましょう。
有酸素運動:椅子歩行
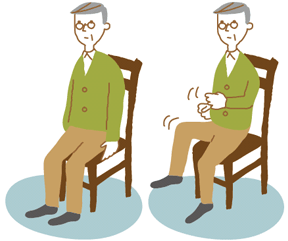
- 椅子に浅めに腰かける。
- ひじを曲げ、腕をふりながら足踏みをする。
筋力強化運動:足の組み力入れ
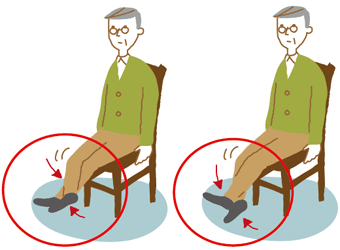
- 椅子のふちを手で握り、足首のところで左右の足を交差させる。
- 下の足はひざを伸ばして足を上げ、上の足はひざを曲げて足を下げ、足同士でお互いに力を入れる。
- 口をすぼめて6秒間力を入れたまま、その状態を保つ。
- 足の交互を逆にして左右10回ずつを目標にしましょう。
上の足は下に、下の足は上に向けて力を入れる。
ストレッチ:胸の筋肉伸ばし
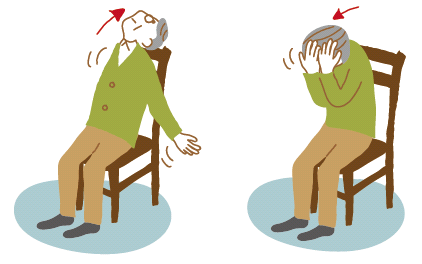
- 椅子に座ったまま頭を後ろにそらし、両手を後ろに引いて、胸を十分に広げながら、鼻から息を吸う。
- 息を吸いきったら、両ひじを曲げて胸の前にもっていく。左右のひじとひじ、手の小指と小指を合わせるようにして、頭を前に曲げ、息を吐きながら背中を丸める。
- 5回繰り返す。
- (注)COPDの人のための家庭でできる運動療法については、すこやかライフ42号「現場レポート」でも詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
トピックス
太っているCOPDの患者さんも増えています!
日本人のCOPD患者さんは、依然としてやせ型の人が多いのが現状ですが、食生活の欧米化などにともない、肥満のCOPD患者さんが少しずつ増えています。
体重が重いからといって体に筋肉がついているわけではないので、肥満のCOPD患者さんでも、放っておくと「やせるだけでなく筋肉量が減ることも問題」で紹介した「サルコペニア」の状態に陥り、身体活動量が低下してしまいます(「サルコペニア肥満注1」とも呼ばれます)。
また、内臓脂肪の蓄積によって横隔膜の動きが悪くなるため肺がうまく広がらず、二酸化炭素が体の中にたまりやすくなります。すると、呼吸困難感が増強し、さらに活動が制限されることにつながります。
内臓脂肪型肥満によって、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を合併するおそれもあります。
肥満のCOPD患者さんは、脂肪を筋肉に置き換えながら、体重を標準体重に近づけていく必要があります。医師や管理栄養士と相談しながら、適切な食事制限と適度な運動を継続していくようにしましょう。
- (注1)サルコペニア肥満について詳しくは、「基礎用語(PDF:1.68MB)
 すこやかライフ49号別添:PDF」をご覧ください。
すこやかライフ49号別添:PDF」をご覧ください。
- 前のページへ(筋肉量を増やすために必要な栄養素「分岐鎖アミノ酸(BCAA)」)
- 栄養療法だけでなく運動も併用して行うことが理想的
- 医療トピックスコーナートップに戻る

















