

すこやかライフNo.45 2015年3月発行
![]() 医療トピックス:知っておきたい 食物アレルギーの診断と検査の方法
医療トピックス:知っておきたい 食物アレルギーの診断と検査の方法
食べられるようになっているか見直すことが大事
乳児から幼児早期の即時型食物アレルギーは、成長とともに症状が出なくなり、原因食物を食べられるようになる耐性獲得(アウトグロー)しやすい病気です。一般に、鶏卵、牛乳、小麦、大豆は耐性獲得しやすい食物と考えられています。
そのため、原因食物が確定し、除去の程度が決定しても、いつまでもそのままの除去を続けるのではなく、半年から1年ごとに繰り返し検査を受け、原因食物を食べられるようになっているか、見直すことがとても大切です。
一度の診断でいつまでも原因食物の除去を続けるのは、保護者の負担にもなりますし、何よりも子どものQOL低下や豊かな食生活の妨げになってしまいます。とくに入園・入学など集団生活を始める際には検査を受け、食べられるものを見直すようにしましょう。
●食物アレルギーの有病率(年齢別)
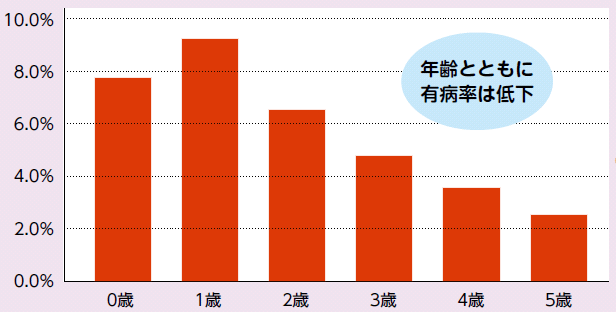
「保育所における食物アレルギーに関する全国調査」(日本保育園保健協議会、平成21年)から引用
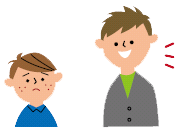
コラム : 食物アレルギーの経口免疫療法について
食物アレルギーの原因である食物が、少しでも食べられるようであれば積極的に食べて、徐々に食べる量を増やしていく「経口免疫療法」という治療法があります。しかし、この治療法は現時点では専門医により研究的に行われている治療法であり、“食物アレルギー診療ガイドライン2012(2011年日本小児アレルギー学会食物アレルギー委員会作成)”でも「一般診療の場において行うことは推奨しない」とされています。
経口免疫療法については、アレルギーに精通した専門の医師に相談してください。
- 前のページへ(必要最小限の除去を実践するために)
- 食べられるようになっているか見直すことが大事
- 医療トピックスコーナートップに戻る

















