

すこやかライフNo.47 2016年3月発行
![]() 現場レポート:ぜん息児へのPM2.5の影響と予防策を知ろう
現場レポート:ぜん息児へのPM2.5の影響と予防策を知ろう
直径は髪の毛の太さの30分の1 肺の奥まで達するPM2.5
大気中に漂う細かい粒子の中で、直径が10㎛(マイクロメートル以下㎛と表記)以下のものを浮遊粒子状物質(SPM)と呼びます。SPMはさらに、直径2.5㎛より大きく10㎛以下の粗大粒子であるPM10と、直径2.5㎛以下の微小粒子であるPM2.5に分けられます(資料1PM2.5の大きさについて)。髪の毛の太さの30分の1以下と非常に小さいPM2.5は、吸い込むと肺の奥まで達し、物理的に気道に刺激を加えたり抗原を引き付けたりする結果、アレルギー反応を起こすと考えられています。
またその構成成分は、自動車からの排気ガス、火力発電所や焼却炉などからの煤煙といった汚染物質が大半を占めるため、そのことでも悪影響を及ぼします。たとえばディーゼルエンジンの排出ガスに含まれるPM2.5には、アレルギー反応を増幅させる性質があるといわれています。
PM2.5とよく混同される黄砂にはさまざまな大きさの粒子があり、2.5㎛以下の粒子はPM2.5に分類されます。
黄砂は、アジア大陸内陸部の砂漠から舞い上がった時点では、土壌鉱物や土壌に含まれる細菌・真菌類で構成され、大きさもほとんどが10㎛以上です。
しかし、飛来中に工業地帯を通ることで、さまざまな汚染物質を帯び、日本に達するころには粒子も小さくなり1~10㎛が中心となります。春先や秋口に黄砂飛来とともにPM2.5の濃度が上昇傾向になるのは、そのためです。
資料1 PM2.5の大きさについて
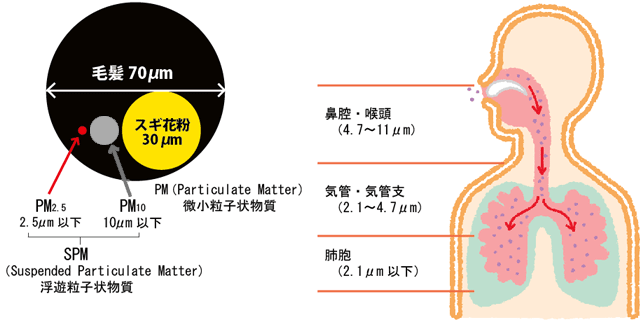
直径が2.5㎛以下のPM2.5は、髪の毛の太さの約30分の1以下と非常に小さいため、細い気管支や肺の奥(肺胞)にまで達します。
- 現場レポートコーナートップに戻る
- 直径は髪の毛の太さの30分の1 肺の奥まで達するPM2.5
- 次のページへ(屋内で発生するPM2.5にも注意が必要)

















