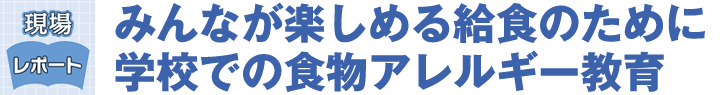![]() すこやかライフNo.53 2019年3月発行
すこやかライフNo.53 2019年3月発行
現場レポート
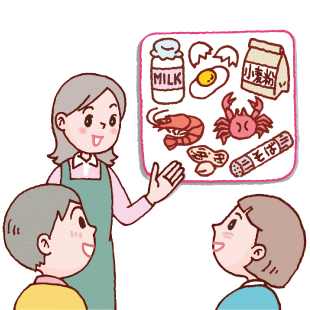
食物アレルギーのある児童生徒の数は年々増加しており、給食や調理実習など、学校生活の中で、適切な配慮が必要な場面が増えてきています。
こうしたなかで食物アレルギーのある児童生徒が安全で楽しい学校生活を送るためには、周囲の児童生徒も食物アレルギーを理解し、助け合うことが大切です。
そこで今回は、学校での食物アレルギー教育について、3つの取り組み事例を紹介します。
より詳しくは、次のメニューからご覧ください
- 事例① 墨田区立曳舟小学校 〔東京都〕
- 事例② ひたちなか市立市毛小学校 〔茨城県〕
- 事例③ 尾張旭市教育委員会 〔愛知県〕
- 7大アレルゲンを使わない人気の給食メニュー
- 付録(No.53)アレルゲンを使わない人気の給食メニューと簡単おやつのレシピ ダウンロード(PDF:733KB)

お話をうかがった先生
うりすクリニック名誉院長/尾張東部アレルギー研究所所長 宇理須 厚雄(うりす・あつお)先生
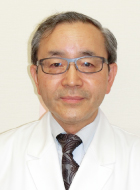
プロフィール
1974年名古屋大学医学部卒業。米国食品医薬品局(FDA)留学、名古屋大学医学部助手、藤田保健衛生大学(現・藤田医科大学)助教授、同大学坂文種報徳會病院(現・藤田医科大学ばんたね病院)小児科教授などを経て、2016年、愛知県尾張旭市に「うりすクリニック」を開業。藤田医科大学客員教授も務める。
総評 「食の楽しみ」に向けた取り組みの広がりを
食物アレルギーのある子どもにとって、代替食や弁当持参といった「人と違うこと」は、時に大きなストレスになることがあります。また、周囲の子どもは、その違いを見つけ、悪意なく心ない言葉をかけてしまうことがあるので、学校教育においては、違いを理解し、認め合う姿勢を教えることが重要です。
学校や世の中には、食物アレルギーだけでなく、腎臓病や糖尿病などさまざまな人が、各々に合った食事をとることで健康を守っています。
この事実を、子どもたちにきちんと教えることが大事です。教育関係者の方々には、こうした教育を粘り強く続けていただきたいところです。また、給食の提供に当たっては、安全の確保が第一ですが、それと併せて「楽しく食べること」も追求していただきたいと思います。
「児童生徒全員が楽しめる給食」に向けた取り組みの広がりが、期待されます。