

すこやかライフNo.42 2013年9月発行
![]() 特集 長引くせきにご用心!からだが発する「危険サイン」を見逃さない!
特集 長引くせきにご用心!からだが発する「危険サイン」を見逃さない!
長引くせきの原因はなに?
せきの原因はさまざま!
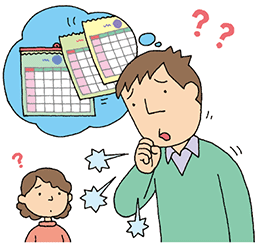
せきが長引く場合、必ず何らかの病気が隠れています。肺がんや結核などの重い病気が原因となっている場合もありますので、まずはそのような重い病気がないか、胸部X 線検査により確認する必要があります。
もし異常がない場合には、ぜん鳴があるかないかで、疑われる病気が変わってきます。
ぜん鳴がある場合にもっとも考えられるのは、ぜん息です。また中高年以上ではCOPDも原因として考えられます。
ぜん鳴がない場合、とくに多い原因が、せきぜん息です。成人の長引くせき(8週間以上)の原因として、およそ半数を占めているといわれています。せきぜん息は、せきだけを症状とするぜん息と考えられています。
このほか、鼻の病気である慢性副鼻腔炎(※)にともない気管支炎が併発する副鼻腔気管支症候群や後鼻漏、呼吸器とは関係ないように思える胃食道逆流症、百日咳やマイコプラズマなどの感染症によるもの、とくに原因のはっきりしない心因性のせきなど、下の図のようにさまざまな原因が考えられます。
※慢性副鼻腔炎については、すこやかライフ37号の特集「ご存知ですか? ぜん息と鼻炎の関係」で紹介しています。(詳しくはこちら)
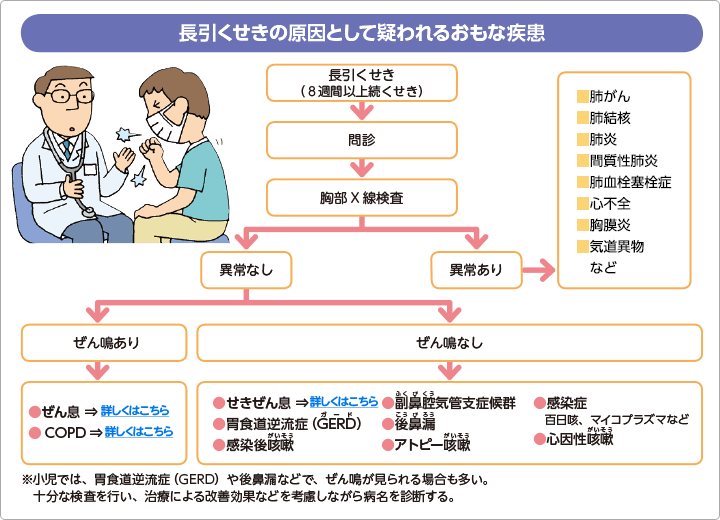
せきが8週間以上続く場合は要注意!
「長引くせきが問題」といっても、どのくらいせきが続いたら「長引くせき」とされ、問題となるのでしょうか?
一般的に、かぜやインフルエンザなどの感染症によるせきは、徐々に軽くなり、2~3週間すれば次第に治まるものです。ところが、かぜが原因で3~4週間以上せきが続くことは少なく、とくに8週間続く場合は原因となる病気が隠れていると考えねばなりません。
下の図のように、次第に治まる急性のせきの場合、多くは気管支や肺などの呼吸器の感染症が原因となります。しかし、せきが続く期間が長くなればなるほど、感染症が原因であることが少なくなっていきます。8週間以上続く場合は「慢性のせき」とされ、感染症以外が原因であることがほとんどで、異なる対処が必要となります。
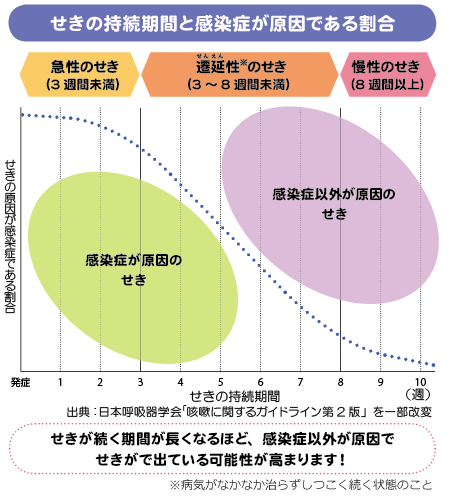
湿ったせき? それとも乾いたせき?どんなせきが出ている?
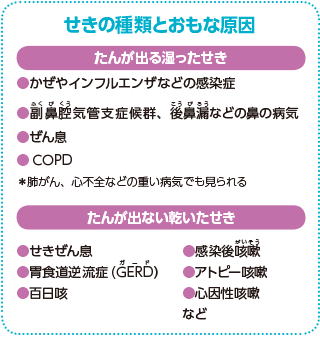
せきは、「たん」をともなうかどうかによってもタイプが異なります。粘り気の強いたんをともなう「湿ったせき」タイプと、たんがないか、出たとしても少量で粘り気がない「乾いたせき」タイプの2 種類です。
湿ったせきの原因となるのは、かぜやインフルエンザなど細菌やウイルスによる感染症が多く、長引いている場合は、鼻の病気( 副鼻腔気管支症候群、後鼻漏など)や、ぜん息、COPDが原因となっていることもあります。
一方、乾いたせきの原因としては、せきぜん息、アトピー咳嗽、百日咳、胃食道逆流症(GERD)、心因性のせきなどがあげられます。
長引くせきの原因をはっきりさせるために、せきの期間とタイプをきちんと医師に伝えることが重要です。

















