

すこやかライフNo.47 2016年3月発行
![]() 特集:小児ぜん息・COPD 検査結果の活用法を知ろう
特集:小児ぜん息・COPD 検査結果の活用法を知ろう
呼吸機能検査
診断確定や経過観察のために行われる重要な検査
- 目的:空気の通り道の広がりを調べる
- COPDを診断するためには呼吸機能検査が欠かせません。ぜん息で行われる呼吸機能検査(小児ぜん息)と同様の検査ですが、COPDではとくに、下記の結果に注目します。最近では、「肺年齢」の検査とも呼ばれます。
COPDの診断基準は、「気管支拡張薬吸入後の呼吸機能検査で1秒率が70%未満」と決められているため、診断するには、気管支拡張薬の吸入前後で2回、呼吸機能検査を行う必要があります。COPDと似ている、ぜん息との鑑別という意味でもこの検査が重要です。ぜん息もCOPDも空気の通り道である気道が狭くなり、空気を吐き出す力が弱くなる病気です。ぜん息の場合は気管支拡張薬を吸入するとすぐに気道が広がります。しかし、COPDの場合は気管支拡張薬の効果がすぐには現れず2回の検査で数値がそれほど変わりません。
診断ではなく、診療の際の病状把握や重症度の判定には、気管支拡張薬を吸入せずに呼吸機能検査を行って、下のような結果の数値で確認します。
結果が出たらここをチェック
とくに注目したいのが「1秒率(FEV1.0%)」の値です。
COPDで肺の弾力性が失われ、気道が狭くなっていると、息を吐き出すのに時間がかかります。
息を吐き出してから最初の1秒間で、全体の70%未満しか吐き出せない場合は、COPDの疑いが高くなります。
肺年齢
最近では、呼吸機能検査の値をわかりやすい「肺年齢」に置き換えて表示してくれる機器もあります。
肺年齢とは、同性同年代で同じ身長の人の平均数値と比べて、それより上か下かを「年齢」に置き換えたものです。実年齢よりも肺年齢が上であれば、COPDの疑いが高いといえます。
- 呼吸機能検査で測定されるこのほかの項目については、すこやかライフ43号別添「基礎用語(PDF:176KB)」
 (すこやかライフ43号別添:PDF)で詳しく紹介しています。ご参照ください。
(すこやかライフ43号別添:PDF)で詳しく紹介しています。ご参照ください。
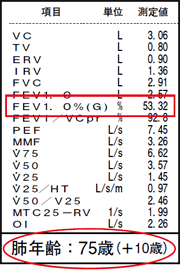
スパイロメータから打ち出される結果レシートの例
検査を受けて行動をチェンジ!
定期的な検査で経過を知ることが大切
COPDと診断されたら、禁煙することが大前提です。肺機能は加齢に伴い低下していきますが、喫煙者では肺機能の低下がより早く進行します。しかし、禁煙することで、その後の肺機能の低下具合はたばこを吸わない人とほぼ同じになります。
また、経過観察のために半年に1回程度は、呼吸機能検査を受けましょう。1秒率は、気道がどのくらい狭くなっているか、薬の効果は出ているかなどの経過観察にも有用だからです。
医師に指示されたとおりに薬を吸入しているのに、呼吸機能検査の数字が改善されないという場合、薬の吸入方法が効果的でないかもしれません。医師や薬剤師に吸入方法をチェックしてもらい、見直すことも大切です。
COPDといわれているけれど、呼吸機能検査を受けたことがないという人は、ぜひ一度、呼吸機能検査を受けましょう。
- 前のページへ(COPD(慢性閉塞性肺疾患)の検査)
- 呼吸機能検査(COPD)
- 次のページへ(画像検査(COPD))

















