

すこやかライフNo.48 2016年9月発行
![]() 特集:上手なサポートで薬嫌いを克服しよう
特集:上手なサポートで薬嫌いを克服しよう
保護者とのコミュニケーション不足などが原因の場合
ひとりで薬を飲み続けることは大変
いつでも見守っているサインを
ぜん息の薬のように定期的な服用、吸入が必要な場合、保護者はつい子どもに任せっきりにしてしまったり、飲まないことを叱ったりしてしまいがちになります。しかし、子どもは「飲みなさい、吸入しなさい」と放っておかれるだけでは、なかなか続けることができません。
実は、保護者が自分に注意を向けてくれないことが、薬嫌いの原因になっていることがよくあります。まずは保護者自身が、ぜん息の治療は「自分でできるんだ!」という子どもの自己効力感を育むよい機会だととらえましょう。そして、薬を飲んだり、吸入したことを見守り、ほめることが、子どもの意欲向上につながることを覚えておきましょう。家族みんなでサポートすること、サポートされていることを子どもに理解させることも大切です。
また、家庭環境や兄弟との関係、通っている園・学校の環境などにも、子どもが薬嫌いになる原因が隠れていることがあります。事例を参考に、子どもの薬嫌いの原因がどこにあるのか探ってみましょう。
事例1 お母さん、肩の力を抜いて
子どもが病気のとき、親が「自分ががんばらないと」と思ってしまうのは当然のことですが、いつもいつも薬のことしか言わない、飲まないと病気が治らないと言われ続けると、子どもは薬自体が嫌いになってしまいます。
嫌がるときには、過度に干渉しないのもひとつの手です。「わかった。じゃあ飲まなくていいよ」といったん引いてみると、子どもは「あれ? いつもと違う」と思い、自分から「飲む」と 言い出すこともあります。子どもとのやりとりを楽しむくらいの余裕を持つことも大切です。
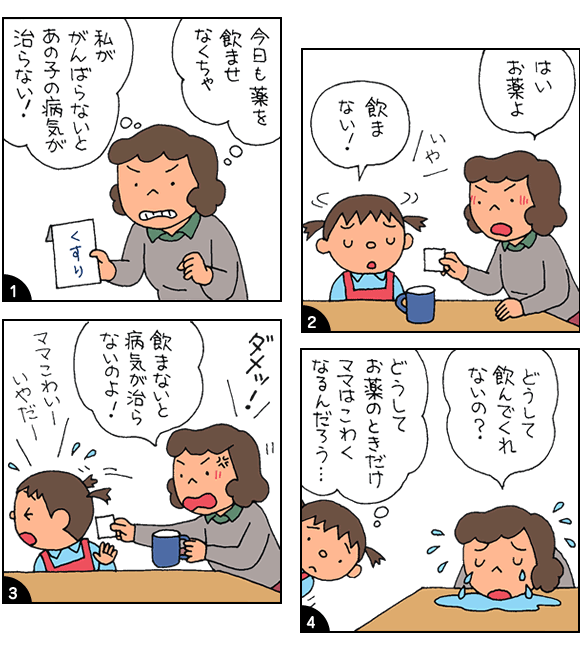
事例2 かまってほしくて…
薬を飲まないで怒られることが、子どもにとっては「親にかまってもらえる」という認識になっていることがあります。
これを「飲めばほめてもらえる、かまってもらえる」という認識に変えましょう。「今日もがんばったね、えらいね」と毎回一言かけるだけでも、子どもの意欲は変わります。
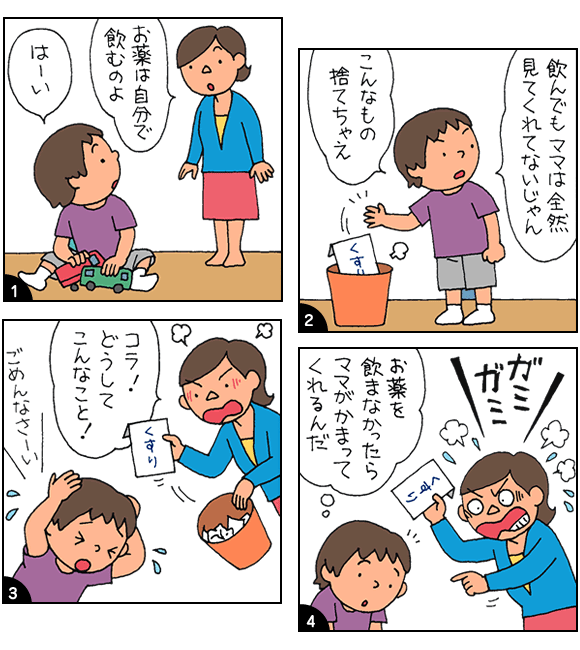
また、兄弟で治療しているときには、上の子どもにも注意を払いましょう。たとえば吸入が終わったら、少しでも1対1で遊んであげると、「ちゃんとやれば、遊んでもらえる」という認識 にすることができます。
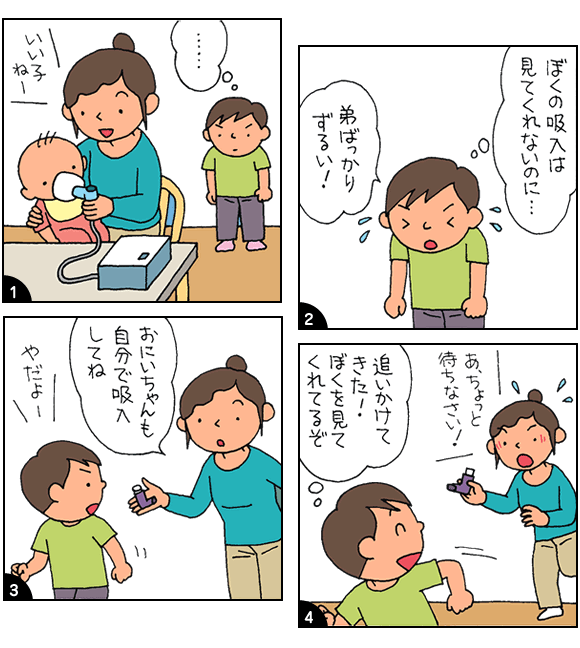
「薬を飲んだらカレンダーやお薬手帳にシールを貼ろうね」と約束し、それを確認することも有効です。シールを貼ることが楽しみや達成感になり、薬を続ける動機につながります。

すずらん調剤薬局で使用しているシール。
自分で動物を元気にすることができる。
事例3 幼稚園ではいい子なのに…
幼稚園や保育所、学校では薬を飲むけれども、家ではまったく飲まないという場合、〈事例2〉と同じような理由が隠れていることがあります。
幼稚園や学校で薬を飲むと、先生や友達がほめてくれる、ヒーローになれることが子どもを満足させ、薬を飲む動機につながるのです。
ほめる一言や、飲んだら一緒に遊ぶなど、家でも薬を飲むといいことがある、という意識を持たせることが大切です。
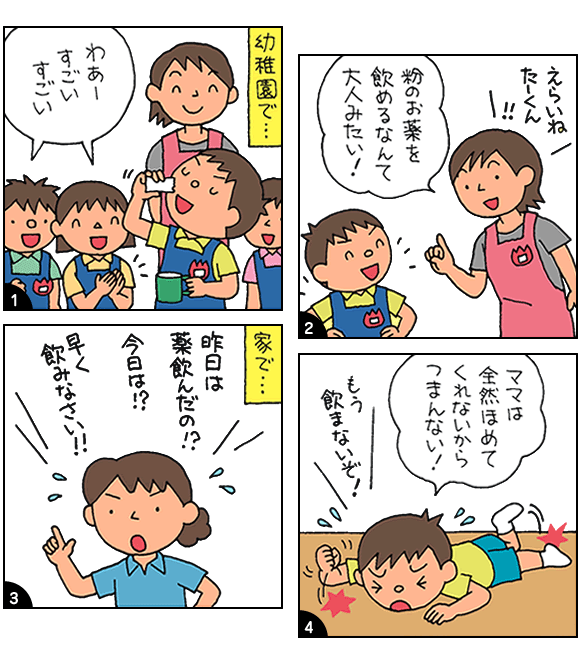
服薬・吸入を嫌がるとき、こんな方法もあります
最近は、祖父母との同居も少なくなり、誰かが薬を飲む光景を子どもが見る機会が少なくなってきました。そのため、子どもが「どうして私だけ、薬を飲まなくちゃいけないの?」「どうして私だけ、面倒な吸入をしなくちゃいけないの?」と思ってしまうこともあります。
- トレーナー(注)を使って兄弟で一緒に吸入の練習をさせてみる。
- 保護者が薬を飲むところを見せる。
- 一緒に薬に似たものを飲む。
こうすることで「同じことを一緒にやる」という気持ちにすることができます。
(注)正しい吸入方法を練習するための薬剤が入っていない練習器。
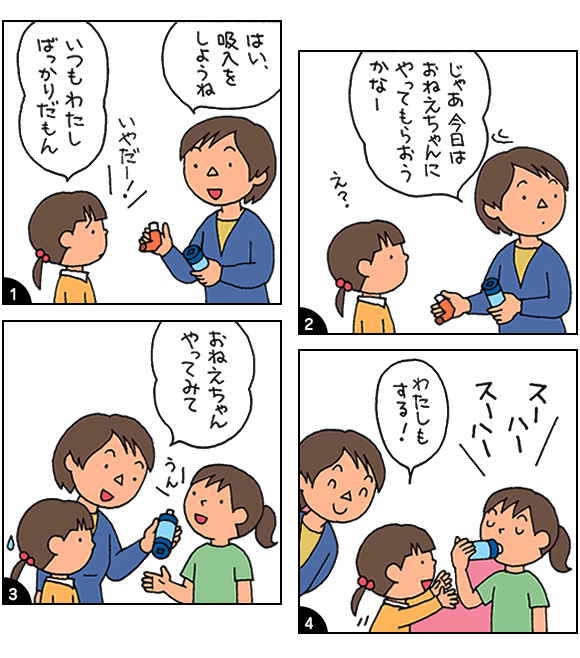
- 前のページへ(病気が原因の場合)
- 保護者とのコミュニケーション不足などが原因の場合
- 次のページへ(子どもが薬を飲まなくなるのはよくあること目標を持って取り組みましょう)

















