

すこやかライフNo.50 2017年10月発行
![]() 特集:「ぜん息・COPD Q&A」
特集:「ぜん息・COPD Q&A」
Q2.吸入ステロイド薬をはじめとする長期管理薬は、いつまで続けなければならないのですか。
A.患者さんの状態を総合的にみて、医師の判断で薬の減量や中止をします。―小児ぜん息 橋本光司先生― ―成人ぜん息 金子教宏先生―
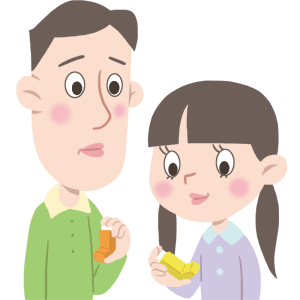 ぜん息は、気道の炎症が原因で、せきやたんなどの症状が起こります。そのため、治療の中心となるのは「気道の炎症を抑える」長期管理薬、主に「吸入ステロイド薬」です。
ぜん息は、気道の炎症が原因で、せきやたんなどの症状が起こります。そのため、治療の中心となるのは「気道の炎症を抑える」長期管理薬、主に「吸入ステロイド薬」です。
長期管理薬をいつ中止するかについては、明確な基準が存在していません。個々の患者さんの年齢、ぜん息の重症度(症状の程度と頻度、治療内容を加味したもの)、今までの入院歴や発作歴、全身性ステロイド薬の使用も含めた治療歴、症状の季節性変動や運動によるぜん息症状の誘発など、各患者さん固有の悪化因子を十分検討したうえで考えるべきだからです。
一般に小児の場合は、症状が出ないコントロール良好な状態が約3か月以上、成人では3か月から6か月以上保てれば、薬の減量(ステップダウン)を考慮します。さらに、必要最少量の薬でコントロール良好な状態が保てれば、中止を試みることがあります。
この際、ピークフロー測定、呼吸機能検査および呼気一酸化窒素検査(呼気NO検査)、可能であれば気道過敏性検査などで、気道の炎症が本当に治まっているかを客観的に評価したうえで、中止するのが望ましい方法です。
ぜん息の検査について
薬の中止後も再燃に注意
注意したいのは、薬を減らしたり、中止できたりしたとしても、何かの拍子で症状が再び出る(再燃する)こともある点です。特にかぜなど呼吸器の感染症により、その危険性が高まります。発作が起こりやすい季節は、薬を継続するのもひとつの方法です。また、小児ぜん息の場合は、残念ながら成人になってから再発する場合もあります。
再燃予防のためダニ、カビ、ペット、たばこ対策などの環境整備、たんれんの継続、再燃時の早期の対処法などを知っておきましょう。また、薬を中止した後も、定期的な呼吸機能検査等を受けることをお勧めします。
5歳以下のお子さんの場合
5歳以下のお子さんでは、ぜん息ではなく感染に伴う「ぜん鳴」注のおそれもあります。その場合、症状が安定したら、早期に薬の減量・中止を考慮することもあります。中止後、症状が再燃したら、ぜん息の治療を再開します。
- (注)
- 気道が狭くなったことで、呼吸によって生じるゼーゼーヒューヒューした音のことを、「ぜん鳴」といいます。
成人ぜん息の患者さんへ
成人ぜん息は完治しにくい病気です。厳しい言い方ですが、「ほぼ、治らない病気」と捉えたほうがよいでしょう。
ただし、「コントロールできる病気」でもあります。薬を使いながら、場合によっては薬を使わなくても、症状が出ないようコントロールし続ければ、健康な人と変わらない生活を送ることができます。
- Q2.吸入ステロイド薬をはじめとする長期管理薬は、いつまで続けなければならないのですか。
- 前のページへ(Q1.ぜん息の場合、ダニ対策は必ずやらなければなりませんか。どの程度までやればいいのですか。)
- 次のページへ(Q3.ステロイド薬の副作用が心配です。)
目次
- Q1.ぜん息の場合、ダニ対策は必ずやらなければなりませんか。どの程度までやればいいのですか。
- Q2.吸入ステロイド薬をはじめとする長期管理薬は、いつまで続けなければならないのですか。
- Q3.ステロイド薬の副作用が心配です。
- Q4.ぜん息は遺伝しますか。
- Q5.園や学校にぜん息のことをどうやって知ってもらえばいいですか。
- Q6.COPDと診断され禁煙するようにいわれました。なぜ禁煙しなければならないのですか。
- Q7.COPDは悪くなる一方と聞きます。最終的には、酸素ボンベが必要になりますか。
- Q8.指示どおりに吸入しているつもりですが、効果が感じられません。本当に薬が効いているのか心配です。
- Q9.病院で先生の前に出ると緊張してうまく話ができません。どうやって自分の症状などを伝えるといいのでしょうか。

















