

すこやかライフNo.53 2019年3月発行
![]() 医療トピックス:ぜん息に影響する鼻の病気―アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎―
医療トピックス:ぜん息に影響する鼻の病気―アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎―
②副鼻腔炎
副鼻腔炎は、副鼻腔と呼ばれる両目の間や額、ほおの下など、鼻のまわりにある空洞に炎症が起こり、膿や分泌物がたまってしまう病気です。蓄膿症(ちくのうしょう)とも呼ばれます。かぜなどの感染症にかかったとき急性の副鼻腔炎が起こることが多くありますが、慢性化することもあります。成人のぜん息患者さんに多くみられますが、小児でも合併していることがあります。
慢性副鼻腔炎は、ぜん息を治りにくくしたり、重症化させたりする大きな要因と考えられています。ぜん息のコントロール状態が悪いときには、副鼻腔炎が合併していないかを調べることも大切です。
- 健康な状態
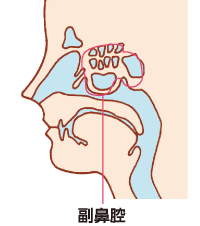
- 副鼻腔炎の状態
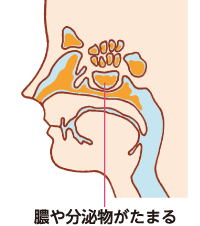
症状
- 嗅覚低下(食事の匂いがわからないなど)
- 鼻づまり、ねばりのある鼻水
- 頭痛、集中力の低下 など
副鼻腔の粘膜にポリープ(鼻茸:はなたけ)ができることが多いのも特徴です。
治療
おもに抗生物質やステロイド薬を使った薬物療法が行われます。
鼻ポリープがある場合には、鼻ポリープを切除する内視鏡を使った手術療法が行われることもあります。
好酸球性副鼻腔炎
とくに成人ぜん息患者さんの場合、気道に好酸球という白血球の一種が増加することがあります。この好酸球が副鼻腔に増え、粘膜が傷ついて起こるのが好酸球性副鼻腔炎です。治療が難しく治りにくいため、副鼻腔炎の症状、とくに嗅覚低下がみられたら、早めに医師に相談し検査や治療を開始しましょう。
また、この好酸球性副鼻腔炎のある患者さんのうち、約半数が非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs:エヌセイズ)に過敏に反応してしまうといわれています。すると、アスピリンをはじめとする解熱鎮痛薬を服用したときに、非常に強いぜん息症状と鼻症状を引き起こすことがあります[アスピリンぜん息(解熱鎮痛薬ぜん息)と呼びます]。解熱鎮痛薬を使用する場合は、必ず医師や薬剤師に確認してください。

















