

すこやかライフNo.51 2018年3月発行
![]() 特集:「小児ぜん息の最新ガイドラインから自己管理のヒントを学ぼう-「コントロール良好」を目指して-」
特集:「小児ぜん息の最新ガイドラインから自己管理のヒントを学ぼう-「コントロール良好」を目指して-」
「コントロール良好」を目指して知っておきたいこと・実践してほしいこと
③定期的な通院で、ぜん息の状態を評価し確認してもらう
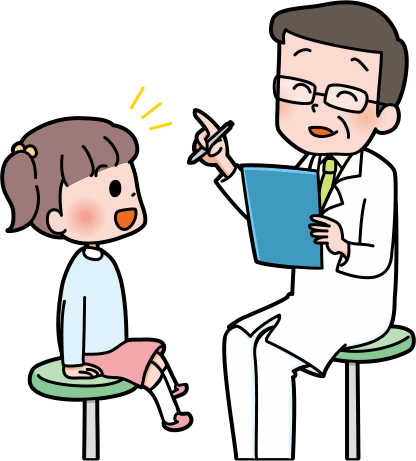 ぜん息の治療では、患者さんの症状に合わせて使う薬の量や種類が選択されます。今回のガイドラインでも、医師は患者さんの症状や重症度、コントロール状態に合わせて「治療ステップ(重症度に合わせた薬の量や種類)」を選択することが推奨されています。
ぜん息の治療では、患者さんの症状に合わせて使う薬の量や種類が選択されます。今回のガイドラインでも、医師は患者さんの症状や重症度、コントロール状態に合わせて「治療ステップ(重症度に合わせた薬の量や種類)」を選択することが推奨されています。
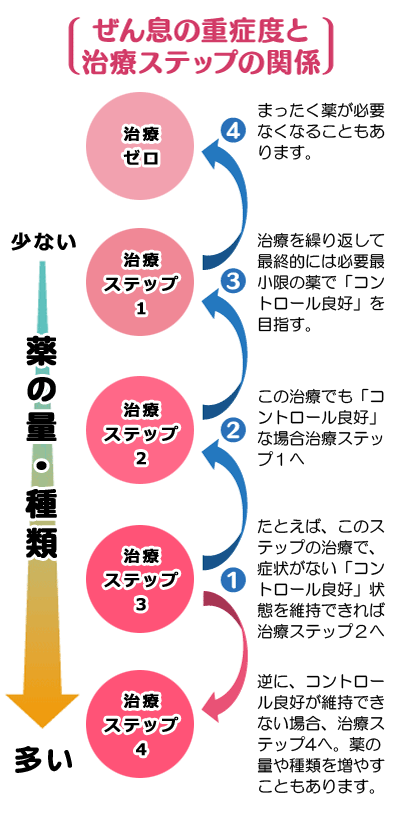
治療ステップは、治療ステップ1から4までの4段階にわかれています。
治療ステップの1から4へと数字が大きくなると、治療に必要な薬の量や種類が増えていきます。たとえば現在受けている治療が、治療ステップ3の患者さんの場合、治療を続けてコントロール良好な状態が維持できれば、医師は薬の量や種類を減らしたり、薬を中止したりすることを考え、治療ステップ2へ移ります。これを繰り返し、最終的にはまったく薬を使わなくてもコントロール良好を維持できることを目標にします。
たとえば、現在「治療ステップ3」(ぜん息の重症度と治療ステップの関係図①)の患者さんが治療を続け、コントロール良好な状態が維持できた場合、医師は薬の量や種類を減らしたり、薬を中止したりすることを考えます(②治療ステップ2)。最終的には、必要最小限の薬(③治療ステップ1)で、もしくはまったく薬を使わなくても(④治療ゼロ)コントロール良好を維持することが目標です。
もし、定期的に呼吸機能検査などを受けずに、同じ薬を長年使っているという場合は、いまのぜん息の状態を医師に再評価してもらいましょう。薬は足りているか、もしくは過剰ではないかなどを確認してもらうことが必要です。呼吸機能検査は、定期的に受けることが望まれます。
また、患者さんも治療を理解して、主体的に自己管理を行うという意識を持ち、診察の際にはいまの状態を医師に詳しく伝えましょう。冒頭のコントロール状態のチェックテストを持参するのもよいでしょう。ガイドラインに書かれている標準治療は、あくまでも指針です。ガイドラインという科学的な根拠をもとに、医師と患者さんが話し合って治療方針を決定していくことが、その患者さんに合った治療につながります。
- 「コントロール良好」を目指して知っておきたいこと・実践してほしいこと③定期的な通院で、ぜん息の状態を評価し確認してもらう
- 「コントロール良好」を目指して知っておきたいこと・実践してほしいこと②悪化因子への対処をする前のページへ
- 次のページへ(「コントロール良好」を目指して知っておきたいこと・実践してほしいこと④ぜん息発作の見分け方、対処ができるようにしておく)
目次
- コントロール良好を目指すために
- まずは、今のコントロール状態をチェックしてみましょう!
- 「コントロール良好」を目指して知っておきたいこと・実践してほしいこと
- ガイドラインからのエッセンス

















