
いすみライフスタイル研究所理事長 髙原和江さん(左)と副理事長 江崎亮さん(右)
活動の一つである有機畑の「いすみっこ給食野菜畑」で
地域に寄り添いながら取り組む、市民の環境意識向上を促す一体型環境保全
「いすみ市の自然環境が魅力的であること。それが私たちの活動の全ての前提でした。」そう語るのは、いすみライフスタイル研究所・副理事長の江崎亮さん。いすみ市の自然環境に魅せられ、熊本県から移住してきた根っからのいすみファンです。
千葉県のいすみ市は、県最大の流域面積を持ち、生息している生物の多様性では日本でも有数の夷隅川が市内を横断し、その河口から沿海には「器械根」という広大な岩礁地帯が広がります。夷隅川の流域、および沿海では農業、漁業が営まれる、里山と里海がコンパクトにまとまった地域です。
いすみライフスタイル研究所は、2008年度からNPOとして活動を始め、移住定住支援と情報発信の活動をいすみ市から受託していました。その活動の中で、いすみ地域の魅力の多くが自然環境に由来することに気づき、自然環境の保全に活動を広げたのです。
「農林地の荒廃と生物相の劣化、化学物質による水質の汚染などへの対応について、いすみ市では大きな地域課題になっていなかったため、市民の環境意識も高くありませんでした。そこで、自然環境の保全のために、『食』の安心・安全、農漁業の持続可能性をライフスタイルの中から見直していくことで、市民の環境への意識を啓発していこうと考えたのです。まちづくり・くらしづくりと環境保全活動を行うための効果的な価値観として、『食と農と環境をつなぐ』*というキーワードを取り入れました。」(江崎さん)
行政や地域のステークホルダーと協働した、環境保全活動とつながったまちづくりが始まりました。
*出典 : 蔦屋栄一『食と農と環境をつなぐ』 全国農業会議所、2008



いすみライフスタイル研究所の取り組みは、市民の意識変革につながる地域イベントや情報発信を、行政や農漁業のステークホルダーと協働して推進することでした。
いすみ市では米どころということもあり、学校給食に有機米が導入されました。このことをきっかけに、2018年に開催された東アジア地域での環境保全型農業の振興を促す農業国際会議 「ICEBA2018 in いすみ」に様々な形で協力・参画しました。また市内の小学校では2016年度より小学5年生を対象とした総合学習「教育ファーム」がスタート。ICEBAで協働体制が強化されたことにより、2019年度にこの「教育ファーム」の副読本として、「いすみの田んぼと里山と生物多様性」の制作に協力し、市内の小学校のほかICEBAで交流を深めた韓国の方々にも配布しました。
その他、パドルに乗って川掃除を行うリバークリーン、市内の中学生が参加するビーチクリーンといった環境活動や、有機畑での食育イベント、ボードゲームを使った獣害対策勉強会などの参加型環境教育を実施したことなどにより、地域の環境や有機農業への理解・関心が深まりました。
「食育イベントでは子供達が畑に入って、土や野菜はもちろんのこと、そこに生きる虫に触れたり、リバークリーンでは川に飛込んで遊ぶなど、自然との一体感を味わえるイベントができたと思います。『ICEBA 2018 inいすみ』の中で実施した田んぼの生き物調査や紙芝居づくりでも、子供達は楽しんで参加してくれました。」(江崎さん)
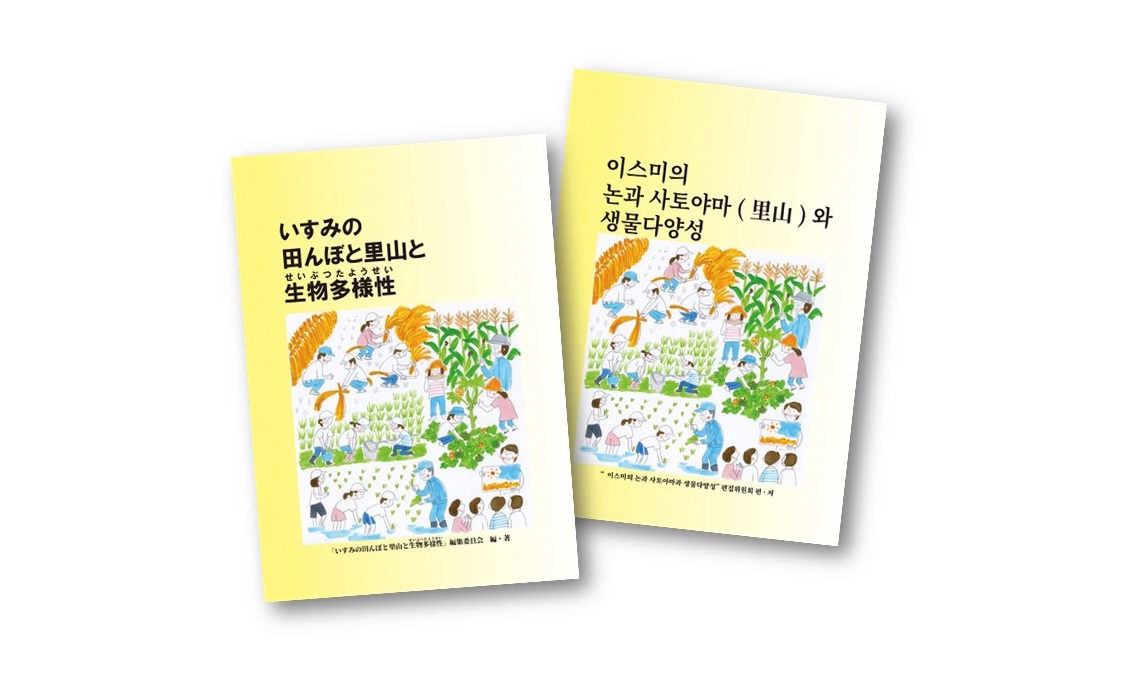


たとえどんな素晴らしいビジョンがあっても、私たち単独では実現することはできません。「地域社会の流れに寄り添いながら、地域の課題解決に取り組むこと」「こちらの考えを一方的に押し付けるのではなく、相手の考えや立場を尊重しながら、辛抱強くすり合わせること」これがビジョン達成の鍵になりました。
たとえばいすみ市では、2012年に「自然と共生する里づくり連絡協議会」が設立され、2017年には学校給食用米を全量有機米にしました。こうした地域の動きに寄り添い、協力しながら課題に取り組んできた結果、「ICEBA2018 inいすみ」の開催や教育ファームの副読本の制作が実現できたのです。
また地域内外の多くの人に活動を知ってもらうため、ニュースレターやパネルの制作、WEBでのコンテンツ化など、できるだけ多くの場面で情報発信することを心掛けました。
地道な努力や情報発信による理解の促進、課題解決に向けた連携体制の構築が、地域ぐるみの活動につながったと思います。(江崎さん)
食と農と環境をつなぎ、地域の自然環境を保全する活動は、今後どのように発展していくのでしょう。いすみライスフスタイル研究所理事長の髙原和江さんはこう語ってくれました。
「この地域には、自然環境が豊かな夷隅川の他に、多様な生物を育む水田もたくさん存在します。それらを保全していくことが、『食』の安心・安全と、地元の農業・漁業の持続可能性につながります。そのために地域で『食の有機化』などに取り組んでいる農家や生産者・流通業者・市民をネットワークし、お互いに支え合う、ゆるやかなつながりを作ることが当面の目標です。」
いすみライフスタイル研究所では、こうしたネットワークづくりから、有機食材とそれを活かしたイベントやコンテンツの作成と地域内外への発信を検討しています。有機農業を重視した地域づくりにより、生き物や自然の力を借りた、食と農業と環境がつながった「地域循環共生圏」のプラットフォームをつくることが、この事業のビジョンです。
「SDGsの開発目標の中にも、『11. 住み続けられるまちづくりを』というテーマがあります。地域の魅力づくりを進めることで、みんなが住み続けたくなる食の安全・安心や自然環境の保全につながっていく。そんな持続可能な地域社会がつくれるとうれしいです。」(江崎さん)
自然環境の保全から、自然や生き物の力を借りた地域循環共生圏の創生へ。いすみライフスタイル研究所は、これからも地域に寄り添い、自然という地域の魅力を生かした持続可能なまちづくりに取り組みます。

地域との協働で行った参加型環境教育や情報発信により、地域住民の環境意識の変化につながりました。また、地域の環境を保全・維持していく人を増やす活動が、子供達の体験学習などESD*の視点で展開されているのも素晴らしいと思います。地域内外で協働体制をさらに強化し、いすみの豊かな自然を生かした地域循環共生圏を構築していくことにも期待が高まります。
*持続可能な社会を目指す教育
 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード