



地球環境基金便り No.53 (2022年9月発行)


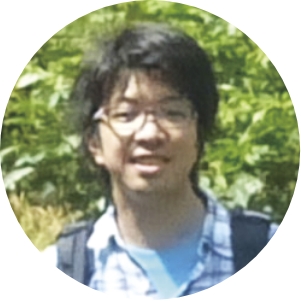

地域の人々とより良い未来を考え、自主性と主体性を養いながら持続可能なまちづくりを進めています。企業や団体との協働を促進し、おのおのの特性を引き出し活かし合う「まちづくりのトータルコーディネーター」としても課題解決に取り組んでいます。
ラオスでは人口の約8割が農業に従事し、自然に寄り添う暮らしを営んでいます。その一方で、急速な開発が進み森林面積や水源が減少、都市化によるごみ問題や環境汚染が深刻化しています。
私たちの活動の始まりは給水および衛生設備事業でしたが、安定的な水の供給には水資源の森を守ることが急務だったため植林事業を展開。村人へ植林技術を伝えるとともに、中学校などで環境意識を高めるワークショップや苗木育成活動、果樹栽培を行いました。その活動を通じて感じたのが、次世代を育成する重要性でした。また、興味深いことに、親世代にはなかなか伝わらないことでも、子どもを通すと伝わることを知りました。そこで、コミュニティを変えていくうえで、学校での活動がとても効果的だと考え、2018年度から学校での環境教育定着を目指して、本活動を始めました。
環境教育プログラムの開発・実施を重ねて5年目。現在、教育局が認証する環境に配慮した学校「グリーンスクール」認定校は2校で、10校の認定を目指してプログラムの改良を進めています。グリーンスクール認証は、教員たちのモチベーション向上につながっていて、自発的に環境保全活動を始める学校も出てきました。SNSのグループで複数の中学校がつながり、チームとして地域で環境活動に取り組むようにもなってきています。

中学校での環境教育授業。
森林保全や農業課題に比べて、村人たちに馴染みが薄いのがごみ問題です。学校敷地内へのごみのポイ捨ても問題となっていました。まずは、ごみ分別ステーションを設置して分別を呼びかけましたが、関心を持たない村人が大多数でした。そこで「この活動は地域の環境保全だけでなく、子どもたちの学習環境を整えることにつながる」と丁寧に説明していきました。さらに、農業大学の学生たちが中心となって、リサイクル可能な資源ごみを天然資源環境局や工場に販売。得られた現金収入を活動の継続と学校での学用品の購入に活用しました。すると「子どもたちのより良い学校生活につながっている」との理解が広がり、昨年度は410名の村人がごみ分別に協力してくれました。
このほかに、学校では環境保全活動として、取り木手法を用いた果樹や有機野菜の栽培にも取り組み、苗木や農産物を地域の村人に販売しています。もともと良質な果樹から株分けしているため将来的に良い実がなり、種から育てるよりも早く生育すると、好評です。事業の継続には資金確保が欠かせません。さらなる販路拡大にも取り組んでいます。
いくら良い事業であっても、そこに住む人々が自ら変えていこうとしなければ何も変わりません。「卒業して自分の村に戻っても環境保全活動をやりたい」と言ってくれた農業大学の学生がいました。そんな地域の人々の熱い思いや行動に触れると、やっていて良かったと感じ、もっと頑張らなければと思います。

プラスチック製ごみ・紙ごみ・不燃ごみ・生ごみに分別。

資源ごみを販売し、中学校の環境活動継続の資金に。
 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード