



地球環境基金便り No.54 (2023年3月発行)




2050年までに脱炭素社会を実現するためには、多くの人のライフスタイルの転換が不可欠です。私たちが目指すのは、京都市において脱炭素ライフスタイルを選択し、実践する人を着実に増やすことです。
1997年、地球温暖化対策について国際的な約束として初めて採択された「京都議定書」。KYOTOは地球環境を語る世界中の人たちにとって、ひとつの共通語でもあります。そんな京都市では早くから環境対策に取り組み、2020年には、ピーク時に比べエネルギー消費量31・1%減を実現しています。しかし、家庭でのエネルギー消費量に目を向けると、ほぼ横ばいが続いています(クイズ参照)。これからさらに脱炭素を進めるためには、一人ひとりのライフスタイルの転換が必要なのです。
脱炭素への関心は高くても、実践につながらない人が多いのはなぜなのか?京都市が2019年におこなった環境基本計画市民アンケートでは「環境教育・学習や環境保全活動に関する情報が十分に得られていない」と感じている人が、約7割にのぼり、これまでの情報発信とは異なるアプローチの必要性を感じました。そこで2021年、京都市と連携し、若者を中心とする市民、事業者、学識者とともに「京都発脱炭素ライフスタイル推進チーム」を立ち上げ、的確で多面的な働きかけをおこなうための活動を始めました。



協会が京都市とともに事務局を務める、京都発脱炭素ライフスタイル推進チームが中心となり、市民の環境アクションを広げる多彩な情報を発信するWEBマガジン「2050MAGAZINE」。(https://doyoukyoto2050.city.kyoto.lg.jp)

「2050MAGAZINE」では、公園でコンポスト堆肥回収会を開催した「地域での生ごみ堆肥の活用推進プロジェクト」などを紹介。多くの人に情報が届くようさまざまな方法で情報を発信中。
2022年度からは地球環境基金の助成を受け、「脱炭素ライフスタイルの見える化」「市民の脱炭素ライフスタイル調査」「多様な手法を用いた市民参加型行動促進」を柱に、活動を進めています。
着実に脱炭素ライフスタイル実践者を増やすためには、まず市民のみなさんが本当はどう思っているのか、いったい何が脱炭素ライフスタイルにつながる行動のきっかけになるのかなど、現状を把握することが大切です。「市民の脱炭素ライフスタイル調査」では、誰に、どのように聞くかを、約1年かけ専門家とともに考え、アンケート内容を練り上げてきました。消費・移動・食・住という4つのカテゴリーごとに40の質問を設け、これから1000人へのアンケート調査が始まります。調査対象者には学生も多いため、「住」に対するアクションはしづらいことが予想されるので、「消費」や「移動」など身近な行動に関わる設問も盛り込みました。
この1年は下準備やヒント探しのフェーズでしたが、得るものがいくつもありました。
ひとつは、CO2削減だけでは行動変容の動機にはなりづらいということ。「脱炭素ライフスタイルの見える化」として、製品のCO2使用量がわかるカーボンフットプリントの活用を検討していたのですが、プレ調査として実施した小規模アンケートから、あまり効果的ではないことがわかりました。逆に、レストランで食べ残しの持ち帰りサービスがあれば積極的に利用したい人が多いなど、お得や便利さが伴うと、自然に行動が変わることがわかりました。「動機の見える化」も大切ですが、知っているけれどやらない理由を浮き彫りにする「障壁の見える化」、そしてその障壁をどう解消するかを考えることが重要だと感じています。
もうひとつ、いくらアイデアがあっても、それを実行するプレイヤーがいないと活動が進まないということも課題です。例えば、環境負荷をかけない農業を営む農家の方が、その取り組みを伝えながら販売したくても、売る場や人手がない……。これは今年、学生が農家で農業体験をし、さらに売り子となって、京都の中心地で地産地消につながる農産物イベントを開催することで実現できる予定です。プレイヤーになる市民や事業者を巻き込み、みんなで動くことが持続可能な活動には欠かせません。
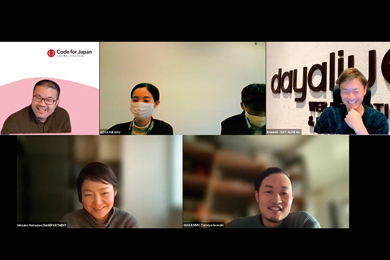
2023年1月に開催した、オンライン「広報検討会」。市民参加型行動促進を進めるために、地域振興や市民活動、デザインなどの分野で先進的な活動を続けている方たちをアドバイザーに迎え、どのような広報ツールが効果的かを議論。
2018年度からの3年間は「プラスチックごみ削減活動を通じた住民と観光客の持続可能な共存」をテーマに、地球環境基金の助成を受け活動をしていました。露店などでリユース食器を使う「祇園祭ごみゼロ大作戦」では、2019年に193店舗で18万個以上のリユース食器が導入され、2013年に比べて全体の廃棄物量を2万5千kg削減することができました。プラごみを出さず、食器を循環して使うというサーキュラーエコノミーにつながるこの取り組みは、今も続いています。全国のお祭り主催者らが視察に来ることもあります。
京都は発信力のある都市なので、目下進行中の脱炭素ライフスタイルの活動も、全国へ波及することが最終目標です。そのためにも、脱炭素ライフスタイルへの転換を実現できる「京都モデル」を作りあげたいと思っています。

「祇園祭ごみゼロ大作戦」で導入した
リユース食器。
 adobe
readerダウンロード
adobe
readerダウンロード