



地球環境基金便り No.55 (2023年9月発行)


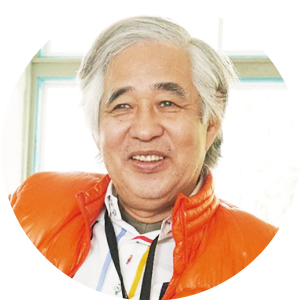

奄美大島は世界自然遺産の島であり、自然と人間の関わり豊かな土地です。しかし、町ではSDGsや環境文化を学ぶ場がなく、町内の幼稚園で実施したアンケートでは、普段の生活で土に触れる機会が「ある」と答えた母親は0%でした。
私たちはSDGsを広く学べる場をつくるために、2018年に活動を開始。2020年から地球環境基金の助成を受け、廃棄食材で生産をおこなう「リフード・コンセプト」を軸に、廃校を再活用しながら、奄美の自然や伝統文化を通して地域や環境を学ぶ体験型プログラムを開発・実践しています。文化の伝承と人の交流を促進し、地域循環共生圏のモデル地区になれればと思っています。

修繕した廃校が活動の拠点です。

鶏卵は新聞紙を容器にして、人の温かみと環境配慮のコンセプトが伝わるよう工夫して販売。
リフード・コンセプトの取り組みとしては、地域の病院と連携し、食事の食べ残しではなく、調理時に出る野菜くずや余ったお米などを回収し、鶏の餌に活用。鶏卵を生産したり、鶏から得られる糞を有機肥料にして有機農産物をつくったりしています。
体験会、ワークショップ、講演会は、これまでの2年間で計35回開催し、のべ539人が参加。手応えを感じています。
なかでも、集落の高齢者、地元の中高生、鹿児島大学の学生たちとの交流会は大成功。その後、大学生が自主的に大学と奄美の2拠点で活動する「奄美を知るサークル(ゆりむん)」を立ち上げ、循環型有機農業の体験や集落の人たちとの交流を継続。滞在中に仕入れた奄美の食材を、鹿児島のカフェで使うことも検討しているそうです。
今年の春には「給食をオーガニックへ」というテーマで、元農林水産大臣を迎えたイベントも実現。予想を超えた反響があり、島全域で取り組もう!という機運が高まっています。
こうした体験プログラムやイベントの充実は、行政との連携の賜物です。行政のネットワークを利用できたことで、町民に広く広報でき、参加者募集もできました。また、行政の仕組みに活動を組み込むことで、活動自体が持続可能なものになりました。地域循環共生圏の仕組みを継続するには、行政とのタッグが必要だと感じています。
地元の子も、都市部の子も、一人でも多くの若い人たちが、自然豊かな島で、地域資源を有効活用しながら暮らす価値や課題を体感し、未来の社会を担う人材になってほしいです。これからも多様な人たちと協力しながら、活動を広げていきたいと思っています。

あいがも農法でお米を育てる「泥んこ田植え体験」。子どもたちも素足で田んぼに入って苗を植えます。
 adobe
readerダウンロード
adobe
readerダウンロード