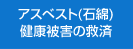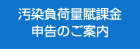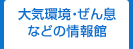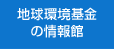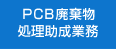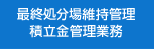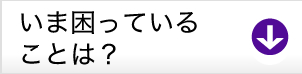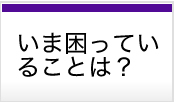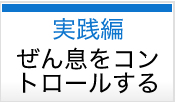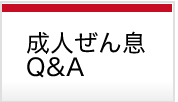あなたがいま困っているのは、どんなことですか?
高齢のぜん息患者さんへ
治療薬の進歩などにより、ぜん息が原因で亡くなる人は1980年に6,370人だったのに対し、2016年には1,454人注にまで減少しています。しかし、ぜん息で死亡している人の年齢をみると、89%が65歳以上の高齢者です。
高齢のぜん息患者さんは、ぜん息に加えてほかの病気を合併していることが多かったり、視力が落ちる、握力が弱くなるなどの身体機能の低下によって、治療にあたり注意しなければならない点が多くあります。
- 注:厚生労働省 平成28年人口動態統計
ここがポイント!
- 高齢者のぜん息は、COPDや心臓病など、ほかの病気を合併していることが多くあります。
- ぜん息治療には主に吸入薬が使われるため、正しく吸入できているか繰り返し指導を受けましょう。
- ぜん息を悪化させるインフルエンザや肺炎の予防接種を受けましょう。
- 自己管理が必要なぜん息治療には、家族や介護者のサポートが欠かせません。
高齢者のぜん息の特徴
 高齢者では、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)が見つからない「非アトピー型ぜん息」の割合が高い、という特徴があります。
高齢者では、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)が見つからない「非アトピー型ぜん息」の割合が高い、という特徴があります。
また、COPD(慢性閉塞性肺疾患)や心臓病をはじめとする、ほかの病気との合併が多くなることも大きな特徴です。とくに同じ呼吸器の病気であるCOPDを合併するとぜん息が重症化しやすくなり、呼吸機能が著しく低下してしまうため、注意が必要です。
ぜん息以外の病気がある場合には、その病気の主治医にぜん息のことを相談しましょう。また、ぜん息の治療をするときにも、ほかにどのような病気があるかを医師に必ず伝えるようにしましょう。
合併症の有無に関わらず、ぜん息と診断された場合には医師の指示に従って治療を継続し、常に気道の炎症を抑えておくことで、重症化の予防、ぜん息死の回避につながることを覚えておきましょう。
COPDについて詳しくは、ぜん息などの情報館慢性閉塞性肺疾患(COPD)基礎知識をご覧ください。
繰り返し吸入指導を受けましょう
 合併症の有無などによって、医師が選択する薬は異なりますが、ぜん息の治療では薬を気道に直接届けるために主に「吸入薬」が使われます。吸入薬を使用するうえでもっとも大切なことは、正しい吸入方法をマスターすることです。
合併症の有無などによって、医師が選択する薬は異なりますが、ぜん息の治療では薬を気道に直接届けるために主に「吸入薬」が使われます。吸入薬を使用するうえでもっとも大切なことは、正しい吸入方法をマスターすることです。
しかし、高齢になると視力や握力の低下がみられ、指先を使う細かい作業が困難になりがちです。そのために医師の指示通りに服薬できなかったり、自分では正しく吸入しているつもりでも薬が十分に気道の奥まで入っていない、ということが起こります。また、認知症や意欲の減退などによって操作手順の理解が難しい場合もあります。
吸入が上手にできない、操作を理解できないという場合は、医師や看護師、薬剤師などに、覚えられるまで吸入指導を繰り返してもらいましょう。また、どの種類の吸入薬であれば上手に吸入できるか、スペーサーや補助器具、ネブライザーを使用したほうがいいかなど、相談しながら治療を進めていきましょう。吸入がどうしてもうまくできないという場合には、貼るタイプの薬や飲み薬に変更するという方法もあります。また、家族や介護してくれるまわりの人たちに協力を求めるようにしましょう。
感染症を予防し、禁煙を
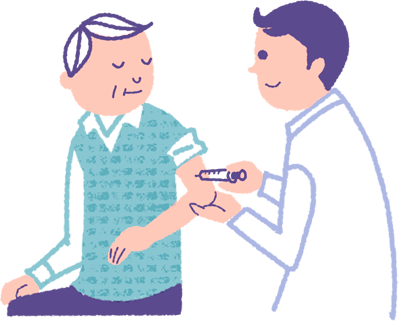 高齢になると免疫力の低下によりカゼやインフルエンザ、肺炎など呼吸器の感染症にかかりやすくなります。これらの感染症は、ぜん息を悪化させる大きな要因です。症状が急激に悪くなる「急性増悪」を招くと、ぜん息死につながることもあります。
高齢になると免疫力の低下によりカゼやインフルエンザ、肺炎など呼吸器の感染症にかかりやすくなります。これらの感染症は、ぜん息を悪化させる大きな要因です。症状が急激に悪くなる「急性増悪」を招くと、ぜん息死につながることもあります。
予防のためには、流行期前にインフルエンザの予防接種を受ける、肺炎を予防する「肺炎球菌ワクチン」の接種を受けることが有効です。65歳以上の方は、肺炎球菌ワクチンを初めて接種する場合、公費助成が受けられます注。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
また、うがいと手洗いを忘れずに行う、十分な睡眠と栄養をとり規則正しい生活を送ることも重要です。
さらに、喫煙はぜん息薬の効果を不十分にし、気道の炎症に悪影響を及ぼします。喫煙者の方は一刻も早く禁煙しましょう。
- 注:その年に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方で、初めて肺炎球菌ワクチンを受ける方が対象です。
日常生活の中で動きましょう
ぜん息やCOPDなどの呼吸器の病気があると、動くと苦しくなるために運動はもちろんのこと、日常生活でも動かなくなってしまうことが問題になっています。しかし、動かなくなると筋肉が減り、さらに動けなくなる、という悪循環に陥ることが知られています。
ぜん息治療の目標は、健康な人と変わらない生活を送ることです。高齢であっても適切な治療と自己管理で、この目標は達成することができます。
まずは、動いても苦しくならないよう治療をしっかりと行い、ぜん息をコントロールしましょう。無理に運動をしなくても、家事をしたり、買い物や散歩に出かけるなど日常生活の中で動くことで、呼吸機能にいい影響を与えることができます。
ご家族の方へ
高齢になると身体的な衰えに加え、認知機能や意欲の低下が起こります。しかし、ぜん息という病気は、医師に治療を任せればよいというものではなく、自分で薬を継続して使用するなど、自己管理が必要な病気です。また、医師に日ごろの様子や、吸入薬をきちんと使うことができているかなどを詳しく伝えることで、患者さんの生活に配慮した無理のない治療計画を立ててもらうことができます。そのため、高齢のぜん息患者さんの治療をスムーズに進めていくためには、家族や介護する方のサポートが欠かせません。
ぜん息はしっかりと治療すれば、合併症があっても健康な人とほとんど変わらない生活が送れる病気です。高齢だからとあきらめてしまうのではなく、「もっとよくなる」「もっと楽になる」という目標を患者さんと共有しながら、希望をもって治療に臨みましょう。
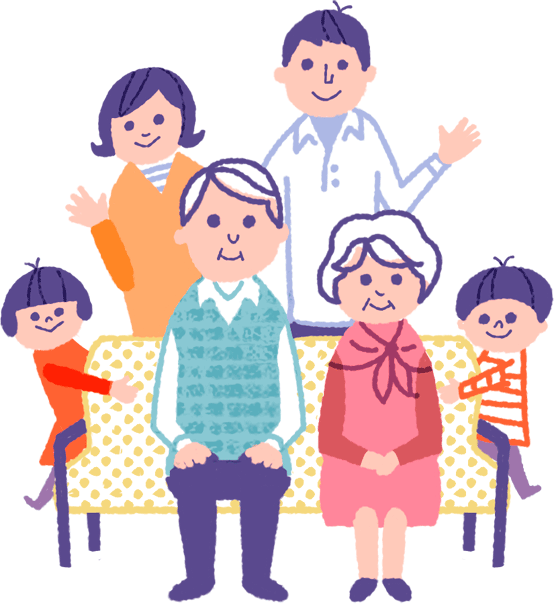
関連リンク
- 高齢のぜん息患者さんへ
- 思春期のぜん息患者さんへ
- 知識編ぜん息とは
-
- 自分のぜん息の状態を把握する
- コントロール状態を調べよう
- ピークフロー測定とぜん息日記
- 医療機関で客観的な評価を