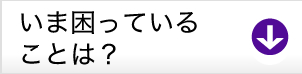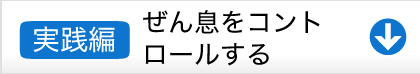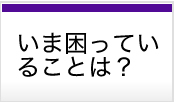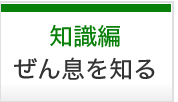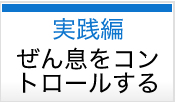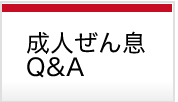知識編ぜん息を知る
治療
ぜん息の薬
ぜん息治療に使われる薬は大きく分けて「長期管理薬(コントローラー)」と「発作治療薬(リリーバー)」に分けられます。治療の基本は、気道の炎症を抑える「長期管理薬」です。
ここがポイント!
- ぜん息治療の基本は、気道の炎症を抑える吸入ステロイド薬を基本とした「長期管理薬」です。
- コントロール良好な状態を長く保つことができれば、徐々に薬の量や種類は減らすことができます。
- 吸入ステロイド薬は副作用も少なく、長期に安全に使うことができます。
気道の炎症を抑え発作を予防する「長期管理薬」
 「長期管理薬」は2本だてです。最も重要なひとつめの薬剤は「吸入ステロイド薬」です。ぜん息の症状は気道の炎症が原因で起こります。その炎症を抑え、発作を予防するのが「吸入ステロイド薬」です。「吸入ステロイド薬」が普及してから、ぜん息で亡くなる人や入院する人の数が大幅に減少しました。
「長期管理薬」は2本だてです。最も重要なひとつめの薬剤は「吸入ステロイド薬」です。ぜん息の症状は気道の炎症が原因で起こります。その炎症を抑え、発作を予防するのが「吸入ステロイド薬」です。「吸入ステロイド薬」が普及してから、ぜん息で亡くなる人や入院する人の数が大幅に減少しました。
もうひとつの薬剤は、気管支を広げる「気管支拡張薬」です。「気管支拡張薬」には、長時間作用性β2刺激薬、テオフィリン徐放製剤、長時間作用性抗コリン薬などがあります。ロイコトリエン受容体拮抗薬やテオフィリン製剤は、気管支拡張作用と抗炎症作用をあわせもっています。症状に応じて、これらの中からひとつ、あるいはいくつかの薬剤を用います。
吸入ステロイド薬と長時間作用性β2刺激薬を配合した薬剤は、1剤で炎症を抑え、気管支を拡張するため、広く用いられています。
長期管理薬は長期間使ってはじめて本当の効果が現れる薬です。使い始めてすぐに症状はおさまりますが、気道の中の炎症は続いています。症状がないからと途中でやめてしまわず、医師の指示通りに続けることが重要です。
ただし、2~4週間使用しても症状が改善しない場合は、ぜん息でない可能性もあるため、主治医に相談しましょう。
長期管理薬の種類と働き
- 1.副腎皮質ステロイド薬
-
- 1)吸入ステロイド薬 吸入薬
- ぜん息治療の中心となる薬です。薬を吸い込んで直接肺まで届けることで、炎症を抑えます。
- 商品名:アズマネックス®、オルベスコ®、キュバール®、パルミコート®、フルタイド®など
- 2)経口ステロイド薬 飲み薬
- 全身性に働くステロイド薬で、炎症を抑える強い作用があります。副作用に十分な注意が必要です。
- 商品名:プレドニゾロン®、プレドニン®、メドロール®、リンデロン®、セレスタミン®(抗ヒスタミン薬との合剤)など
- 2.長時間作用性β2刺激薬
- 交感神経を刺激して、気管支を広げる働きがあります。長期管理薬として使う場合は、吸入ステロイド薬と併用するのが基本です。
- 商品名:セレベント® 吸入薬 、ホクナリンテープ® 貼り薬 など
- 3.吸入ステロイド薬/長時間作用性β2刺激薬配合剤 吸入薬
- 1剤で気管支の炎症を抑える効果と、気管支を広げる効果があります。
- 商品名:アドエア®、シムビコート®、フルティフォーム®、レルベア®など
- 4.ロイコトリエン受容体拮抗薬 飲み薬
- 気管支を収縮させる作用に深く関係しているロイコトリエンという化学伝達物質をブロックする働きがあります。
- 商品名:オノン®(プランルカスト)、キプレス®・シングレア®(モンテルカスト)など
- 5.テオフィリン徐放製剤 飲み薬
- ゆっくり溶ける作用時間の長い薬で、気管支を広げる働きがあります。また、弱いながらも、抗炎症作用があることも報告されています。
- 商品名:スロービッド®、テオドール®、テオロング®など
- 6.長時間作用性抗コリン薬 吸入薬
- 気管支の収縮をうながすアセチルコリンという物質をブロックし、気管支の収縮を抑える働きがあります。
- 商品名:スピリーバレスピマット®
- 7.ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬 飲み薬
- 気管支の収縮を引き起こす物質の放出を抑えたり、アレルギー炎症を起こす物質の産生を抑えたりします。
- 商品名:アイピーディ®、アレジオン®、インタール®、ザジテン®、ドメナン®、ベガ®、リザベン®など
発作を止める薬「発作治療薬」
 発作が起きたときに使うのが、発作治療薬(リリーバー)です。気管支を広げる働きがあり、すぐに効き目が現れます。しかし、気道の炎症を抑える働きはないので、ぜん息の根本的な治療にはなりません。長期管理薬を使わずに発作治療薬だけに頼っていると、気道の炎症が進み、ぜん息が悪化してしまいます。
発作が起きたときに使うのが、発作治療薬(リリーバー)です。気管支を広げる働きがあり、すぐに効き目が現れます。しかし、気道の炎症を抑える働きはないので、ぜん息の根本的な治療にはなりません。長期管理薬を使わずに発作治療薬だけに頼っていると、気道の炎症が進み、ぜん息が悪化してしまいます。
発作治療薬の種類と働き
- 1.短時間作用性β2刺激薬 吸入薬 飲み薬
- 交感神経を刺激して、気管支を広げる働きがあります。
- 商品名:サルタノール®、メプチンエアー®、アイロミール®など
- 2.テオフィリン薬 飲み薬
- 気管支の緊張をとって、気管支を広げる働きがあります。
- 商品名:ネオフィリン®など
薬の量は減らせます(治療のステップダウン)
医師はまず、問診で患者さんの症状がどのくらいの頻度で起こっているのかなどを把握するとともに、呼吸機能検査や呼気NO検査の結果などをもとに、患者さんの状態を判定します。そして、一人ひとりの重症度に応じて、使う治療薬の種類や量、組み合わせなどを決定します。(治療ステップ。表1~2参照)
(表1)未治療患者さんの症状と目安となる治療ステップ
-
(軽症間欠型相当)
- 症状が週1回未満
- 症状は軽度で短い
- 夜間症状は月に2回未満
- 治療ステップ1
- (軽症持続型相当)
- 症状が週1回以上、しかし毎日ではない
- 月1回以上日常生活や睡眠が妨げられる
- 夜間症状は月2回以上
- 治療ステップ2
- (中等症持続型相当)
- 症状が毎日ある
- 短時間作用性吸入β2刺激薬がほぼ毎日必要
- 週1回以上日常生活や睡眠が妨げられる
- 夜間症状が週1回以上
- 治療ステップ3
- (重症持続型相当)
- 治療下でもしばしば増悪
- 症状が毎日ある
- 日常生活が制限される
- 夜間症状がしばしば
- 治療ステップ4
- 治療ステップ1
- 治療ステップ2
- 治療ステップ3
- 治療ステップ4
- (喘息予防・管理ガイドライン2018を一部改変)
(表2)治療ステップにあわせた治療薬の目安
-
- 長期管理薬
-
- 基本治療
-
治療ステップ1
吸入ステロイド薬
(低用量)上記が使用できない場合は以下のいずれかを用いる
- ロイコトリエン受容体拮抗薬
- テオフィリン徐放製剤
※症状がまれなら必要なし
- 追加治療
- ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬
-
治療ステップ2
吸入ステロイド薬
(低~中用量)上記で不十分な場合に以下のいずれか1剤を併用
- 長時間作用性β2刺激薬(配合剤使用可注1)
- 長時間作用性抗コリン薬
- ロイコトリエン受容体拮抗薬
- テオフィリン徐放製剤
- 追加治療
- ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬
-
治療ステップ3
吸入ステロイド薬
(中~高用量)上記に下記のいずれか1剤、あるいは複数を併用
- 長時間作用性β2刺激薬(配合剤使用可注1)
- 長時間作用性抗コリン薬
- ロイコトリエン受容体拮抗薬
- テオフィリン徐放製剤
- 追加治療
- ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬
-
治療ステップ4
吸入ステロイド薬
(高用量)上記に下記の複数を併用
- 長時間作用性β2刺激薬(配合剤使用可注1)
- 長時間作用性抗コリン薬
- ロイコトリエン受容体拮抗薬
- テオフィリン徐放製剤
- 抗IgE抗体(ゾレア®)注2、注3
- 抗IL-5抗体(ヌーカラ®)注3
- 抗IL-5受容体抗体(ファセンラ®)注3
- 経口ステロイド薬注3
- 気管支サーモプラスティ(BT)注3
- 追加治療
- ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬
-
- 追加治療
- ロイコトリエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬(各治療ステップ共通)
-
- 発作治療
- 短時間作用性吸入β2刺激薬注1(各治療ステップ共通)
- 注1:ブデソニド/ホルモテロール配合剤(商品名:シムビコート®)で長期管理を行っている場合には、同剤を発作治療にも用いることができる。長期管理と発作治療を合わせて1日8吸入までとするが、一時的に1日合計12吸入まで増量可能である。ただし、1日8吸入を超える場合は速やかに医療機関を受診すること。
- 注2:通年性吸入アレルゲンに対して、陽性かつ血清総IgE値が30~1,500IU/mLの場合に適用となる。
- 注3:長時間作用性β2刺激薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬などを吸入ステロイド薬に加えてもコントロール不良の場合に用いる。
- (喘息予防・管理ガイドライン2018を一部改変)
ぜん息治療における大きな目的は、症状や発作が起こらない状態(コントロール良好な状態)を保つことです。
該当するステップの治療を行い、症状が出ない状態が3~6か月持続すれば、治療をステップダウン(薬の種類や量を減らす)することも可能です。
症状が出なくなったからと自分の判断で治療を中止してしまわずに、医師の指示通り治療を続け、コントロール良好な状態を持続できるようにしましょう。
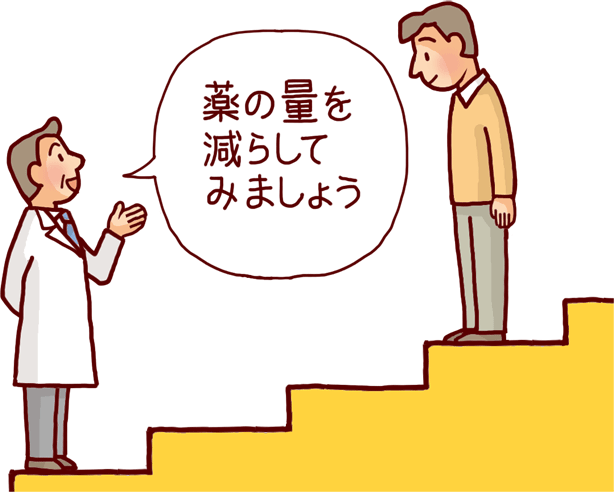
薬の副作用対策
経口ステロイド薬、注射でのステロイド薬投与の場合
ステロイド薬は、炎症を抑える強力な作用をもち、約70年前から使用されています。しかし、このステロイド薬を飲み薬や注射などで長期間使用すると、薬が全身に作用するためさまざまな副作用(体重増加、高血圧、糖尿病、骨粗しょう症、脂質異常症、胃潰瘍、感染症、副腎不全、白内障など)が生じることがあります。
- <対策>
-
- 高血圧、糖尿病、脂質異常症、感染症、骨粗しょう症などが起きていないか、定期的に検査(血液、レントゲン、骨密度検査など)を受けましょう。
- ステロイド骨粗しょう症に関しては、服薬で予防する方法もあるため、主治医に相談しましょう。
- 体重増加はぜん息の悪化要因です。体重を増やさないように、食生活を工夫しましょう。
吸入ステロイド薬の場合
ステロイド薬の副作用のリスクを減らす工夫を施された薬が、現在のぜん息治療の中心となっている「吸入ステロイド薬」です。吸入ステロイド薬は、気道だけに作用する薬であるため、通常の投与量では全身の副作用はほとんどなく、長期に安心して、小児から高齢者、妊娠中の方でも使用できます。
吸入ステロイド薬の副作用としては、声がかれたり、口の中に残ると粘膜の免疫を抑制してしまい、カンジダというカビの一種が増えたりすることがあります。
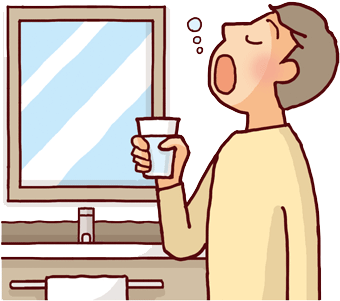
- <対策>
- 口の中のカンジダによる感染症を防ぐため、吸入後には必ずうがいをしましょう。「ガラガラ」うがいが難しい場合は、「ブクブク」して飲み込んでしまっても大丈夫です。それでも、患者さんによっては、声がれなどが出ることもありますが、その場合は、吸入ステロイド薬の使用をあきらめるのではなく、薬剤の種類を変えることによって対処できることが多くあります。
気管支拡張薬の場合
気管支拡張薬には、特有の副作用がいくつかあります。
- β2刺激薬
- 手の震え、動悸、脈が速くなる、筋肉がつるなどの症状が出ることがあります。
- 抗コリン薬
- 口が渇く、男性の場合に尿が出にくくなるなどの症状が出ることがあります。また、前立腺肥大や閉塞隅角緑内障のある方は、使用することができません。
- テオフィリン薬
- 吐き気、頭痛、動悸などを認めることがあります。
- <対策>
- 治療を始めた後に、気になる症状があれば担当医に相談しましょう。薬剤をうまく選んで副作用をなくすことが可能です。
関連リンク
- 治療 ぜん息の薬
- 日常生活におけるぜん息悪化の要因
- そのほかの治療法
-
- 自分のぜん息の状態を把握する
- コントロール状態を調べよう
- ピークフロー測定とぜん息日記
- 医療機関で客観的な評価を