

地球環境基金便り No.47 (2019年9月発行)
特集森林(もり)をつくる、
人をつくる

「森のようちえん」で丸太の皮むきに挑戦する幼児たち
掛川市倉真(くらみ)地区は地区の約7割を森林が占める中山間地域ですが、そのほとんどは林業が成り立たない小規模区画民有林です。当団体は13年にわたり、その森林所有者の理解を得ながら荒廃した森林の間伐に取り組み、地球環境基金や地方公共団体の助成を受け、これまでに間伐面積を450ヘクタールまで拡大。林内の下層植生が回復するなど効果が出ています。
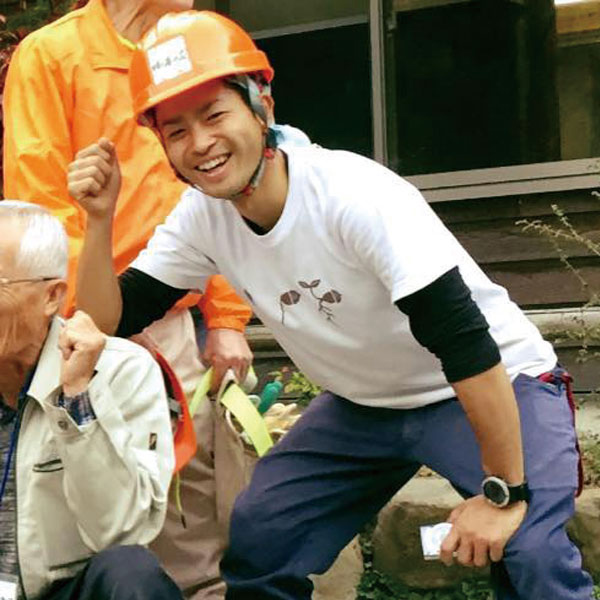
お話を伺った事務局の大石 淳平さん
しかしこれまでの活動は、長年放置されてきた荒廃森林に風穴を開けたにすぎません。今後も所有者による保全管理は期待できず、放っておけば数年で元の状態に戻ってしまうことでしょう。そこで私たちは、所有者に代わって当団体が持続的に森林を経営管理できるしくみを構築するとともに、森林や里山を社会全体の共有財産として「分かち合う=シェアする」ことによって将来にわたり豊かな森林が維持されることを目指し、取り組んでいます。
森林・里山を「シェアする」とは、森林・里山という空間とその恵みに直に触れ、その心地よさや楽しさ、厳しさ、大切さを家族や仲間と体験を通じて分かち合うことです。その代表的な活動が、幼児を対象に毎月2回開催している「森のようちえん」です。再生しつつある倉真地区の森林を活用し、山の散策、川遊び、植樹、キャンプファイヤーなどのほか、ときには子どもにマッチを握らせ火をおこしたり、のこぎりで木を切ったりするプログラムもあります。幼児の保護者からは「自然への興味が強くなり、家でも図鑑を見ながら生き物観察や採取をしていて、心豊かに育っていると感じる」「体力がついて、よく歩くようになった」「火の怖さを知ったようで、その怖さを親に教えてくれる」といった声が聞かれるなど好評で、18年度は延べ600人以上が参加しました。
今後は森のようちえんを継続するとともに、その参加者を軸に乳幼児から小学生までの子どもたちとその保護者が継続して森と関われるプログラムの構築も考えています。

里山をシェアする体験プログラム「里山ガイドウォーク」

地球環境基金助成事業で商品化した「Grace of Forest 森の恵み石けん」。時ノ寿の森の森林資源であるヒノキの葉とクズのエキスからできた、合成化合物、合成界面活性剤無添加の化粧石けんは、街で暮らす人へ森の恵みを届けるツールの一つとして販売されているほか、掛川市のふるさと納税の返礼品にも採用されている
「いのちの源」といわれ、昔から人の営みとともに歩んできた森林・里山が荒廃しています。持続的に保全するためには「人と森との関係を紡ぎ直す」ことが重要です。里山に暮らす人、都市に暮らす人、それぞれが森林・里山に異なる価値観をもっています。また直接森を訪れ実体験を通じてその価値を享受する人もいれば、都市に暮らしながら森の恵みを暮らしに取り入れる人もいます。どんなかたちであっても、多様な森との関わり方がより多くの人の暮らしに存在することが当たり前になれば、それが将来にわたり豊かな森林を維持することにつながると信じ、今後も活動を継続していきます。

 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード