

地球環境基金便り No.48 (2020年3月発行)

自然との関わりあいが薄れてきている今だからこそ、周りの自然との共存を「自分事」ととらえ、地域を盛り上げていく必要がある、と同団体理事長の松井宏光さんは話します。「オオキトンボの保全活動をひとつのきっかけとして、地域の人たちがより里地全体のことを考え、自らアクションを起こすようになってほしいです。オオキトンボが生息する環境が、里地の他の生き物、農作物にとってもよい影響をもたらし、この地域にとって大きな魅力になると思います。そのために、私たちはこれからも調査や研究を積み重ね、地域の人たちがオオキトンボに興味をもってもらえるように、そして、里地の魅力が広く認知されるように、楽しい機会をつくっていきたいです」
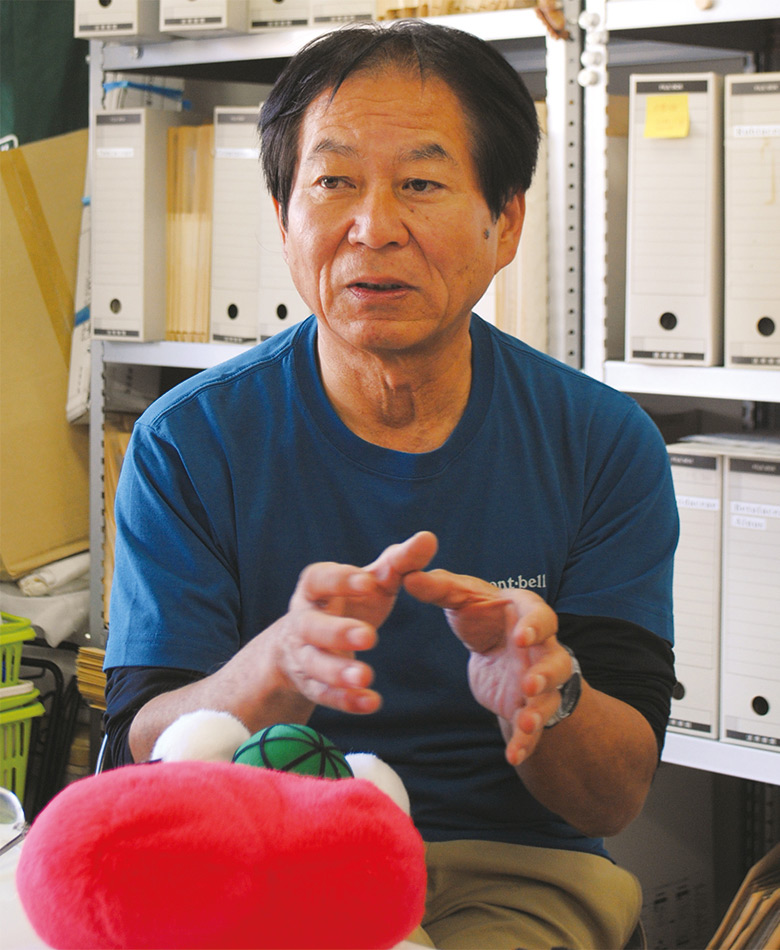
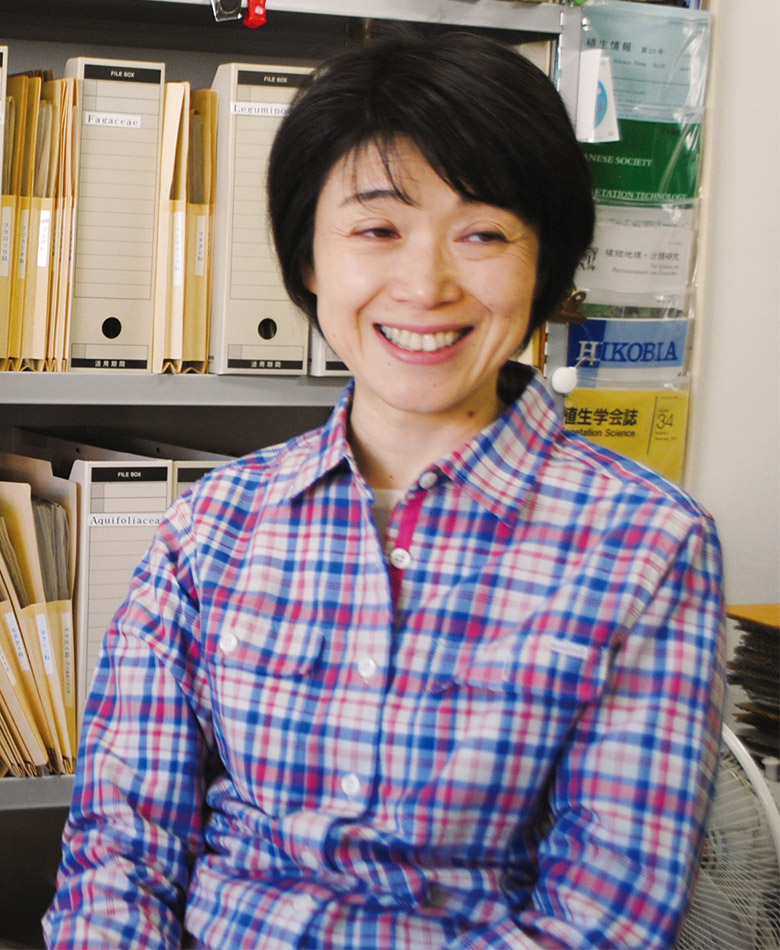
お話を伺った特定非営利活動法人 森からつづく道 理事長の松井宏光さんと事務局長の黒河由佳さん

愛媛県立衛生環境研究所
生物多様性センター 農学博士
久松 定智さん
オオキトンボの保全事業では主に調査計画の策定、現地調査、結果の集約に協力するほか、観察会やセミナーでオオキトンボについて説明を行っています。
オオキトンボの存在を地域の人たちに知ってもらえるのは嬉しいです。特に子どもたちが関心をもってくれることは、地域にとっても大切なことだと感じます。愛媛県にとってオオキトンボは美しい自然を未来に残すためのシンボル。みなさんにそう思ってもらえるよう、活動を続けていきます。

オオキチくん
 adobe readerダウンロード
adobe readerダウンロード
保全活動
保全活動その1: 調査をして根拠となるデータを集める!
保全の必要性を理解してもらうためには、説得力のある調査データが必要。調査、研究に力を入れオオキトンボの生活史について、不足しているデータを集めています。写真2は調査のために羽化殻を収集している様子です。
保全活動その2: 保全活動の機運醸成を高め、将来を見据える!
保全活動を続けていくうえで、子どもたちと交流できたことは大きな成果。学校側も協力してくれて、家族参観日でオオキトンボの発表をしてくれました。
保全活動その3: オオキトンボのことをみんなに知ってほしい!
オオキトンボの情報を下敷きにしたり、オオキトンボをはじめ、里地の生き物情報を盛り込んだ『オオキチくん通信』を発行したりして、地域の人たちに情報を発信しています。